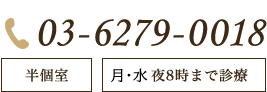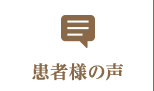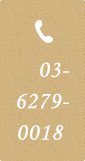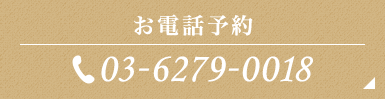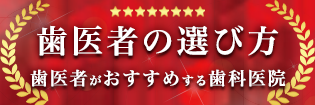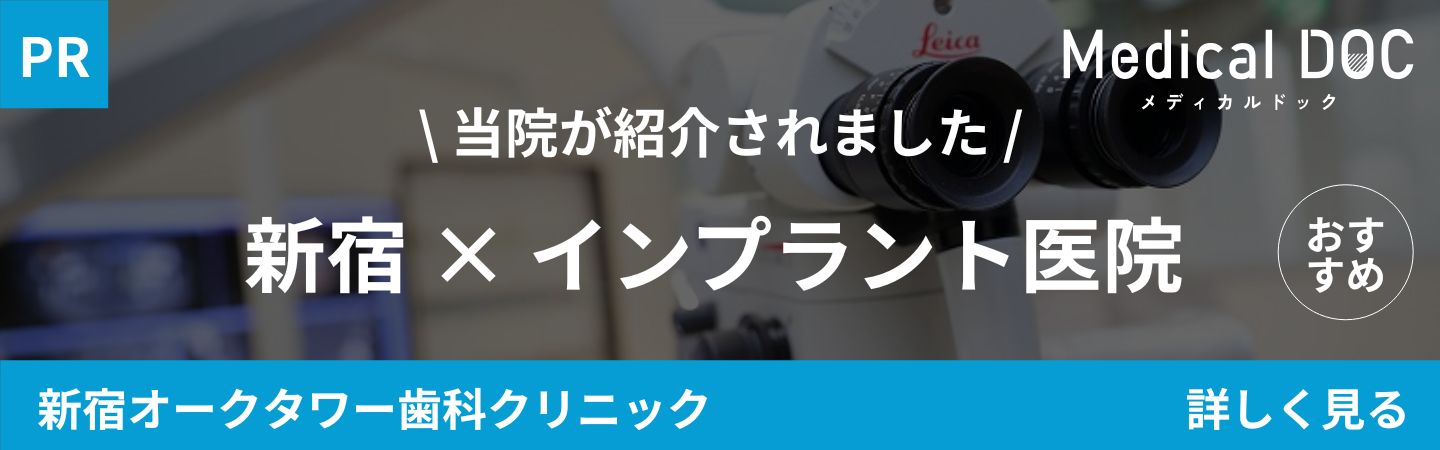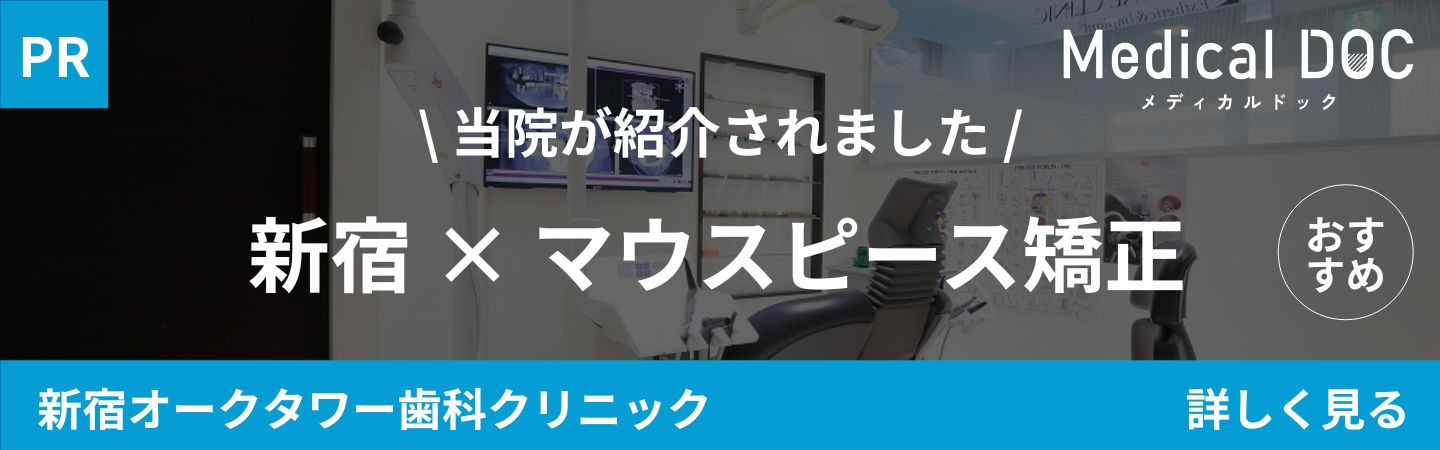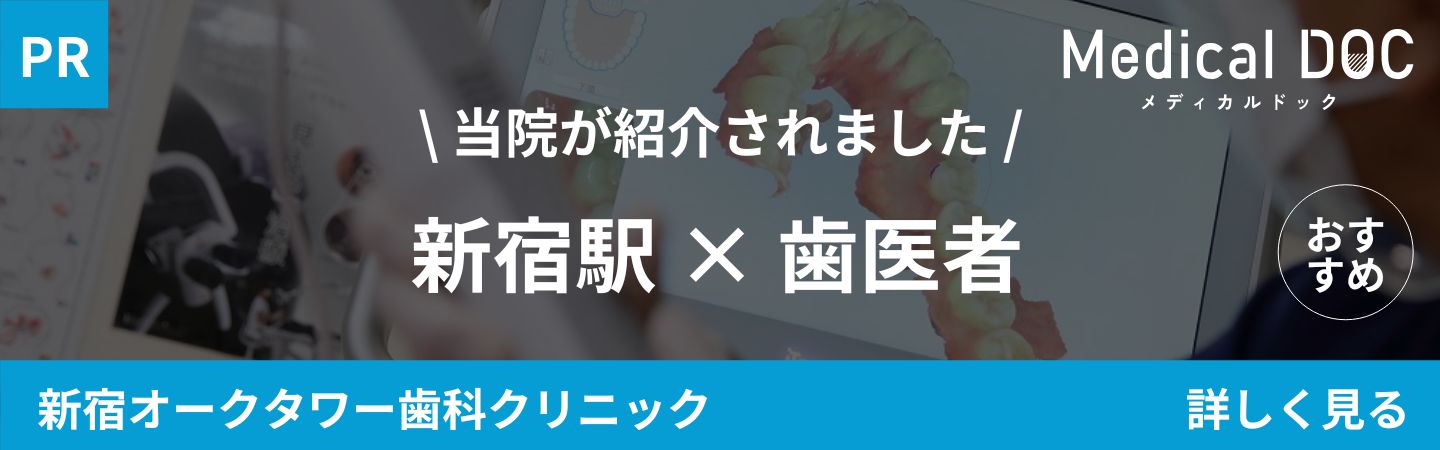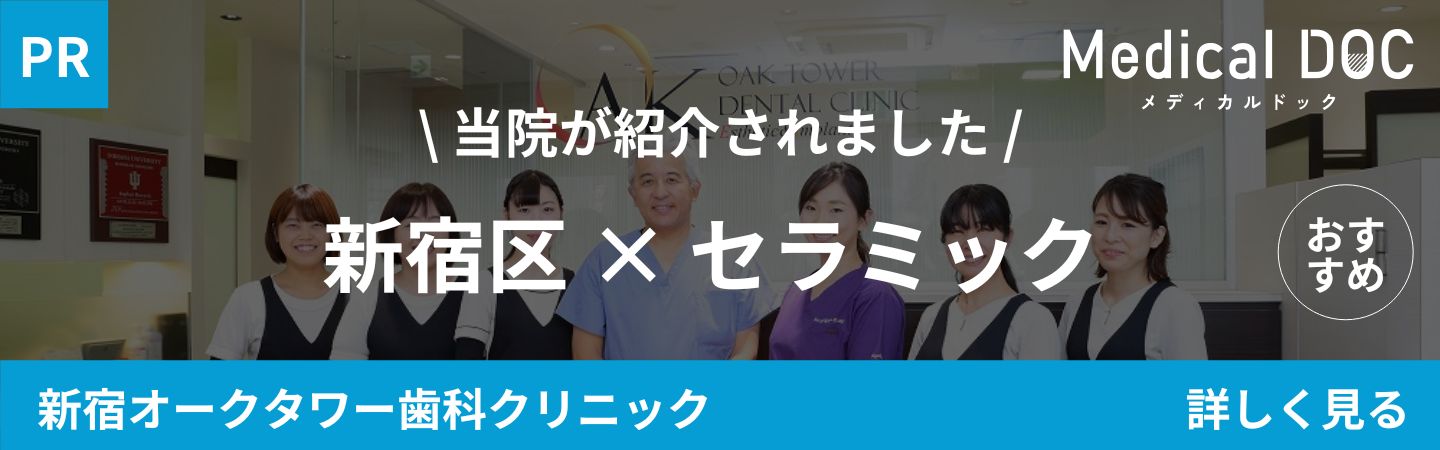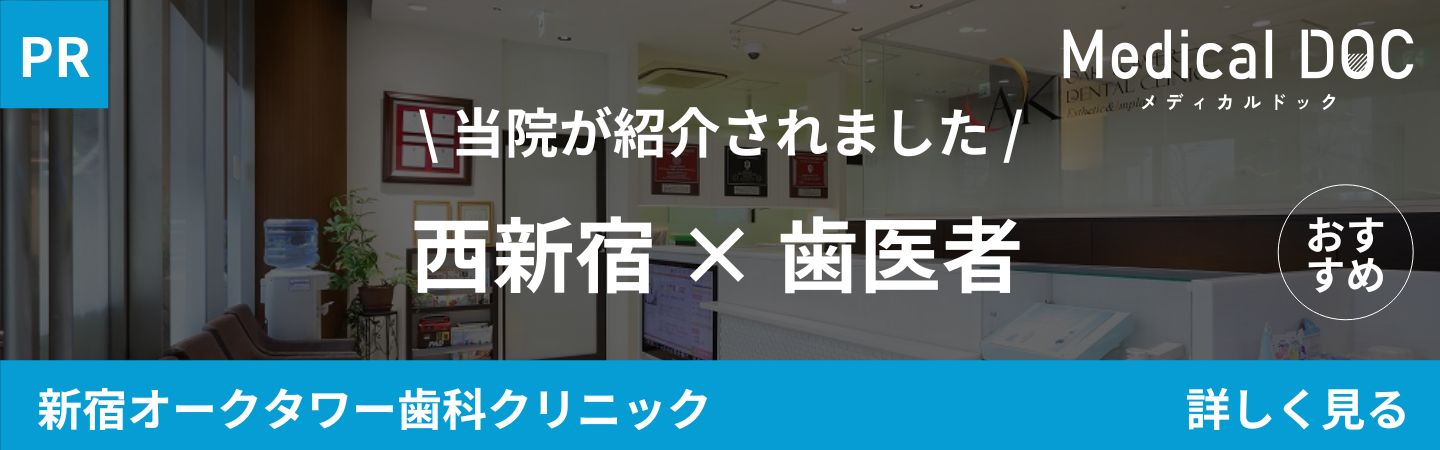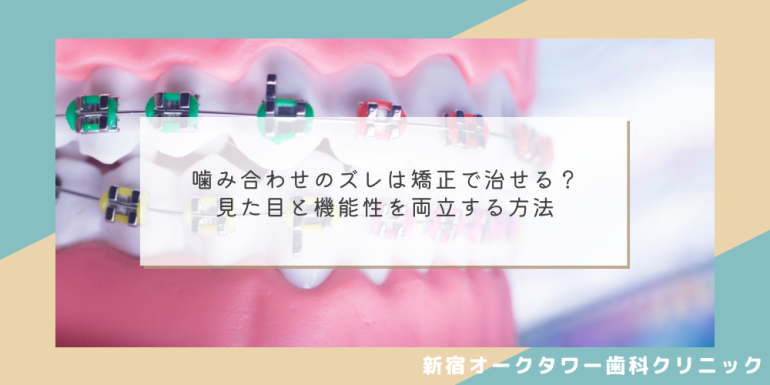
新宿オークタワー歯科クリニックです。
噛み合わせのズレは、見た目の問題だけでなく、頭痛や肩こり、顎の不快感など、全身のさまざまな不調の原因となることがあります。このような悩みを抱えている方にとって、歯列矯正治療は見た目の美しさだけでなく、お口の健康と体の機能性を向上させる有効な解決策となります。この記事では、噛み合わせのズレが引き起こす問題から、その原因、そして矯正治療でどのように改善できるのかを詳しく解説し、悩みの解決に役立つ具体的な情報を提供します。
その不調、噛み合わせのズレが原因かも?セルフチェックと放置するリスク
原因不明の頭痛や肩こり、あるいは顎の違和感や「カクカク」といった音に悩まされていませんか?これらの不調は、もしかしたら噛み合わせのズレが根本的な原因かもしれません。噛み合わせの乱れは、見た目の問題だけでなく、全身の健康にまで影響を及ぼすことがあります。このセクションでは、ご自身の噛み合わせに問題がないかを確認できるセルフチェックの項目、そして噛み合わせがズレてしまう主な原因、さらに放置することによってどのようなリスクが生じるのかを詳しく解説していきます。
こんな症状はありませんか?噛み合わせのズレのサイン
ご自身の噛み合わせにズレがないか、以下の項目でセルフチェックをしてみてください。一つでも当てはまる症状があれば、噛み合わせの乱れが原因となっている可能性があります。
食事の際に片側ばかりで噛んでしまう、口を開け閉めする際に顎がカクカク鳴ったり、痛みを感じたりする、鏡で顔を見たときに左右が非対称に見える、といったことはありませんか。また、食事中に頬の内側や唇を噛んでしまうことが多い、滑舌が悪く発音しにくい言葉がある、といった症状も噛み合わせのズレが影響している可能性があります。
さらに、原因がはっきりしない頭痛や肩こりが慢性的に続く、めまいや耳鳴りがするといった全身の不調も、噛み合わせの悪さが関連していることがあります。これらの症状は、口腔内の問題が全身に及ぼす影響を示唆していますので、気になる症状があれば専門家に相談することをおすすめします。
なぜ噛み合わせはズレる?主な3つの原因
噛み合わせのズレは、日常生活におけるさまざまな要因や、生まれ持った骨格の特徴によって引き起こされます。このセクションでは、噛み合わせが乱れる主要な原因として、「遺伝的な骨格の問題」「口呼吸や頬杖などの日常的な癖」「顎の成長異常」の3つに焦点を当てて詳しく解説します。それぞれの原因がどのように噛み合わせに影響を及ぼすのかを理解することで、ご自身の状況を把握する手助けとなるでしょう。
遺伝的な骨格の問題
噛み合わせのズレの最も根深い原因の一つとして、遺伝によって受け継がれる顎の骨格的な特徴が挙げられます。例えば、親から子へと、上顎と下顎の大きさのバランスや、顎全体の形、位置関係が受け継がれることがあります。これにより、上下の顎の成長に不調和が生じ、噛み合わせにズレが生じることがあります。
具体的には、上顎に対して下顎が極端に小さい、あるいは大きいといった顎の前後的な位置関係の異常や、顎が左右どちらかに歪んでいるといった骨格的な非対称性が挙げられます。このような骨格の不調和は、歯並びそのものにも影響を与え、結果として正しい噛み合わせを妨げることがあります。このような状態は、専門的には「顎変形症」と呼ばれることもありますが、遺伝的な要素が強く関与しているケースも少なくありません。
口呼吸や頬杖などの日常的な癖
無意識に行っている日常的な癖が、長期的に見ると顎の成長や歯並びに悪影響を及ぼし、噛み合わせのズレを引き起こす大きな原因となることがあります。これらの癖は、持続的に顎や歯に不適切な力を加え、骨格や歯の位置を徐々に変化させてしまうためです。
具体的な癖としては、「口呼吸」が挙げられます。口呼吸は、舌の位置が低くなり、上顎の成長を妨げたり、歯列を狭めたりする原因となり得ます。また、「頬杖」をつく癖は、顎に偏った力が加わり、顎の骨格や歯並びを歪ませる可能性があります。さらに、「舌で前歯を押す癖(舌癖)」や「片側ばかりで噛む癖」も注意が必要です。舌癖は前歯の隙間を広げたり、出っ歯にしたりすることがあり、片側噛みは顎関節への負担を増加させ、顔の左右差を生じさせることにつながります。
これらの癖は、一見すると些細な行動に思えますが、長期間にわたって繰り返されることで、噛み合わせのバランスを大きく崩してしまうことがあるため、意識して改善することが重要です。
顎の成長異常(顎変形症など)
噛み合わせのズレの大きな原因の一つに、顎の骨の成長過程で生じる異常があります。これは、単に歯並びの問題にとどまらず、顎の骨格そのものに不調和がある状態を指し、その代表的なものが「顎変形症」です。顎変形症とは、上下の顎の骨の大きさ、形、または位置関係に著しいずれがある状態をいいます。
顎の成長異常の原因は多岐にわたります。遺伝的要因だけでなく、成長期のホルモンバランスの乱れや、病気、外傷などが影響することもあります。例えば、下顎が過剰に成長して受け口になったり、逆に下顎の成長が不十分で下顎後退(いわゆる「出っ歯」の状態)になったりすることがあります。
このような顎の成長異常がある場合、歯並びだけを整えても噛み合わせの根本的な改善にはつながりません。骨格レベルでの問題であるため、場合によっては歯列矯正治療だけでなく、顎の骨を切って位置を修正する外科手術が必要となることもあります。顎変形症は、見た目の問題だけでなく、発音や咀嚼機能、さらには顎関節の健康にも影響を及ぼす可能性があるため、専門的な診断と治療が重要になります。
放置は危険!顎関節症や不定愁訴につながる可能性
噛み合わせのズレは、見た目だけの問題として軽視されがちですが、実は全身の健康にまで影響を及ぼすことがあります。噛み合わせが悪い状態を放置すると、顎の関節に過度な負担がかかり、さまざまな不調を引き起こす可能性が高まります。
特に注意したいのが「顎関節症」です。顎関節症は、口を開け閉めする際に顎の関節から「カクカク」という音がしたり、痛みを感じたり、あるいは口が大きく開けられなくなるといった症状が現れる病気です。噛み合わせのズレによって顎関節に常に無理な力が加わることで、関節円板というクッションがずれたり、骨が変形したりすることが原因となります。
さらに、噛み合わせの悪さが全身に影響を及ぼし、「不定愁訴」と呼ばれる原因不明の不調を引き起こすこともあります。慢性的な頭痛、肩こり、首の痛み、めまい、耳鳴りなどがその例です。これは、噛み合わせのバランスが崩れることで、顎を支える筋肉だけでなく、首や肩の筋肉にも過緊張が生じ、全身のバランスが乱れることによって発生すると考えられています。また、下顎が小さい「下顎後退」のような特定の顎の状態は、睡眠中に気道が狭くなりやすいため、睡眠時無呼吸症候群のリスクを高める可能性も指摘されています。このように、噛み合わせの問題は、単なる口腔内のトラブルにとどまらず、全身の健康に直結しているため、放置せずに専門家に相談することが大切です。
噛み合わせのズレは矯正で治せる?原因別の治療アプローチ
噛み合わせのズレは、見た目の問題だけでなく、全身の不調にもつながる可能性があるため、適切な治療によって改善を目指したいと考える方は多いでしょう。しかし、一言に「噛み合わせのズレ」といっても、その原因は人それぞれで異なります。そのため、治療法もその原因に応じて最適なアプローチを選ぶ必要があります。このセクションでは、噛み合わせのズレを矯正治療で治せるのかという疑問にお答えし、主に「歯並びが原因の場合」「顎の骨格が原因の場合」「不定愁訴を伴う場合」という3つのケースに分けて、それぞれの具体的な治療方法について詳しく解説していきます。
歯並びが原因の場合:矯正装置による治療
顎の骨格には大きな問題がなく、主に個々の歯の生え方や傾き、位置の異常によって噛み合わせが悪くなっているケースは少なくありません。このような場合は、歯科矯正装置を用いて歯を適切な位置に動かし、正しい噛み合わせを構築することが可能になります。
治療では、ワイヤー矯正やマウスピース矯正といった装置を使用し、歯に継続的な力を加えることで、少しずつ歯を移動させていきます。骨格的なズレが軽度であれば、歯の移動だけで見た目と機能性を改善する「カモフラージュ治療」というアプローチも選択肢の一つとなります。この治療法は、外科手術を伴わないため身体的負担が少ないというメリットがあります。しかし、歯の移動だけで骨格的なズレを完全に補うことには限界があり、口元の突出感を大きく改善したい場合などには、期待するほどの効果が得られない可能性もあります。そのため、担当医とよく相談し、自身の骨格の状態や希望する仕上がりを考慮した上で、治療計画を立てることが重要です。
顎の骨格が原因の場合:外科手術を併用した矯正治療
歯並びの問題だけでなく、顎の骨格そのものにズレや大きさの不調和がある「顎変形症」のような重度のケースでは、歯列矯正治療だけでは理想的な噛み合わせや顔のバランスを得ることが難しい場合があります。このような状況では、「顎矯正手術(外科手術)」を併用した矯正治療が必要となります。
顎矯正手術を伴う矯正治療は、主に次の3つのステップで進められます。まず「術前矯正」として、手術に備えて顎の骨格のズレが目立つように歯並びを整えます。次に、「顎矯正手術」が行われ、口腔外科医が顎の骨を切って、上下の顎の位置や大きさを調整し、正しい噛み合わせと顔のバランスに近づけます。手術は全身麻酔下で行われ、入院が必要になることが一般的です。最後に、「術後矯正」として、手術で動かした顎の位置に合わせて、細かく歯並びや噛み合わせを調整し、治療を完了させます。この治療は、矯正歯科医と口腔外科医が密に連携を取りながら進めることが非常に重要です。
外科手術を併用した矯正治療は、骨格レベルでの根本的な改善が期待でき、顔貌の審美的変化も大きいという特徴があります。しかし、治療期間が長くなることや、手術に伴うリスクがあるため、治療を受けるかどうかは慎重に検討し、担当医から十分な説明を受けることが大切ですことです。
頭痛などの不調を伴う場合:顎の位置を安定させてから治す方法
噛み合わせのズレが原因で、すでに頭痛や顎の痛み、首や肩のこりといった「不定愁訴」に悩まされている方もいらっしゃるかもしれません。このような場合、ただ歯を動かすだけでは症状が改善しないだけでなく、かえって悪化させてしまう可能性もあります。そのため、まずは顎にとって最も負担が少なく、機能的に安定する位置を見つけ出すことが治療の最優先事項となります。
具体的には、「オーソティック」と呼ばれる特殊なマウスピースを装着する「一次治療」から始めることが一般的です。このオーソティックは、患者さんの顎関節や咀嚼筋の状態に合わせて精密に作られ、正しい顎の位置を誘導し、安定させることで、症状の改善を目指します。この際、筋電計や顎運動記録装置(K7)といった精密機器を用いて、客観的なデータに基づいて顎の動きや筋肉の状態を評価し、最適な顎の位置を特定していきます。
一次治療によって不定愁訴が改善し、顎が安定したことを確認できた後で、その理想的な顎の位置を長期間維持するために「二次治療」へと移行します。二次治療では、矯正治療によって歯並びや噛み合わせを根本的に修正したり、必要に応じて補綴治療(被せ物や詰め物)によって歯の形や高さを調整したりします。このように、二段階の治療プロセスを経ることで、症状の改善と安定した噛み合わせの両方を目指すことができます。この治療法は、全身の不調を伴う噛み合わせのズレに対して、非常に効果的なアプローチと言えるでしょう。
噛み合わせ治療に使われる主な矯正装置の種類と特徴
噛み合わせの治療では、患者さんの状態や希望に合わせてさまざまな種類の矯正装置が用いられます。それぞれの装置にはメリットとデメリットがあり、どの方法が最適かは、専門家である歯科医師との相談を通じて決定されます。このセクションでは、代表的な矯正装置であるワイヤー矯正とマウスピース矯正について、その特徴や治療のポイントを詳しくご紹介します。
ワイヤー矯正(表側矯正・裏側矯正)
ワイヤー矯正は、長い歴史と豊富な実績を持つ、もっとも一般的な矯正治療法の一つです。歯の表面に「ブラケット」と呼ばれる小さな装置を取り付け、そこに金属のワイヤーを通して少しずつ歯に力をかけることで、歯を動かしていきます。この方法は、幅広い症例に対応でき、治療効果も非常に高いとされています。
ワイヤー矯正には、大きく分けて二つの種類があります。一つは「表側矯正」で、ブラケットとワイヤーを歯の表側に取り付ける方法です。費用が比較的抑えられ、多くの矯正歯科医が習熟しているため、選択肢として広く利用されています。しかし、装置が目立つため、見た目を気にされる方もいらっしゃいます。
もう一つは「裏側矯正(リンガル矯正)」です。これはブラケットとワイヤーを歯の裏側に取り付けるため、外からは矯正装置が見えないという大きなメリットがあります。接客業の方や、人前で話す機会が多い方など、審美性を重視する方には特におすすめです。ただし、オーダーメイドで作製する必要があるため費用は高額になりがちで、舌が触れることで一時的に発音に影響が出たり、慣れるまでに時間がかかったりする場合があります。
マウスピース矯正
マウスピース矯正は、近年注目を集めている新しい矯正治療法です。透明なプラスチック製のマウスピースを段階的に交換していくことで、歯を少しずつ動かしていきます。この治療法は、特に審美性と快適さを求める方に選ばれています。
マウスピース矯正の最大のメリットは、まず「目立ちにくい」という点です。透明な素材でできているため、装着していてもほとんど気づかれることがありません。また、「取り外しが可能」であるため、食事や歯磨きの際にはマウスピースを外すことができ、衛生的です。これにより、口腔内を清潔に保ちやすく、虫歯や歯周病のリスクを軽減できると考えられます。
しかし、マウスピース矯正には注意点もあります。一つは、ワイヤー矯正に比べて適応できる症例に限りがあることです。特に複雑な歯の動きが必要なケースや、顎の骨格に大きな問題がある場合には、ワイヤー矯正が適していることもあります。もう一つは、患者さんご自身が「装着時間を守る」という自己管理が不可欠であることです。マウスピースは1日20時間以上の装着が推奨されており、これを守らないと計画通りに歯が動かず、治療期間が延びてしまう可能性があります。
自分に合った治療法の選び方
ワイヤー矯正とマウスピース矯正、どちらの治療法を選ぶべきか迷う方も少なくありません。最も重要なのは、ご自身の判断だけで決めるのではなく、専門知識を持った矯正歯科医による精密な診断とアドバイスを受けることです。ご自身の歯並びの状態や顎の骨格は一人ひとり異なるため、最適な治療法も異なります。
治療法を選ぶ際には、いくつかの要素を考慮することが大切です。まず「噛み合わせのズレの重症度」です。軽度な歯並びの乱れであればマウスピース矯正で対応できるケースも多いですが、重度な骨格の問題を伴う場合はワイヤー矯正や外科手術の併用が必要になることもあります。次に「審美性へのこだわり」も重要なポイントです。装置が目立たないことを最優先するなら裏側矯正やマウスピース矯正が適しているでしょう。
さらに、「ライフスタイル」も考慮に入れるべきです。例えば、仕事柄、人前で話す機会が多い方や、スポーツをする方、特定の楽器を演奏する方などは、装置の見た目や装着感が生活に与える影響を考える必要があります。また「予算」も無視できない要素です。一般的にワイヤー矯正(表側)は比較的費用が抑えられますが、裏側矯正やマウスピース矯正は高額になる傾向があります。これらの要素を踏まえ、医師と十分に話し合い、ご自身が納得できる最適な治療法を選ぶことが、治療を成功させる鍵となります。
治療開始から完了までの流れと期間・費用の目安
噛み合わせの治療を検討されている方にとって、治療がどのような流れで進むのか、どのくらいの期間や費用がかかるのかは、とても気になる点ではないでしょうか。治療は決して短期間で終わるものではないため、事前に全体像を把握しておくことは、安心して治療を進める上で非常に重要です。
このセクションでは、実際に治療を開始してから完了するまでの具体的なステップ、治療期間の目安、そして費用の内訳について詳しくご説明します。これらの情報を参考に、ご自身の治療計画を立てる際のお役立てください。
初診相談から保定期間までのステップ
噛み合わせの治療は、いくつかの重要なステップを経て進められます。まず、治療の第一歩は「①初診相談」です。ここでは、現在抱えている悩みや治療に対する希望を歯科医師に伝えます。歯科医師は、その内容をもとに、治療の可能性や大まかな方向性について説明してくれます。
次に、「②精密検査」を行います。これは、レントゲン撮影(セファログラムなどの特殊なX線写真を含む)、歯型の採取、口腔内や顔貌の写真撮影など、多角的なデータ収集を行う重要なステップです。これらの検査結果をもとに、歯科医師は現在の噛み合わせの問題点を詳細に分析し、具体的な治療計画を立てます。そして「③診断・治療計画の説明」において、現在の状態、治療の具体的なゴール、使用する装置の種類、治療期間、費用、そして起こりうるリスクや副作用について、患者さんが納得できるまで丁寧に説明します。ここで治療計画に同意することで、次のステップへ進みます。
計画が決定したら、「④矯正装置の装着と治療開始」です。ワイヤー矯正の場合はブラケットとワイヤーを装着し、マウスピース矯正の場合は最初のマウスピースを受け取ります。治療期間中は「⑤定期的な調整」が必要です。ワイヤー矯正では数週間に一度のペースでワイヤーの調整や交換を行い、マウスピース矯正では新しいマウスピースに交換していきます。この期間に歯が計画通りに動いているかを確認し、必要に応じて微調整を行います。そして、目標とする噛み合わせに到達すれば、「⑥装置の撤去」となります。長かった矯正装置の生活もここで一旦終了です。
しかし、治療はこれで終わりではありません。矯正治療で動かした歯は、元の位置に戻ろうとする「後戻り」を起こしやすい性質があります。これを防ぐために、装置撤去後は「⑦保定期間」に入ります。この期間には「保定装置(リテーナー)」と呼ばれる装置を装着し、新しい歯並びを安定させます。リテーナーの装着は、治療効果を長く維持するために非常に重要で、歯科医師の指示に従って一定期間装着し続ける必要があります。
治療にかかる期間の目安
矯正治療にかかる期間は、お口の状態や選ぶ治療法によって大きく異なります。一般的な歯列矯正の場合、数ヶ月から数年単位、具体的には1年半から3年程度の期間を要することが多いです。軽度の歯並びの乱れであれば比較的短期間で終わることもありますが、複雑な症例ほど治療期間は長くなる傾向にあります。
特に、顎の骨格的な問題があり、外科手術を併用する治療が必要な「顎変形症」の場合、治療期間はさらに長くなります。手術前の術前矯正、外科手術、そして手術後の術後矯正を含めると、合計で3年から5年程度の期間がかかることもあります。また、歯の動きやすさには個人差があり、年齢や健康状態なども治療期間に影響するため、あくまで目安としてお考えください。
正確な治療期間については、精密検査後に歯科医師から提示される治療計画の説明をしっかりと聞くことが大切です。
費用の目安と保険が適用されるケース(顎変形症など)
矯正治療は、多くの場合、健康保険が適用されない自由診療となり、費用が高額になる傾向があります。治療費は、選択する治療法(ワイヤー矯正かマウスピース矯正か、表側か裏側かなど)、症例の難易度、治療期間、そしてクリニックによって大きく異なります。
しかし、一部の特定の症例では、公的医療保険が適用される場合があります。特に重要なのは、「顎変形症」と診断され、外科手術を伴う矯正治療が必要なケースです。顎変形症と診断された場合、その治療に関連する矯正治療も保険適用の対象となります。これは、単なる見た目の改善だけでなく、咀嚼機能の改善や顎関節への負担軽減といった機能的な側面が重視されるためです。
保険適用となるためには、いくつかの条件があります。まず、顎変形症の診断が確定していること。次に、厚生労働大臣が定める施設基準を満たした医療機関(保険医療機関)で治療を受けること。そして、矯正歯科と口腔外科が連携して治療を進める必要があります。もしご自身の症状が顎変形症に該当する可能性があると感じる場合は、必ず専門の歯科医師に相談し、保険適用の可否について確認することが大切です。
費用については、事前にカウンセリングや精密検査を通じて、総額や支払い方法について詳しく説明を受けるようにしましょう。複数のクリニックで相談し、見積もりを比較検討することもおすすめです。
後悔しないために知っておきたい矯正歯科の選び方
噛み合わせの治療は、見た目の改善だけでなく、全身の健康にも深く関わる大切な医療行為です。そのため、費用や治療期間だけでなく、信頼できる矯正歯科医院と医師を選ぶことが、治療を成功させ、後悔しない結果を得るために最も重要となります。このセクションでは、ご自身に合った矯正歯科を見つけるための具体的なチェックポイントを3つご紹介します。
噛み合わせ治療に関する専門知識と実績があるか
矯正歯科を選ぶ際、まず確認したいのは、その医師が噛み合わせ治療に関して深い専門知識と豊富な臨床経験を持っているかという点です。単に歯をきれいに並べるだけでなく、顎関節の健康や顔全体のバランス、咀嚼機能まで考慮した、機能的に安定した噛み合わせを構築するスキルが求められます。
良い矯正歯科医を見極める一つの目安として、「日本矯正歯科学会が認定する認定医や専門医」であるかどうかを確認することをおすすめします。これらの資格は、専門的な知識と技術を有していることの証明となります。また、クリニックのウェブサイトなどで、ご自身の症例と似た患者さんの治療前後の写真や説明が豊富に公開されているかも参考にすると良いでしょう。
精密な検査と丁寧な説明を受けられるか
治療開始前の検査と、その検査結果に基づいた説明の質は、クリニックの信頼性を測る重要な指標です。レントゲン撮影(特にセファログラムと呼ばれる頭部X線規格写真)、歯型の採取、口腔内写真や顔貌写真の撮影など、詳細な精密検査をしっかりと行い、客観的なデータに基づいて診断してくれるかがポイントです。
その上で、医師が現在の噛み合わせの問題点、治療によってどのような変化が期待できるのか、具体的な治療計画、予想される治療期間や費用、そして治療に伴うリスクや副作用についても、専門用語ばかりを使わず、患者さんが理解し納得できるまで時間をかけて丁寧に説明してくれるかどうかを見極めましょう。質問に対して誠実に答えてくれる姿勢も大切です。
複数の選択肢を提示し、希望に寄り添ってくれるか
患者さん一人ひとりの噛み合わせの状態や、治療に対する希望は異なります。そのため、最も優れた治療法が一つとは限らない場合もあります。良い矯正歯科医は、ワイヤー矯正とマウスピース矯正、抜歯治療と非抜歯治療など、メリットとデメリットを含めて複数の治療選択肢を提示してくれるでしょう。
患者さんの見た目に関するこだわり、費用面での希望、ライフスタイル(食事や職業など)といった価値観を尊重し、一方的に特定の治療法を押し付けるのではなく、共に最良の治療計画を考えてくれるパートナーシップを築ける医師を選ぶことが重要です。ご自身の希望を伝えやすい雰囲気であるかどうかも、クリニック選びの大切な要素になります。
まとめ:正しい治療で見た目と機能性を両立させよう
これまで見てきたように、噛み合わせのズレは単に歯並びが悪いという見た目の問題だけでなく、頭痛や肩こり、顎の痛みといった体の不調、さらには睡眠の質にまで影響を及ぼす可能性があります。しかし、適切な矯正治療を受けることで、これらの悩みから解放され、健康的で美しい口元を取り戻すことが可能です。
噛み合わせの治療では、歯並びを整えるだけでなく、顎の骨格や筋肉、そして全身のバランスを考慮したアプローチが求められます。ワイヤー矯正やマウスピース矯正、場合によっては外科手術の併用など、様々な治療法があり、それぞれの症状やライフスタイルに合わせた最適な選択肢が用意されています。
もし、ご自身の噛み合わせに不安を感じたり、原因不明の体の不調に悩んでいるのであれば、まずは矯正歯科医に相談し、専門的な診断を受けることを強くおすすめします。正確な診断と丁寧な治療計画の説明を通して、コンプレックスを解消し、見た目と機能性を両立させた、より快適で自信に満ちた生活を手に入れてください。
少しでも参考になれば幸いです。
自身の歯についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
監修者
東京歯科大学卒業後、千代田区の帝国ホテルインペリアルタワー内名執歯科・新有楽町ビル歯科に入職。
その後、小野瀬歯科医院を引き継ぎ、新宿オークタワー歯科クリニック開院し現在に至ります。
また、毎月医療情報を提供する歯科新聞を発行しています。
【所属】
・日本放射線学会 歯科エックス線優良医
・JAID 常務理事
・P.G.Iクラブ会員
・日本歯科放射線学会 歯科エックス線優良医
・日本口腔インプラント学会 会員
・日本歯周病学会 会員
・ICOI(国際インプラント学会)アジアエリア役員 認定医、指導医(ディプロマ)
・インディアナ大学 客員教授
・IMS社VividWhiteホワイトニング 認定医
・日本大学大学院歯学研究科口腔生理学 在籍
【略歴】
・東京歯科大学 卒業
・帝国ホテルインペリアルタワー内名執歯科
・新有楽町ビル歯科
・小野瀬歯科医院 継承
・新宿オークタワー歯科クリニック 開院
新宿区西新宿駅徒歩4分の歯医者・歯科
『新宿オークタワー歯科クリニック』
住所:東京都新宿区西新宿6丁目8−1 新宿オークタワーA 203
TEL:03-6279-0018