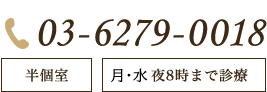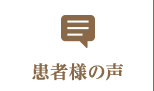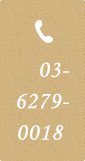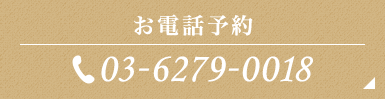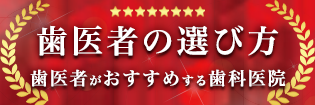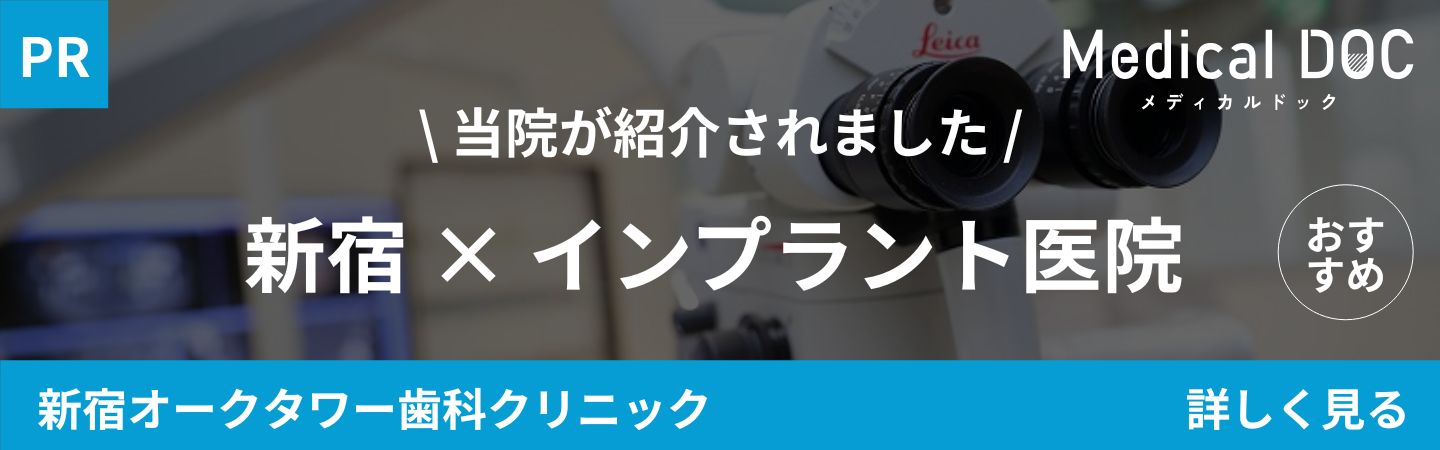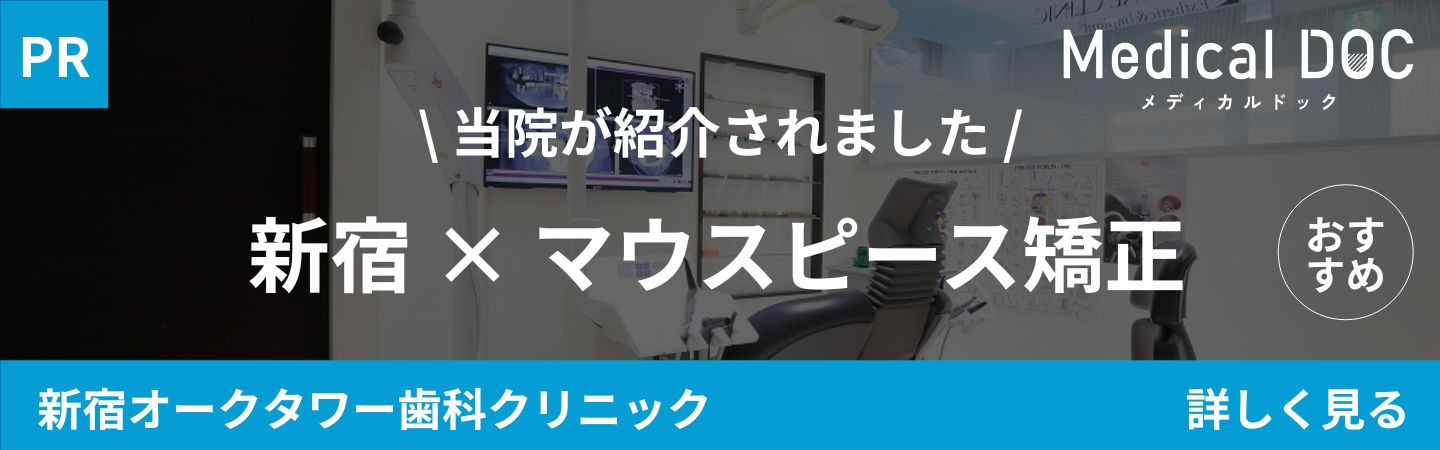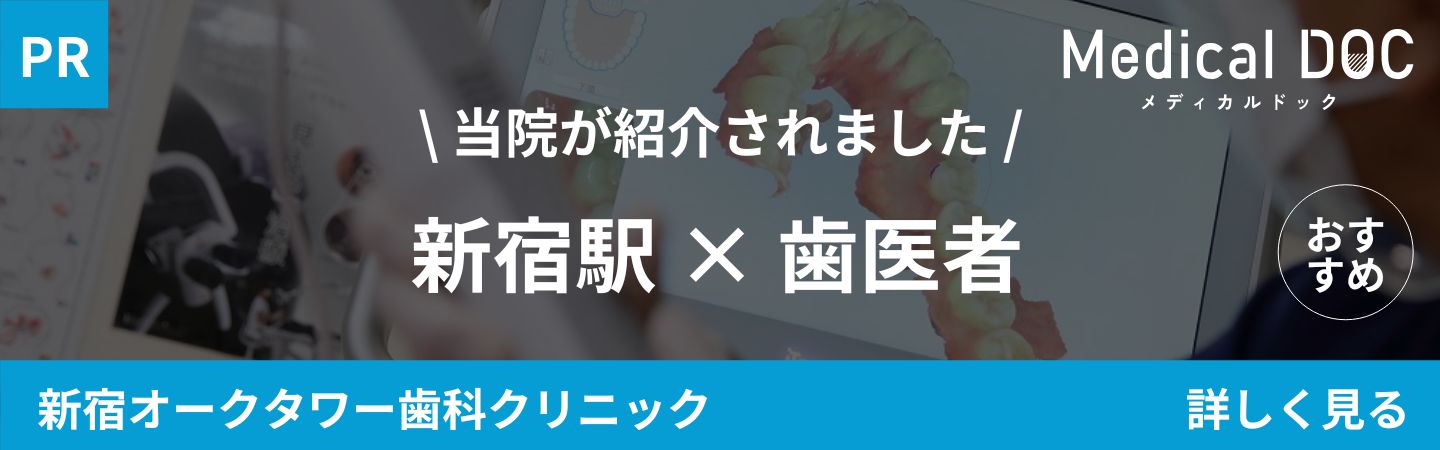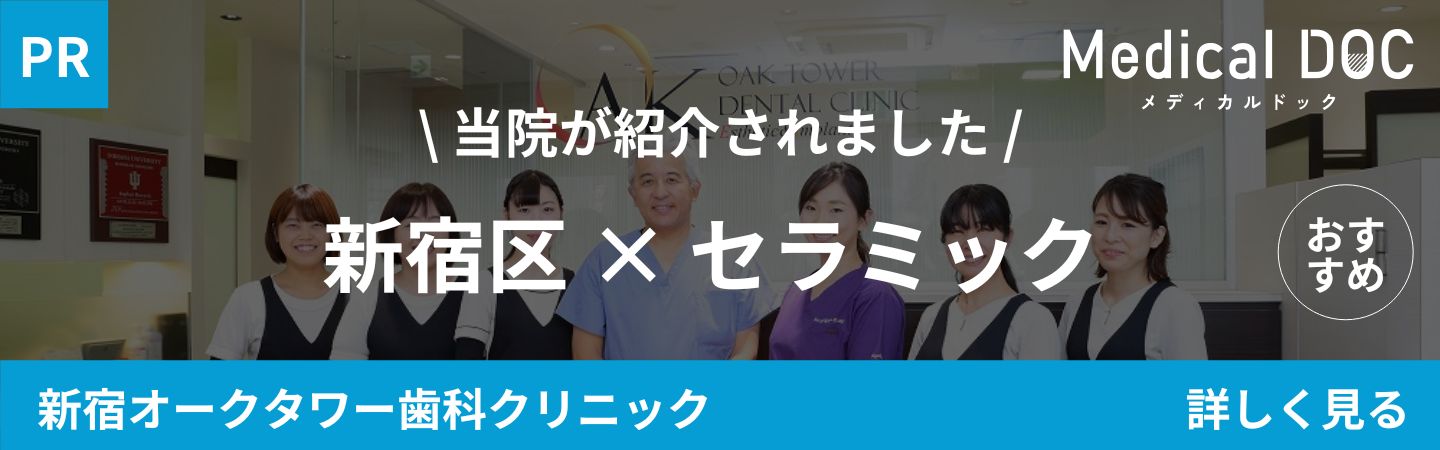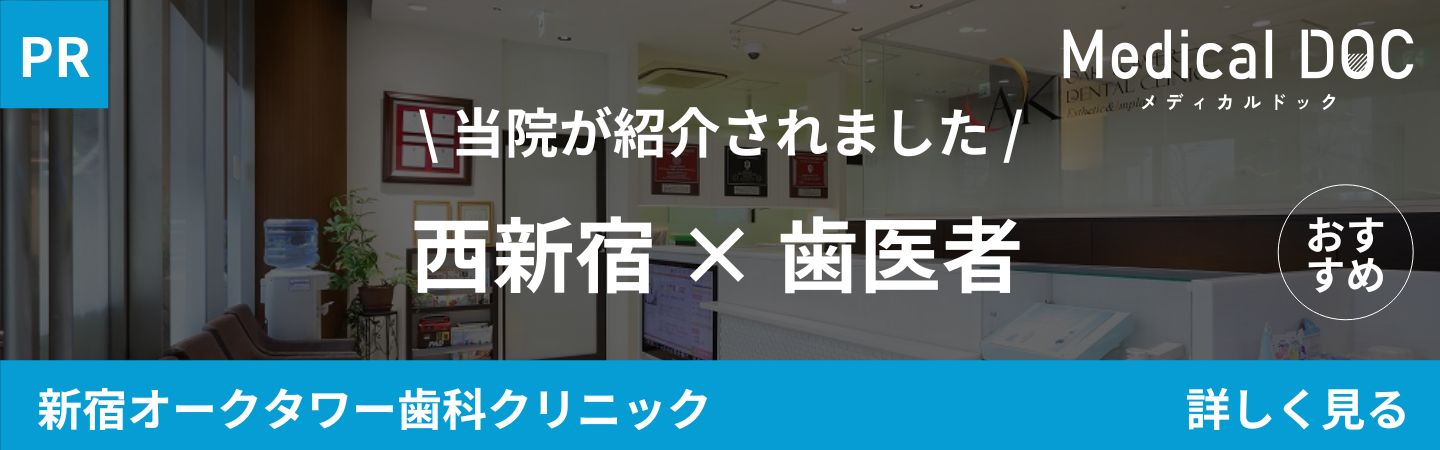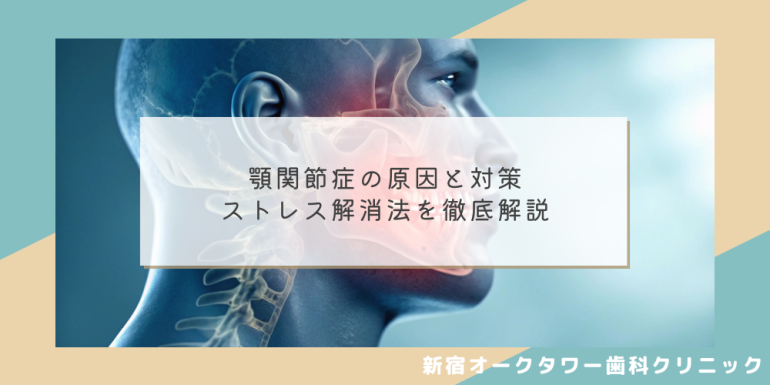
新宿オークタワー歯科クリニックです。
顎が痛む、口を開けるとカクカク音が鳴る、大きく口を開けられないといった顎の不調は、日常生活に大きな影響を及ぼし、多くの方が悩まれている身近な問題です。これらの症状は「顎関節症」と呼ばれる病気のサインかもしれません。顎関節症は、単なる痛みだけでなく、食事や会話のしづらさ、さらには頭痛や肩こりにもつながることがあります。この記事では、顎関節症の基本的な知識から、ご自身でできるセルフチェック、発症の主な原因、そして具体的な対策方法(セルフケアと専門的な治療)までを網羅的に解説いたします。
もしかして顎関節症?気になる顎の症状をセルフチェック
顎の痛みや違和感、カクカクという音に悩まされていても、「これって顎関節症なのかな?」「どこか受診した方がいいのかな?」と不安に感じる方は少なくありません。ご自身の状態が顎関節症によるものなのか、それとも一時的なものなのか、判断に迷うこともあるでしょう。このセクションでは、顎関節症の基本的な症状やタイプをご紹介します。ご自身の顎の不調を客観的に見つめ直し、適切な対処法を見つけるための一歩として、ぜひセルフチェックにお役立てください。
顎関節症とは?基本的な知識と症状
顎関節症は、顎の関節やその周りの筋肉に痛みが生じたり、口を開け閉めする際に音が鳴ったり、大きく口を開けられなくなったりする病気の総称です。顎の関節は、下あごの骨である下顎骨の先端(下顎頭)と、頭の骨(側頭骨)のくぼみ(側頭窩)が合わさる部分にあり、その間にはクッションのような役割を果たす「関節円板(ディスク)」が存在します。顎関節症は、この関節や円板、または周りの筋肉に何らかの問題が生じることで発症します。
顎関節症の主な症状は、「顎の痛み」「関節音」「開口障害」の3つです。顎の痛みは、口を開け閉めする時や食事の際に生じることが多く、顎だけでなく、こめかみや頬、首筋にまで広がることもあります。関節音は、「カクカク」「ミシミシ」「ジャリジャリ」といった音が口を開け閉めする際に聞こえるもので、必ずしも痛みを伴うわけではありません。開口障害は、口を大きく開けられない、または開けた口を閉じにくいといった症状で、食事や会話に支障をきたすことがあります。
顎関節症は、特に20代から50代の女性に多く見られる傾向があります。もし、これらの症状に心当たりがある場合は、顎関節症の可能性を考え、ご自身の生活習慣や癖を見直すことが大切です。
顎関節症の主な4つのタイプ
顎関節症と一言でいっても、その原因や症状によって主に4つのタイプに分類されます。ご自身の顎の不調がどのタイプに近いのかを知ることで、より適切な対処法を見つける手助けになります。
まず、I型は「咀嚼筋痛障害」と呼ばれ、主に顎を動かす筋肉(咀嚼筋)の痛みやこわばりが原因です。ストレスによる食いしばりや歯ぎしりなどで筋肉が過度に緊張することで生じます。次に、II型は「顎関節痛障害」で、顎関節そのものに炎症が起きて痛むタイプです。関節を覆う膜や靭帯が傷つくことで、口を開け閉めする際に強い痛みを感じることがあります。
III型は「顎関節円板障害」で、顎関節の中にあるクッション材の関節円板が正しい位置からずれてしまうことで起こります。「カクカク」といったクリック音や、口の開け閉めがスムーズにいかない開口障害が特徴です。最後に、IV型は「変形性顎関節症」と呼ばれ、顎関節の骨自体が変形してしまうタイプです。関節円板のずれが長期化したり、関節への負担が大きかったりすることで、骨がすり減ったり形が変わったりして、「ジャリジャリ」といった不快な音がしたり、慢性的な痛みが続くことがあります。
顎関節症の主な原因|ストレスや何気ない生活習慣が関係
顎関節症は、単一の原因で発症するわけではありません。ストレスや生活習慣、噛み合わせといった複数の要因が複雑に絡み合い、顎の関節やその周囲の筋肉に負担をかけることで症状が現れます。これから、精神的なプレッシャー、無意識の癖、歯並びの問題、そして日々の姿勢などが、どのように顎に影響を与え、顎関節症を引き起こすのかを詳しく見ていきましょう。
精神的なストレスと食いしばり・歯ぎしり
顎関節症の大きな原因の一つとして、精神的なストレスが挙げられます。私たちの体はストレスを感じると、無意識のうちに歯を強く食いしばったり、寝ている間に歯ぎしりをしたりすることが増える傾向にあります。これは、ストレスに対する体の防御反応の一種とも言えますが、顎にとっては大きな負担となります。
通常、食事中など以外は上下の歯は触れ合っていない状態が理想的です。しかし、ストレスによって食いしばりや歯ぎしりが頻繁に起こると、顎関節やその周辺の咀嚼筋に過度な力が長時間かかり続けることになります。この持続的な負荷が、顎の痛みや動きの制限といった顎関節症の症状を引き起こしたり、悪化させたりする主要な要因となるのです。特に夜間の歯ぎしりは、意識できないために対処が難しく、顎へのダメージも大きくなりがちです。
TCH(歯列接触癖)などの無意識の癖
TCH(Tooth Contacting Habit:歯列接触癖)とは、食事や会話の時以外にも、上下の歯が常に接触している癖のことを指します。本来、リラックスしている状態では、上下の歯の間には数ミリの隙間が空いているのが正常です。しかし、集中している時や緊張している時など、無意識のうちに歯を軽く接触させている方が多くいらっしゃいます。
このTCHは、食いしばりほど強い力ではありませんが、長時間にわたって顎の筋肉を緊張させ、疲労を蓄積させてしまいます。特にパソコン作業やスマートフォンの操作中に無意識に歯を接触させ続けることで、顎関節や咀嚼筋にじわじわと負担がかかり、結果として顎関節症の症状を引き起こす大きな原因となることがあります。この癖に気づき、意識的に歯を離す習慣をつけることが大切です。
噛み合わせの不調和や歯並びの問題
噛み合わせの不調和や歯並びの問題も、顎関節症の一因となる可能性があります。例えば、虫歯治療で入れた詰め物や被せ物の高さが合っていなかったり、特定の歯が強く当たりすぎたりすると、顎が不自然な位置で動かざるを得なくなり、顎関節に偏った負担がかかることがあります。
また、重度の出っ歯や受け口、あるいは不揃いな歯並びも、顎関節への負担を増やす要因となることがあります。しかし、噛み合わせの不調和だけが顎関節症の単独の原因となることは少なく、ストレスや無意識の癖といった他の要因と複合的に関係している場合がほとんどです。そのため、噛み合わせの治療を行う際には、全身的な要因も考慮に入れることが重要になります。
不良姿勢(猫背・頬杖)や外傷などその他の要因
顎関節症の原因は、ここまで解説したものの他にも、日々の何気ない習慣の中に潜んでいます。例えば、長時間のデスクワークで背中が丸まる猫背や、テレビを見ながら無意識にしてしまう頬杖といった「不良姿勢」は、頭の位置を前方にずらし、首や肩、そして顎周りの筋肉のバランスを崩して大きな負担をかけてしまいます。
さらに、スポーツ中の衝突や交通事故による「外傷」も、顎関節に直接的なダメージを与え、顎関節症を引き起こすことがあります。また、極端に硬い食べ物を頻繁に食べる習慣、管楽器の演奏など、顎に繰り返し負担をかける特定の活動も、リスクを高める要因となり得ます。このように、私たちの日常生活には、顎関節症に繋がる多様な原因が隠されているのです。
【セルフケア編】今日から始められる顎関節症の対策
顎関節症のつらい症状を和らげ、さらには予防していくためには、日々の生活の中で実践できるセルフケアが非常に重要です。専門的な治療が必要な場合もありますが、多くの場合、セルフケアを継続することで症状が大きく改善することが期待できます。これからご紹介する生活習慣の見直し、顎周りのマッサージ、そして心身をリラックスさせるストレス解消法は、どれもご自宅で気軽に始められるものばかりです。ぜひ今日から試していただき、顎の不調の改善につなげてください。
顎の負担を減らす生活習慣の見直し
日々の何気ない行動が、知らず知らずのうちに顎関節に大きな負担をかけていることがあります。食事の仕方や口の開け方、座っているときの姿勢など、毎日の習慣を少し見直すだけで、顎への負担を軽減し、顎関節症の症状が大きく改善する可能性があります。ご自身の生活習慣を振り返りながら、顎に優しい習慣を身につけていきましょう。
硬い食べ物を避け、食事を工夫する
顎関節症で痛みがあるときは、一時的に硬い食べ物を避けることが大切です。フランスパンやスルメ、硬い肉、せんべいなどは、噛むときに強い力が必要となり、顎関節に大きな負担をかけてしまいます。これらの食べ物はできるだけ控えるようにしましょう。
代わりに、おかゆ、スープ、豆腐、ヨーグルト、プリン、うどん、煮魚、蒸し野菜など、柔らかく噛みやすい食事を心がけてください。食材を細かく切ったり、よく煮込んだりする調理の工夫も有効です。顎を休ませる期間を設けることで、炎症が鎮まり、痛みの軽減につながります。
大きく口を開けすぎないように意識する
あくびをするときや食事の際、また会話をしているときなど、必要以上に大きく口を開けすぎないように意識することも、顎関節症の症状緩和に役立ちます。大きく口を開けることで、顎関節やその周辺の靭帯に過度な負担がかかり、痛みや関節音を誘発することがあるためです。
特に大きなあくびが出る際には、下顎に軽く手を添えて、口が開きすぎるのを物理的に防ぐようにしましょう。食べ物を口に入れる際も、一口サイズに切るなどして、無理なく口に入れられるように工夫すると良いでしょう。これらの小さな意識が、顎関節への負担を軽減し、症状の悪化を防ぐことにつながります。
姿勢を正し、頬杖をやめる
猫背などの不良姿勢は、頭部の位置が前にずれ、首や肩、そして顎周りの筋肉に余計な緊張と負担をかける原因となります。特にデスクワークをする際は、モニターを目線の高さに調整し、椅子には深く腰掛け、背筋を伸ばすように意識しましょう。正しい姿勢を保つことで、顎関節にかかる負担を軽減できます。
また、頬杖をつく癖も顎関節症の大きな原因の一つです。片側の顎に長時間不自然な圧力がかかり、顎関節のバランスを崩してしまう可能性があります。テレビを見ているときや考え事をしているときなど、無意識に頬杖をついていないか意識し、できるだけ避けるように心がけてください。姿勢を改善することは、顎だけでなく、首や肩こりの軽減にもつながります。
顎周りの緊張をほぐすマッサージ・ストレッチ
顎関節症では、顎周りの筋肉、特に咬筋(こうきん)や側頭筋(そくとうきん)が緊張し、硬くなっていることが多いです。これらの筋肉を優しくほぐすマッサージやストレッチは、血行を促進し、痛みを和らげる効果が期待できます。ご自宅で安全に実践できる方法をいくつかご紹介します。
まず、咬筋のマッサージです。人差し指と中指の腹を使い、頬骨の下あたり、奥歯を噛みしめたときに硬くなる部分(咬筋)に当てます。息を吐きながら、優しく円を描くようにゆっくりとマッサージしてください。次に、側頭筋のマッサージです。こめかみから耳の上のあたり(側頭筋)に指の腹を当て、こちらも優しく円を描くようにほぐしていきます。これらのマッサージは、痛みを感じない範囲で、入浴後など体が温まっている時に行うとより効果的です。無理な力を加えずに、リラックスして行うことが大切です。
心身をリラックスさせるストレス解消法
顎関節症の主な原因の一つに、精神的なストレスが挙げられます。ストレスは無意識の食いしばりや歯ぎしりを引き起こし、顎関節に過度な負担をかけるため、心身をリラックスさせることは顎関節症の根本的な対策となります。これからご紹介する深呼吸や軽い運動、そして趣味の時間は、ストレスを軽減し、顎周りの緊張を和らげるのに役立ちます。
深呼吸や軽い運動を取り入れる
ストレスによる体の緊張を和らげるためには、深呼吸が非常に効果的です。腹式呼吸を意識し、鼻から4秒かけてゆっくりと息を吸い込み、口から8秒かけてさらにゆっくりと息を吐き出すというサイクルを繰り返してみてください。この深呼吸を数回繰り返すだけで、自律神経が整い、心身がリラックスするのを感じられるでしょう。いつでもどこでも手軽に実践できるため、仕事の合間や就寝前などに取り入れてみてください。
また、ウォーキング、ヨガ、ストレッチなどの軽い有酸素運動もおすすめです。適度な運動は、全身の血行を促進し、筋肉の緊張をほぐすだけでなく、ストレスホルモンの分泌を抑える効果も期待できます。毎日少しでも体を動かす習慣を取り入れることで、ストレスが軽減され、顎関節への負担も自然と和らぐでしょう。
趣味や休息の時間を確保する
顎関節症の改善には、物理的なアプローチだけでなく、精神的な休息も不可欠です。仕事や家事、人間関係などで日々感じるストレスから意識的に離れる時間を作りましょう。読書、音楽鑑賞、映画鑑賞、散歩、ガーデニングなど、ご自身が心から楽しめる趣味に没頭する時間を持つことは、心の安定につながり、顎の緊張緩和にも良い影響を与えます。
また、十分な睡眠時間を確保することも、心身の回復とストレス耐性の向上には欠かせません。質の良い睡眠は、日中のストレスを解消し、体の修復を促します。決まった時間に寝起きする、寝る前にカフェインを控える、寝室の環境を整えるなど、生活リズムを整える工夫もしてみてください。心と体がリラックスすることで、顎関節症の症状改善につながります。
【専門治療編】症状が改善しない場合に歯科・口腔外科で行う治療法
セルフケアを続けても顎の痛みや不快感が改善しない場合や、日常生活に支障が出るほど症状が強くなってきた場合は、専門的な治療が必要になります。歯科医院や口腔外科では、患者さんの症状や顎の状態に合わせて、さまざまな治療法が提供されています。手術が必要になるケースは非常に稀で、多くの場合、セルフケア、理学療法、内服治療、スプリント治療といった方法で症状の改善を目指しますので、過度な心配はいりません。ここでは、専門家による代表的な治療法についてご紹介します。
スプリント(マウスピース)療法
スプリント療法は、顎関節症の治療において非常に一般的で効果的な方法の一つです。患者さん一人ひとりの歯型に合わせてオーダーメイドで作製される専用のマウスピース(スプリント)を、主に就寝中に装着していただきます。
このスプリントは、歯ぎしりや食いしばりによる過度な力を分散させ、歯や顎関節への負担を軽減するクッションのような役割を果たします。また、顎関節が最も安定する位置に導くことで、顎関節周辺の筋肉の緊張を和らげ、顎の痛みやクリック音といった症状の改善につながります。就寝中の無意識の食いしばりや歯ぎしりが原因で顎関節症になっている方にとって、スプリント療法は特に有効な治療法と言えるでしょう。
薬物療法(鎮痛薬・筋弛緩薬)
顎関節症による痛みが強い場合や、炎症が起きている場合には、薬を用いた治療が行われることがあります。一般的には、炎症を抑えながら痛みを和らげる非ステロイド系鎮痛薬(NSAIDs)が処方されます。これにより、顎の不快感を軽減し、日常生活を送りやすくする効果が期待できます。
また、顎関節症の原因が顎周辺の筋肉の過度な緊張やこわばりにある場合は、筋肉の働きを緩める筋弛緩薬が用いられることもあります。これらの薬は、あくまで症状を一時的に緩和するための対症療法であり、顎関節症の根本的な原因を解決するものではありません。そのため、薬物療法は、スプリント療法や理学療法といった他の治療法と並行して行われることが多く、専門医の指示に従って適切に服用することが大切ですんです。
理学療法(マッサージ・低周波治療など)
歯科医院や専門機関で行われる理学療法も、顎関節症の症状緩和に有効な治療法です。これには、専門家による顎周りの筋肉のマッサージ、顎の動きをスムーズにするための開口訓練、そして血行を促進して筋肉の緊張を和らげるための温熱療法や低周波治療などが含まれます。
セルフケアで行うマッサージと異なり、理学療法では専門知識を持ったスタッフが、患者さん一人ひとりの顎の状態や痛みの原因に合わせて、適切な方法でアプローチします。これにより、硬くなった筋肉を効果的にほぐし、顎関節の動きを改善することで、より高い症状改善効果が期待できます。必要に応じて、ご自宅で行えるストレッチやマッサージの方法についても、専門家から指導を受けられます。
外科的治療
顎関節症の治療において外科的治療が選択されるケースは、非常に稀であることをまずお伝えしておきます。顎関節症のほとんどは、スプリント療法や薬物療法、理学療法といった保存的な治療で改善が見込まれるため、手術が行われることは滅多にありません。この点について、過度な不安を感じる必要はありません。
外科的治療が検討されるのは、他のあらゆる保存療法を試しても全く効果が見られず、かつ関節の構造に明確な異常があり、日常生活に著しい支障をきたしている重度の患者さんに限られます。具体的な手術方法としては、関節内の癒着を剥がす関節腔内洗浄療法や、関節鏡を使った関節鏡視下手術などがありますが、これらは非常に専門性の高い治療であり、専門医によって慎重に判断されます。
顎関節症に関するよくある質問
ここでは、顎関節症に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめます。顎関節症に関する疑問を解消し、適切な対応をとるための参考にしてください。
顎関節症は何科を受診すればいい?
顎関節症の症状を感じた際に「何科を受診すればよいのか」と迷われる方は少なくありません。まず第一に受診を検討していただきたいのは、歯科または口腔外科です。これらの診療科は、顎関節症の診断と治療を専門としており、レントゲンやMRIなどの専門的な検査を通じて、正確な診断を下すことができます。
一般的な歯科医院でも顎関節症の相談は可能ですが、症状が重度の場合や診断が難しい複雑なケースでは、大学病院などの専門的な口腔外科を紹介されることもあります。ご自身の症状の程度に応じて、適切な医療機関を選ぶことが重要です。
顎関節症は自然に治る?放置するリスクは?
顎関節症の症状は、軽度であれば生活習慣の見直しやセルフケアによって自然に軽快することがあります。特に、一時的なストレスや疲労が原因で起こる顎の不調であれば、原因が取り除かれることで症状が落ち着くことも少なくありません。顎関節症の症状は多くの場合、2週間から3か月程度で改善することが知られています。
しかし、症状を放置してしまうことには大きなリスクが伴います。痛みが慢性化して日常生活に支障をきたしたり、口がほとんど開かなくなって食事や会話が困難になったりする可能性があります。また、顎関節の変形が進んでしまい、治療がより困難になるケースも存在します。症状が長引く場合や悪化する兆候が見られる場合は、自己判断せずに早めに専門医に相談することが、症状の悪化を防ぎ、早期改善につながります。
治療にかかる期間や費用は?
顎関節症の治療にかかる期間や費用は、症状の重さや選択される治療法によって大きく異なります。セルフケアや薬物療法のみで改善が見られる場合は数週間から数ヶ月で症状が落ち着くこともありますが、スプリント療法(マウスピース療法)を用いる場合は、効果を実感するまでに数ヶ月以上かかることもあります。治療期間は患者さんの症状や生活習慣によって個々に異なるため、担当医とよく相談し、治療計画を確認することが大切です。
費用についても、保険適用の治療と適用外の治療があります。診察料、レントゲン検査、一部の薬などは健康保険が適用されます。一方、顎関節症治療で広く用いられるスプリント療法は、保険適用となる場合と保険適用外の混合診療となる場合があり、その費用は数万円程度が目安となることが多いです。具体的な費用については、受診する医療機関に直接問い合わせて確認するようにしましょう。
まとめ:顎の不調は体からのサイン。セルフケアと専門家の力を借りて改善しよう
顎関節症は、顎の痛みやカクカク音、口の開けづらさといった症状を引き起こし、日常生活に大きな影響を与えることがあります。顎の不調は、ストレスや食いしばり、不良姿勢といった日々の生活習慣の乱れからくる、体からの大切なサインと捉えることができます。
この記事でご紹介したように、硬い食べ物を避ける、姿勢を意識する、顎周りのマッサージを行う、そして何よりも心身をリラックスさせるためのストレス解消法など、ご自身で実践できるセルフケアはたくさんあります。これらのセルフケアは症状緩和の第一歩として非常に有効ですが、もし症状が改善しない場合や痛みが強い場合には、ためらわずに歯科や口腔外科といった専門家の助けを借りることが大切です。適切なセルフケアと専門的な治療を組み合わせることで、多くの場合、顎関節症の症状は改善し、快適な生活を取り戻すことができます。
少しでも参考になれば幸いです。
自身の歯についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
監修者
東京歯科大学卒業後、千代田区の帝国ホテルインペリアルタワー内名執歯科・新有楽町ビル歯科に入職。
その後、小野瀬歯科医院を引き継ぎ、新宿オークタワー歯科クリニック開院し現在に至ります。
また、毎月医療情報を提供する歯科新聞を発行しています。
【所属】
・日本放射線学会 歯科エックス線優良医
・JAID 常務理事
・P.G.Iクラブ会員
・日本歯科放射線学会 歯科エックス線優良医
・日本口腔インプラント学会 会員
・日本歯周病学会 会員
・ICOI(国際インプラント学会)アジアエリア役員 認定医、指導医(ディプロマ)
・インディアナ大学 客員教授
・IMS社VividWhiteホワイトニング 認定医
・日本大学大学院歯学研究科口腔生理学 在籍
【略歴】
・東京歯科大学 卒業
・帝国ホテルインペリアルタワー内名執歯科
・新有楽町ビル歯科
・小野瀬歯科医院 継承
・新宿オークタワー歯科クリニック 開院
新宿区西新宿駅徒歩4分の歯医者・歯科
『新宿オークタワー歯科クリニック』
住所:東京都新宿区西新宿6丁目8−1 新宿オークタワーA 203
TEL:03-6279-0018