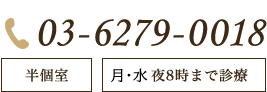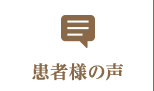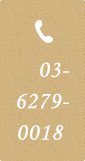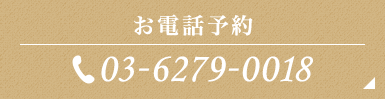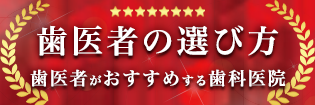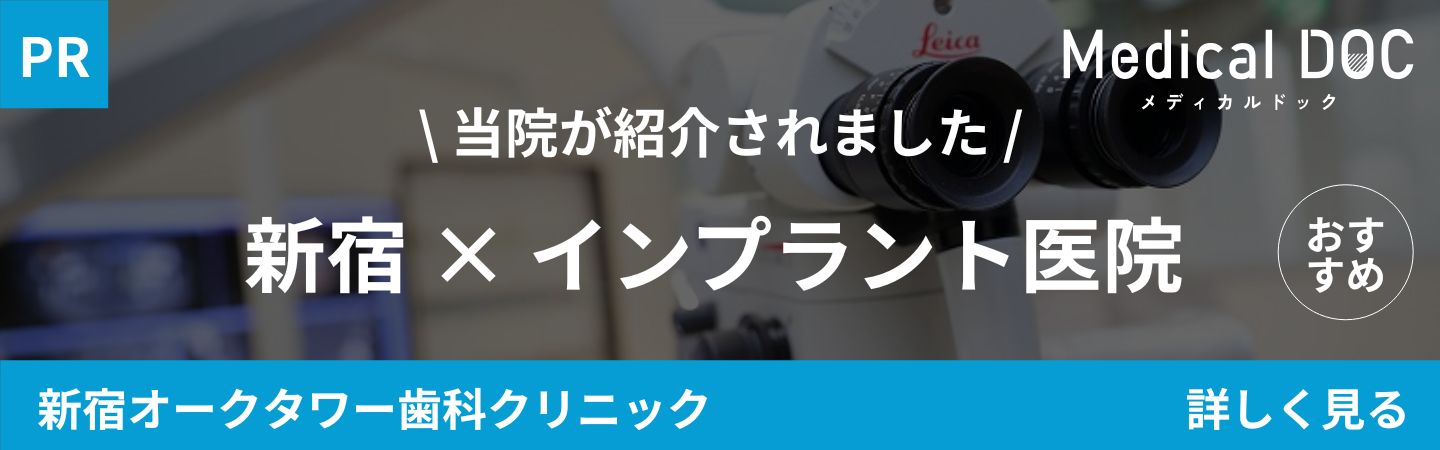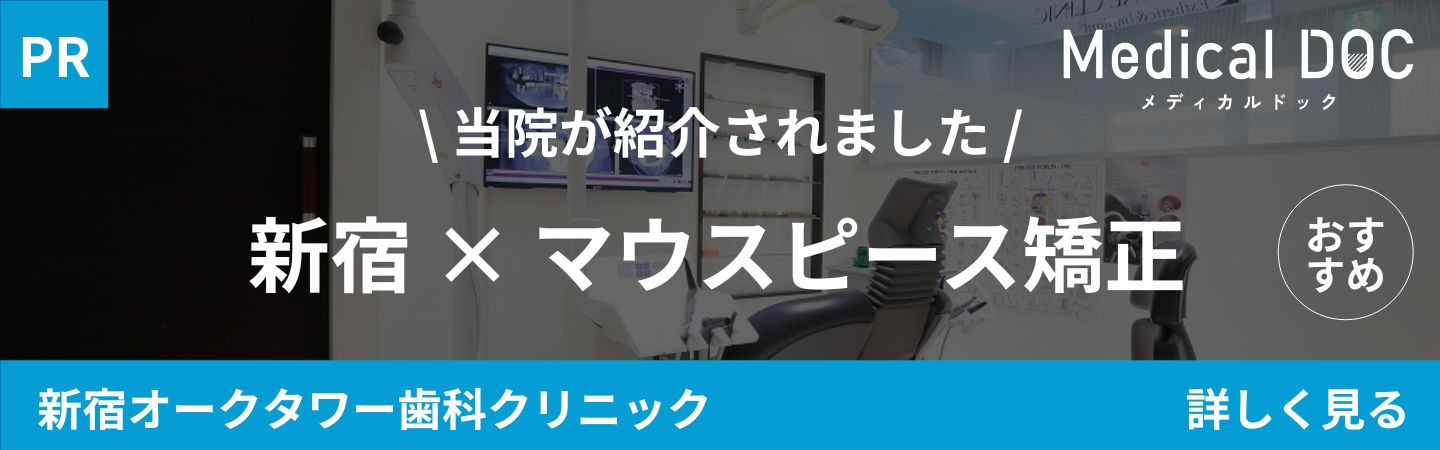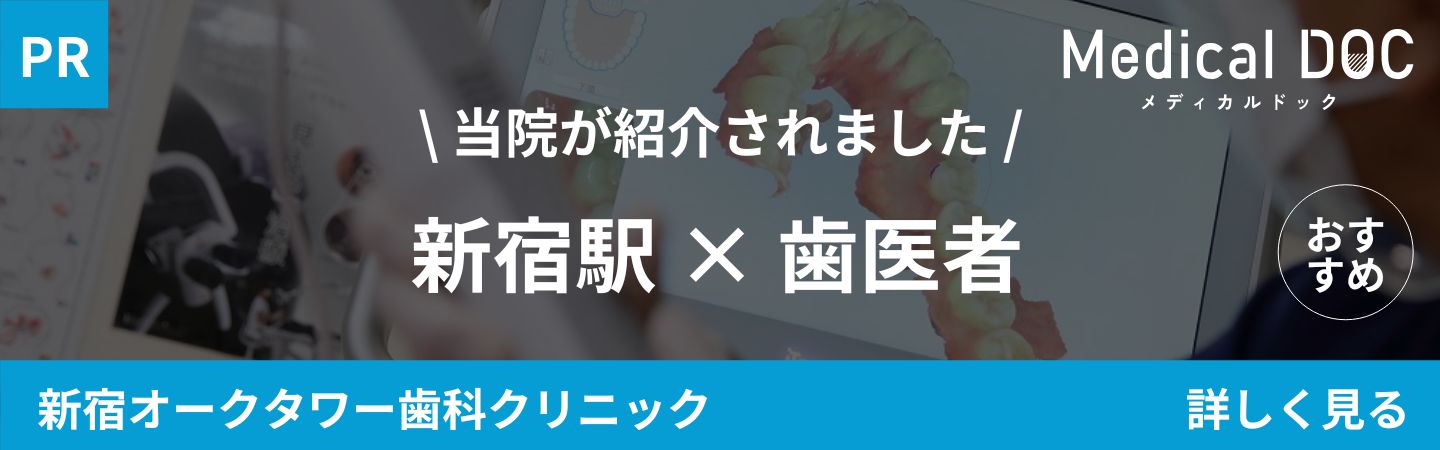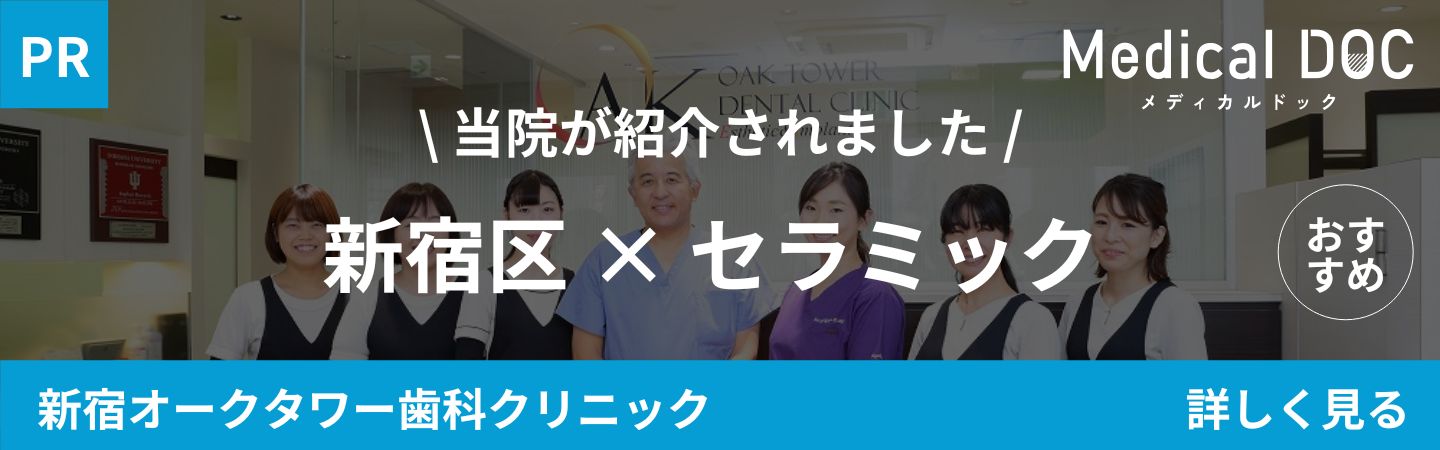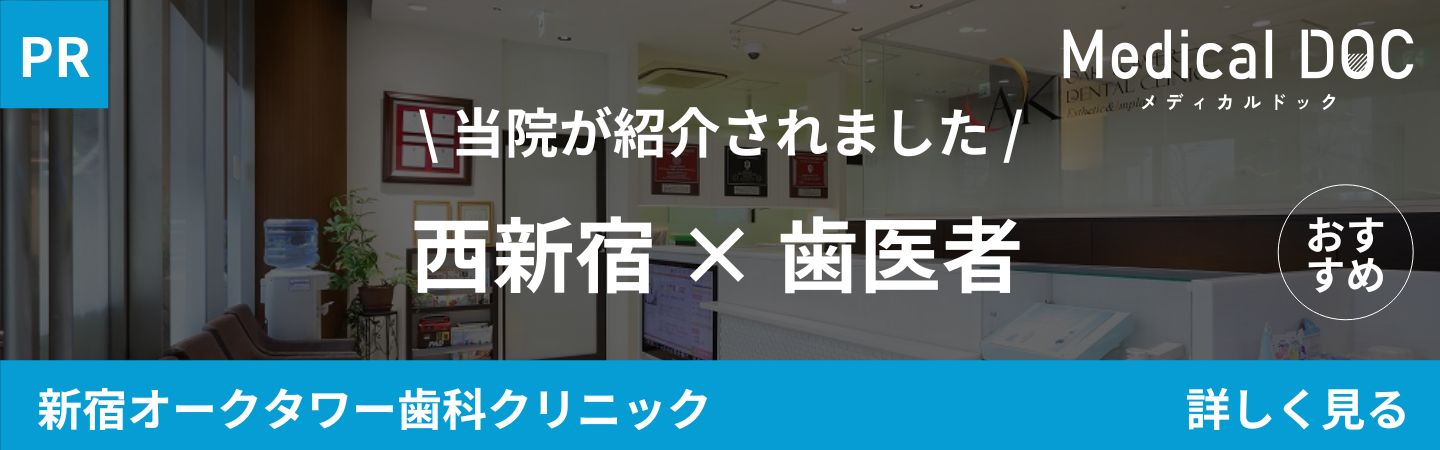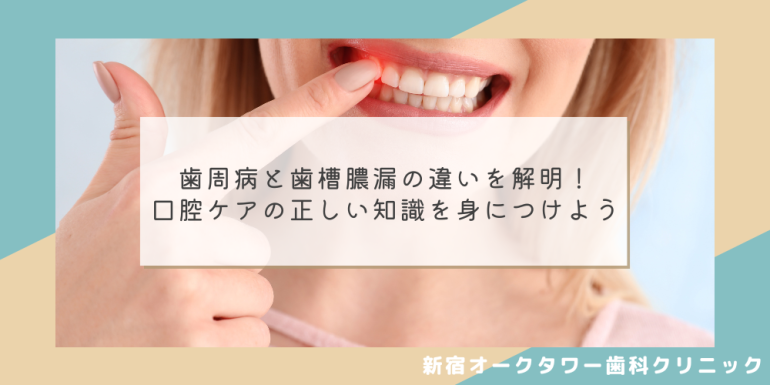
新宿オークタワー歯科クリニックです。
最近、歯ぐきからの出血が気になったり、家族から口臭を指摘されたりして、「もしかして歯周病かな?」と不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。歯科検診で「歯周ポケットが深い」と言われて、治療が必要なのかと心配になっているかもしれません。また、「歯周病」と「歯槽膿漏」という言葉を耳にするものの、その違いがよく分からず、ご自身の症状がどちらに当てはまるのか悩んでいる方も少なくないはずです。
この記事では、そのような疑問や不安をお持ちの方のために、「歯周病」と「歯槽膿漏」の違いを分かりやすく解説します。それぞれの病気がどのような状態を指すのか、なぜ発症するのか、そしてご自身でできる予防やセルフケアの方法、さらに歯科医院で受けられる専門的な治療法まで、口腔ケアに関する正しい知識を丁寧にお伝えします。この情報を通じて、あなたの歯と全身の健康を守るための一歩を踏み出すお手伝いができれば幸いです。
「歯周病」と「歯槽膿漏」の違いとは?実は密接な関係
歯ぐきの腫れや出血、口臭、そして歯科検診で指摘される「歯周病」。しかし、その一方で「歯槽膿漏」という言葉も耳にすることがあり、どちらがご自身の症状に当てはまるのか、あるいは両者は同じ病気なのかと疑問に感じる方も少なくないでしょう。
「歯周病」と「歯槽膿漏」は、全く別の病気というわけではなく、実は密接な関係にあります。多くの方が混同しがちですが、それぞれの言葉が指す意味合いには明確な違いがあるのです。
まず、「歯周病」がどのような病気の総称であるか、そして「歯槽膿漏」がその中でどのような位置づけにあるのかを詳しく解説します。これらを理解することで、ご自身の口腔内の状態をより正確に把握し、適切なケアや治療へ繋げる第一歩となるでしょう。
歯周病は歯を支える組織の病気の総称
「歯周病」とは、歯を支えている周りの組織に起こる病気の総称です。具体的には、歯肉(歯ぐき)、歯根膜(しこんまく)、セメント質、そして歯槽骨(しそうこつ)といった、歯を顎の骨にしっかりと固定する役割を持つ組織すべてが対象となります。
この病気は、主に歯肉に炎症が起こる「歯肉炎」と、さらに炎症が進行して歯槽骨まで破壊されてしまう「歯周炎」という二つの状態を含んでいます。つまり、一口に「歯周病」といっても、その進行度合いや影響を受ける組織の範囲によって、状態が異なることを意味します。
歯周病は、歯そのものが虫歯のように溶ける病気ではなく、あくまで歯を支える土台に問題が起こる病気なのです。そのため、歯が健康な状態に見えても、歯周病が進行している可能性も十分にあります。
歯槽膿漏は重度に進行した歯周病の状態を指す言葉
「歯槽膿漏(しそうのうろう)」という言葉は、多くの方が耳にしたことがあるかもしれません。しかし、実はこれは正式な病名ではありません。歯槽膿漏とは、歯周病が非常に重度に進行した状態、特に「歯槽骨から膿が漏れ出す」という症状が顕著になった状態を指す、一般的に使われている俗称です。
言葉の由来が示す通り、歯槽膿漏の段階では、歯を支える骨の破壊が著しく進み、歯ぐきから膿が出たり、強い口臭が発生したり、歯がグラグラしたりといった、深刻な症状が現れます。これは、歯周病の中でも「重度歯周炎」と呼ばれる段階に相当します。
したがって、「歯周病」という大きなカテゴリーの中に、「歯槽膿漏」という、病気が最も悪化した状態が含まれる、という関係性で理解することができます。この状態に至る前段階で、いかに歯周病の進行を食い止められるかが、歯の健康を維持する上で非常に重要となります。
ご自身の症状はどの段階?歯周病の進行ステージとセルフチェック
歯周病は、ある日突然重症になるわけではなく、初期の段階から少しずつ進行していく病気です。初期のサインを見逃さずに適切なケアをすれば、健康な状態に戻せる可能性が高まります。しかし、放置してしまうと、骨の破壊が進み、最終的には大切な歯を失ってしまうことにもなりかねません。
ご自身の歯ぐきや歯の周りの状態に目を向けてみてください。歯みがきの時に出血はありませんか?口臭が気になったり、歯がグラつく感じがしたりしませんか?これらの症状は、歯周病のサインかもしれません。
歯周病がどのように進行していくのかを、3つのステージに分けて詳しく解説します。ご自身の症状と照らし合わせながら読み進めていただくことで、今、どの段階にいるのか、どのような対処が必要なのかを理解する手助けになるでしょう。
ステージ1:歯肉炎 – 歯ぐきからの初期サイン
歯周病の最初の段階は「歯肉炎」と呼ばれます。この段階では、まだ歯を支えている骨が溶けてしまうことはなく、歯ぐきだけに炎症が起こっている状態です。主なサインとしては、歯ぐきが赤く腫れていたり、歯みがきの時やデンタルフロスを使った時に出血が見られたりすることが挙げられます。
痛みを感じることが少ないため、ご自身では気づきにくい場合も多くあります。しかし、この段階で炎症を放置すると、歯周病は次の段階へと進行してしまいます。初期の段階であれば、適切なブラッシングなどのセルフケアを毎日きちんと行うことで、健康な歯ぐきの状態を取り戻せる可能性が十分にあります。
歯みがき時の出血は、体が発する重要なサインです。このサインを見逃さず、ご自身の口腔ケアを見直すきっかけにしてください。早めの対処が、歯周病の進行を防ぐための大切な一歩となります。
ステージ2:軽度〜中等度歯周炎 – 歯周ポケットが深くなる
歯肉炎がさらに進行すると、「軽度から中等度の歯周炎」という段階へと進みます。このステージでは、歯と歯ぐきの間の溝である「歯周ポケット」が少しずつ深くなり、歯を支えている骨(歯槽骨)の破壊が始まります。歯ぐきの赤みや腫れ、出血といった歯肉炎の症状に加えて、以下のような変化が現れることがあります。
口臭が強くなったり、歯ぐきが下がって歯が長く見えるようになったり、冷たいものが歯にしみやすくなったりするといった症状です。これらの症状は、歯周病菌がさらに奥深くへと侵入し、組織へのダメージが広がっていることを示しています。この段階になると、毎日のセルフケアだけでは症状の改善が難しくなります。
歯科医院での専門的な治療が必要となります。進行を食い止めるためには、歯周ポケットの奥にこびりついた歯垢や歯石を歯科医師や歯科衛生士に除去してもらうことが不可欠です。早期に専門的な治療を受けることで、さらなる骨の破壊を防ぎ、歯の寿命を延ばすことにつながります。
ステージ3:重度歯周炎(歯槽膿漏)- 歯がぐらつき、膿が出ることも
歯周病が最も進行した段階が「重度歯周炎」であり、一般的には「歯槽膿漏」と呼ばれる状態です。この段階にまで進むと、歯を支える歯槽骨の破壊が非常に大きく進んでしまい、歯周ポケットはさらに深く、時には10mmを超えることもあります。これにより、歯がグラグラと揺れ始め、最悪の場合には自然に抜け落ちてしまう危険性もあります。
症状としては、歯ぐきからの出血や腫れがひどくなり、歯ぐきから膿(うみ)が出ることがあります。膿が出ると、強い口臭を伴うことが多く、周囲の人にも不快感を与えてしまうことがあります。また、歯のグラつきが大きくなるため、食べ物をしっかりと噛むことが難しくなり、食生活にも大きな影響が出ます。
このステージでは、歯科医院での集中的な治療が必要となります。失われた骨を完全に元通りにすることは非常に難しいですが、これ以上の進行を食い止め、残っている歯をできるだけ長く維持するための治療が不可欠です。重度歯周炎に至る前に、適切な治療を受けることが大切です。
なぜ歯周病になるのか?知っておきたい主な原因
歯周病は、多くの方が悩まれるお口の病気ですが、「なぜ自分は歯周病になってしまったのだろう?」と疑問に思われる方も少なくありません。歯周病がなぜ発症し、進行してしまうのか、その根本的な原因と、病気のリスクを高めるさまざまな要因について詳しく解説します。歯周病は一つの原因だけで起こるのではなく、複数の要因が絡み合って発症することがほとんどです。
これから、歯周病の直接的な原因である「歯垢(プラーク)」とその中に潜む歯周病菌について、そして喫煙や糖尿病などの全身疾患、日々の生活習慣がどのように歯周病を悪化させるのか、具体的な内容を見ていきましょう。ご自身の状況と照らし合わせながら読み進めることで、歯周病への理解が深まり、より効果的な予防や対策に繋がるはずです。
最大の原因は「歯垢(プラーク)」の中の歯周病菌
歯周病の最大の原因は、実はご自身の口の中に常に存在している「歯垢(プラーク)」の中に潜む細菌です。歯垢とは、単なる食べかすではなく、口腔内のさまざまな細菌が集まって形成される、ネバネバとした塊のことを指します。この歯垢は、歯の表面だけでなく、歯と歯ぐきの境目や歯周ポケットと呼ばれる深い溝にまで付着し、そこで細菌が繁殖し続けます。
歯垢の中には、数多くの種類の細菌が生息しており、その中でも特に歯周病を引き起こす悪性の細菌群が「歯周病菌」と呼ばれています。これらの歯周病菌は、歯ぐきの組織に対して炎症を引き起こす毒素を放出します。この毒素が歯ぐきに侵入することで、歯ぐきが赤く腫れたり、出血しやすくなったりといった初期の炎症症状(歯肉炎)が現れるのです。また、歯周病の進行に深く関与する特定の細菌群は「レッドコンプレックス」と総称され、これにはPorphyromonas gingivalis(ポルフィロモナス・ジンジバリス)などが含まれます。これらの細菌は、歯周ポケットの奥深くで酸素の少ない環境を好み、さらに強力な毒素を産生することで、歯を支える骨まで破壊する「歯周炎」へと病気を進行させていきます。
つまり、歯周病は、この歯垢(プラーク)が歯の表面に長期間留まり、その中の歯周病菌が活動し続けることで発症・進行する感染症だと言えます。毎日の適切な歯磨きによってこの歯垢を徹底的に除去することが、歯周病予防の最も基本的かつ重要なカギとなります。
歯周病のリスクを高める生活習慣や要因
歯周病の原因は、歯垢(プラーク)の中の細菌であることはすでに説明しましたが、なぜ同じように歯磨きをしていても、歯周病になりやすい人となりにくい人がいるのでしょうか。それは、歯垢(プラーク)の量や種類だけでなく、私たちの生活習慣や全身の状態、口腔内の環境など、さまざまな要因が歯周病の発症や進行に影響を与えているからです。
これらの要因は、歯周病菌による攻撃に対する体の抵抗力を弱めたり、プラークが溜まりやすい環境を作ったりすることで、歯周病のリスクを大きく高めてしまいます。歯周病のリスクを高める具体的な要因について詳しく見ていきましょう。ご自身の生活習慣や健康状態と照らし合わせながら、リスクを減らすためのヒントを見つけてみてください。
喫煙
喫煙は、歯周病を悪化させる非常に大きなリスク要因の一つです。タバコに含まれるニコチンは、血管を収縮させる作用があり、これにより歯ぐきの血流が悪くなります。血流が悪くなると、歯ぐきの細胞に十分な酸素や栄養が届かなくなり、体の防御機能が低下します。結果として、歯周病菌に対する抵抗力が弱まり、炎症が広がりやすくなるのです。
さらに、喫煙は歯周病の発見を遅らせる原因にもなります。歯周病が進行すると、歯ぐきからの出血がよく見られる症状の一つですが、喫煙者はニコチンの作用で血管が収縮しているため、炎症が起こっていても出血が抑えられてしまい、病気の初期サインに気づきにくい傾向があります。また、喫煙は歯周病の治療効果を低下させ、治癒を妨げる可能性も指摘されています。もし喫煙されている場合は、禁煙が歯周病改善への第一歩となります。
糖尿病などの全身疾患や薬の副作用
歯周病は、お口の中だけの病気だと思われがちですが、実は全身の健康状態と密接に関わっています。特に「糖尿病」は歯周病と深く関連していることで知られています。糖尿病の患者さんは免疫機能が低下しているため、歯周病菌に対する抵抗力が弱く、歯周病が悪化しやすい傾向にあります。逆に、歯周病による炎症が全身に及ぶことで、血糖値のコントロールがさらに難しくなるという「双方向の関係」が明らかになっています。
また、糖尿病以外にも、特定の薬の副作用が歯周病に影響を与えることがあります。例えば、高血圧治療に用いられる一部の降圧剤や、免疫疾患の治療に使われる免疫抑制剤などには、歯ぐきが腫れやすくなる副作用が見られることがあります。さらに、妊娠中の女性はホルモンバランスの変化により歯ぐきが炎症を起こしやすくなる「妊娠性歯肉炎」になることもあります。このように、全身疾患や服用している薬、体の状態の変化も歯周病に影響を与えるため、歯科医院を受診する際は、ご自身の健康状態や服用中の薬について詳しく伝えることが大切ですいです。
ストレスや不規則な食生活
日々のストレスや不規則な食生活も、歯周病のリスクを高める要因となり得ます。強いストレスを感じると、私たちの体は免疫力が低下しやすくなります。免疫力が下がると、歯周病菌と戦う体の防御機能が弱まるため、歯周病の発症や進行を早めてしまう可能性があります。
また、食生活の乱れも歯ぐきの健康に影響を与えます。例えば、ビタミンCはコラーゲンの生成に不可欠であり、歯ぐきの組織を強く保つ上で重要な役割を担っています。しかし、偏った食生活によってビタミン類が不足すると、歯ぐきの抵抗力が落ち、炎症が起こりやすくなります。さらに、糖分の多い食事を頻繁に摂ることは、虫歯だけでなく歯周病菌のエサとなり、プラークの形成を促進させることにもつながります。バランスの取れた食事と適切なストレスマネジメントは、全身の健康だけでなく、口腔内の健康維持にも欠かせない要素なのです。
歯並びや不適合な被せ物
お口の中の物理的な環境も、歯周病のリスクに大きく関わってきます。例えば、歯並びが悪いと、歯が重なり合っていたり、デコボコしていたりする部分が多くなります。このような部分は歯ブラシの毛先が届きにくいため、どうしても歯垢(プラーク)が残りやすくなります。プラークが長期間蓄積されると、そこに歯周病菌が繁殖し、歯周病のリスクが高まります。
また、過去に治療した詰め物や被せ物が歯にぴったり合っていない「不適合な被せ物」も、歯周病の原因となることがあります。詰め物や被せ物の縁が段差になっていたり、隙間があったりすると、その部分に食べかすやプラークが溜まりやすくなります。さらに、そうした不適合な部分は清掃が困難なため、歯周病菌が繁殖しやすい温床となってしまうのです。これにより、歯周病が進行しやすくなるため、定期的な歯科検診で被せ物の状態をチェックしてもらうことが非常に重要になります。
今日から実践!自宅でできる歯周病の予防とセルフケア
歯周病の予防や進行を抑えるためには、歯科医院での治療はもちろんのこと、日々のセルフケアが非常に重要です。毎日の少しの心がけが、歯ぐきの健康を大きく左右するといっても過言ではありません。
ご自宅で今日からすぐに実践できる効果的な予防策やセルフケアの方法を具体的にご紹介します。正しい知識を身につけ、ご自身の口腔ケアを見直すきっかけにしていただければ幸いです。
基本は毎日の正しいブラッシング
歯周病予防の基本中の基本は、毎日の正しい歯磨きです。特に、歯周病の原因となる歯垢(プラーク)が溜まりやすい歯と歯ぐきの境目、いわゆる「歯周ポケット」の清掃を意識することが重要になります。
歯周ポケットの清掃には、「バス法」と呼ばれるブラッシング方法が効果的です。歯ブラシの毛先を歯と歯ぐきの境目に45度の角度で当て、軽い力で小刻みに振動させるように磨きます。歯ブラシの毛先が歯周ポケットの中まで届き、そこに潜む歯周病菌を効率的に除去できます。力を入れすぎると歯ぐきを傷つけたり、歯を削ってしまったりする原因にもなりますので、優しく丁寧に行うことを心がけましょう。
歯間ブラシやデンタルフロスで歯垢除去率を向上
どんなに丁寧に歯ブラシを使っても、歯と歯の間や、歯並びが複雑な部分には、どうしても歯ブラシの毛先が届きにくいものです。これらの「死角」に潜む歯垢を効果的に除去するためには、補助的な清掃用具の活用が不可欠になります。
デンタルフロスは、歯と歯の隙間が狭い部分の歯垢除去に役立ちます。フロスを歯と歯の間に通し、歯の面に沿わせるようにして上下に優しく動かして清掃します。一方、歯間ブラシは、歯と歯の間の隙間が比較的広い部分や、歯ぐきが下がってできた隙間の清掃に適しています。重要なのは、ご自身の歯と歯ぐきの隙間に合ったサイズの歯間ブラシを選ぶことです。無理に大きなサイズを使うと歯ぐきを傷つけ、小さすぎると効果が十分に得られません。歯科医院で適切なサイズを相談してみるのも良いでしょう。
食生活や生活習慣の見直しも大切なケアの一部
歯周病の予防には、口腔内の清掃だけでなく、全身の健康状態も大きく影響します。以前にご説明したように、喫煙やストレス、栄養バランスの偏りといった生活習慣が歯周病のリスクを高める要因となりますので、これらを見直すことも大切なケアの一部です。
例えば、喫煙は歯ぐきの血流を悪化させ、歯周病の進行を早めることが分かっています。禁煙は歯周病の改善だけでなく、全身の健康にとっても非常に有効な一歩です。また、ストレスは免疫力を低下させ、歯周病菌への抵抗力を弱めることがあります。適度な運動や十分な睡眠を取り入れ、ストレスを上手に管理することも大切です。さらに、ビタミンCなどの栄養素が不足すると、歯ぐきの健康が損なわれやすくなりますので、野菜や果物を積極的に摂取するなど、バランスの取れた食生活を心がけましょう。これらの生活習慣の改善は、体の内側から歯ぐきの健康を支え、歯周病予防に貢献してくれます。
症状が気になったら歯科医院へ|専門的な治療法を知ろう
毎日の丁寧なセルフケアは、歯周病の予防や進行を抑える上で非常に重要です。しかし、一度進行してしまった歯周病や、セルフケアだけでは改善が見られない症状に対しては、歯科医院での専門的な治療が不可欠となります。歯ぐきからの出血が止まらない、口臭が気になる、歯がぐらつくといった症状に気づいたら、自己判断で放置せず、できるだけ早く専門医に相談することが、ご自身の歯と全身の健康を守る第一歩です。
歯科医院では、患者さま一人ひとりの口腔内の状態や歯周病の進行度合いを詳しく検査し、最適な治療計画を提案します。初期の歯周病であれば比較的簡単な処置で改善が見込めますが、進行した歯周病にはより専門的な治療が必要になることもあります。どのような治療法があるのかを知ることで、不安なく治療に臨めるでしょう。
このセクションでは、歯科医院で行われる基本的な治療から、さらに進行した場合の外科的な治療、そして治療後の大切なメンテナンスまで、専門的な歯周病治療の選択肢についてご紹介します。早期の受診が、治療の選択肢を広げ、ご自身の歯を長く使い続けることにつながります。
歯周病の基本的な治療(歯石除去など)
歯科医院で行われる歯周病の基本的な治療は、歯周病の原因となっている歯垢(プラーク)や歯石を徹底的に除去することから始まります。毎日の歯磨きで取り除けなかった歯垢は、時間の経過とともに唾液中のカルシウムなどと結びつき、硬い「歯石」へと変化します。歯石の表面はザラザラしているため、さらに歯垢が付着しやすくなり、歯周病を悪化させる温床となってしまうのです。
この歯石を除去するために行われるのが「スケーリング」です。スケーラーと呼ばれる専門の器具を使って、歯の表面や歯周ポケット(歯と歯ぐきの間の溝)の奥深くにこびりついた歯石を丁寧に取り除いていきます。歯石がなくなることで、歯ぐきの炎症が治まりやすくなり、歯周病の進行を抑えることが期待できます。
さらに、歯周ポケットの奥深くにある歯の根の表面に付着した歯石や、歯周病菌に汚染された組織を取り除き、根の表面を滑らかにする「ルートプレーニング」という処置も行われます。根の表面をツルツルにすることで、歯垢が再付着しにくくなり、歯ぐきが再び健康な状態に引き締まりやすくなります。これらの基本的な治療は、歯周病の原因を根本から取り除く上で欠かせないステップとなります。
進行した場合の治療法(歯周外科治療など)
歯周病が中等度から重度に進行し、歯周ポケットが深く、基本的なスケーリングやルートプレーニングだけでは原因となる歯石や汚染物質を完全に除去できない場合、より専門的な「歯周外科治療」が必要となることがあります。その代表的なものが「フラップ手術」です。
フラップ手術では、歯ぐきを一時的に切開し、めくり上げることで、歯の根の深い部分や、通常では見えない歯槽骨の状態を直接確認しながら、徹底的に歯石や病変組織を除去します。これにより、歯周ポケットの奥深くに隠れたプラークや歯石を確実に除去し、炎症の原因を取り除くことが可能になります。手術後は歯ぐきをもとの位置に戻し、縫合します。
また、歯周病によって失われた歯槽骨や歯根膜などの組織を再生させることを目的とした「再生療法」も行われることがあります。これは、特定の材料や成長因子を使用し、失われた組織の回復を促す治療法です。さらに、特定の細菌を除去する効果や、炎症を抑える効果が期待できる「レーザー治療」も、症例によっては用いられることがあります。これらの治療は、歯周病の進行度合いや患者さまの口腔内の状態に応じて、歯科医師が最適な方法を判断し提案します。
治療後も重要!再発を防ぐための定期メンテナンス
歯周病の治療が一段落し、症状が落ち着いたとしても、そこで終わりではありません。歯周病は生活習慣病の一種であり、残念ながら再発しやすい慢性疾患です。そのため、治療後の良い状態を維持し、再発や進行を防ぐためには、歯科医院での「定期メンテナンス」が非常に重要になります。
定期メンテナンスでは、歯科医師や歯科衛生士が、患者さまの口腔内の状態を定期的にチェックします。歯周ポケットの深さや歯ぐきの状態、歯垢や歯石の付着具合などを検査し、問題がないかを確認します。また、ご自身では取り除ききれない歯垢や歯石、バイオフィルム(細菌の塊)を専門的な機械と技術で徹底的にクリーニングします。これは「SPT(サポーティブペリオドンタルセラピー)」や「PMTC(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)」などと呼ばれ、歯周病の再発を防ぐ上で不可欠な処置です。
定期メンテナンスは、患者さまご自身のセルフケアでは対応できない部分を補い、常に良好な口腔環境を維持するために欠かせません。この定期的なプロフェッショナルケアと、日々の適切なセルフケアを両立させることで、歯周病の再発リスクを最小限に抑え、大切な歯を長く健康に保つことができるのです。歯科医院と患者さまが協力し、長期的に口腔ケアに取り組むことが、歯周病管理の鍵となります。
歯周病・歯槽膿漏に関するよくある質問
ここまで歯周病と歯槽膿漏の違いから、原因、セルフケア、そして専門的な治療法について見てきました。しかし、まだいくつか疑問が残っているかもしれませんね。ここでは、皆様が抱きがちな歯周病に関するよくある質問に、専門的な知見に基づいてお答えします。
これらの情報が、口腔ケアに対する不安を解消し、より良い健康習慣を築くための一助となれば幸いです。
Q. 歯周病は他の人にうつりますか?
「歯周病は、家族やパートナーなど身近な人にうつるのではないか」と心配される声をよく耳にします。結論から申し上げますと、歯周病の原因となる細菌自体は、唾液を介して人から人へ感染(伝播)する可能性があります。
例えば、夫婦間での食器の共有やキスなどによって、細菌が口の中に移動することは十分に考えられます。しかし、細菌がうつったからといって、必ずしも歯周病を発症するわけではありません。歯周病の発症や進行には、個人の免疫力や日々の口腔ケアの状況、さらには喫煙や糖尿病といった全身の健康状態が大きく関係しています。口腔衛生状態が良好で免疫力が高い方は、たとえ細菌がうつっても発症しにくい傾向にあります。
したがって、過度に不安になる必要はありませんが、ご家族全員で適切な口腔ケアを実践し、定期的に歯科検診を受けることが、歯周病予防には非常に重要であると言えます。
Q. 歯周病は完全に治りますか?
「一度歯周病になってしまったら、もう完全に治らないのではないか」と心配される方もいらっしゃるかもしれません。この疑問に対しては、歯周病の進行度合いによって回答が異なります。
もし、歯周病の初期段階である「歯肉炎」であれば、歯を支える骨の破壊はまだ起きていません。この段階であれば、適切なブラッシング指導や歯石除去などの専門的なケアを行うことで、歯ぐきは元の健康な状態に回復し、完全に治すことが可能です。
一方で、骨の破壊が進んでしまった「歯周炎」の段階になると、残念ながら失われた歯槽骨を完全に元通りにすることは非常に困難です。歯科治療の目的は、病気の進行を食い止めて現状を維持し、残っている歯をできるだけ長く保つこと、つまり「病気をコントロールすること」に主眼が置かれます。そのため、治療が完了した後も定期的なメンテナンスを継続し、再発や進行を防ぐことが非常に重要となります。
まとめ:正しい知識を身につけて、大切な歯と全身の健康を守ろう
この記事では、多くの方が混同しがちな「歯周病」と「歯槽膿漏」の違いについて、そしてその原因や進行段階、具体的な予防・治療法までを詳しく解説してきました。歯周病は、歯肉炎から始まり、軽度・中等度歯周炎、そして重度歯周炎(歯槽膿漏)へと進行していく病気です。この進行の鍵を握るのは、お口の中の「歯垢(プラーク)」に含まれる歯周病菌であり、喫煙や糖尿病などの生活習慣もそのリスクを大きく高めることをご理解いただけたかと思います。
大切なのは、日々のセルフケアと歯科医院での専門的なケアを両立させることです。毎日の丁寧なブラッシングはもちろん、歯間ブラシやデンタルフロスの活用、そしてバランスの取れた食生活や禁煙といった生活習慣の見直しが、歯周病の予防と進行抑制には欠かせません。もし歯ぐきの腫れや出血、口臭といった気になる症状があれば、早期に歯科医院を受診し、適切な治療を受けることが重要です。
歯周病は、一度進行すると完全に元の状態に戻すことが難しい慢性疾患ですが、適切なケアと定期的なメンテナンスによって、その進行を食い止め、大切な歯を長く健康に保つことができます。お口の健康は全身の健康にも深く関わっていますので、正しい知識を身につけ、今日から実践できることを始めていきましょう。
少しでも参考になれば幸いです。
自身の歯についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
監修者
東京歯科大学卒業後、千代田区の帝国ホテルインペリアルタワー内名執歯科・新有楽町ビル歯科に入職。
その後、小野瀬歯科医院を引き継ぎ、新宿オークタワー歯科クリニック開院し現在に至ります。
また、毎月医療情報を提供する歯科新聞を発行しています。
【所属】
・日本放射線学会 歯科エックス線優良医
・JAID 常務理事
・P.G.Iクラブ会員
・日本歯科放射線学会 歯科エックス線優良医
・日本口腔インプラント学会 会員
・日本歯周病学会 会員
・ICOI(国際インプラント学会)アジアエリア役員 認定医、指導医(ディプロマ)
・インディアナ大学 客員教授
・IMS社VividWhiteホワイトニング 認定医
・日本大学大学院歯学研究科口腔生理学 在籍
【略歴】
・東京歯科大学 卒業
・帝国ホテルインペリアルタワー内名執歯科
・新有楽町ビル歯科
・小野瀬歯科医院 継承
・新宿オークタワー歯科クリニック 開院
新宿区西新宿駅徒歩4分の歯医者・歯科
『新宿オークタワー歯科クリニック』
住所:東京都新宿区西新宿6丁目8−1 新宿オークタワーA 203
TEL:03-6279-0018