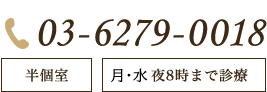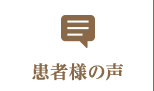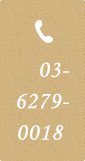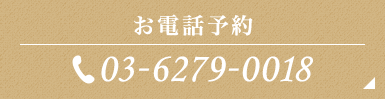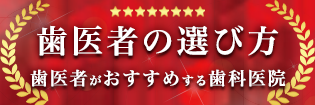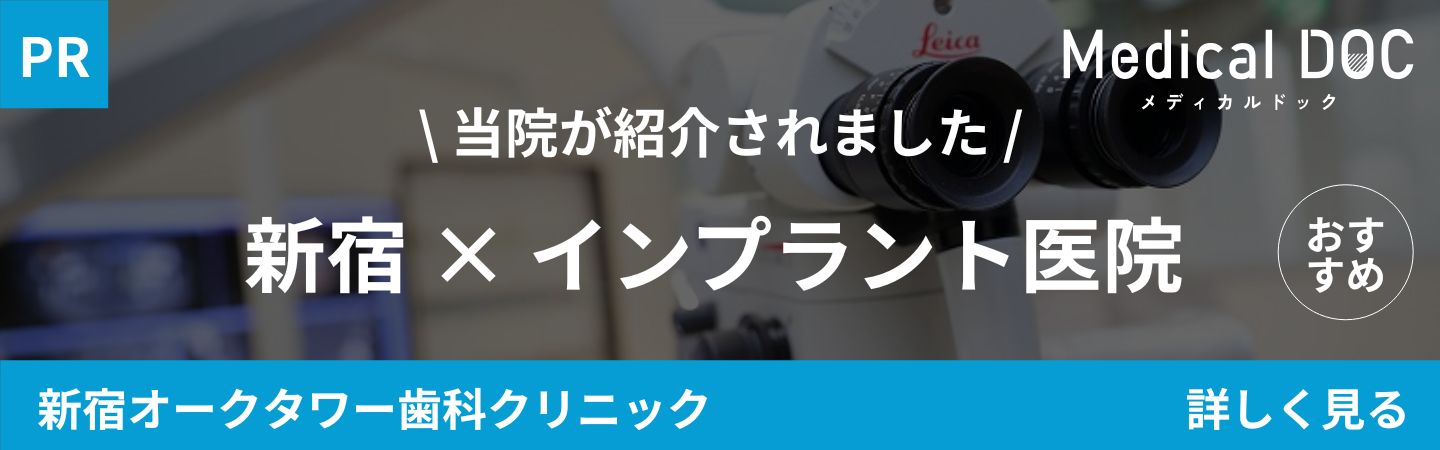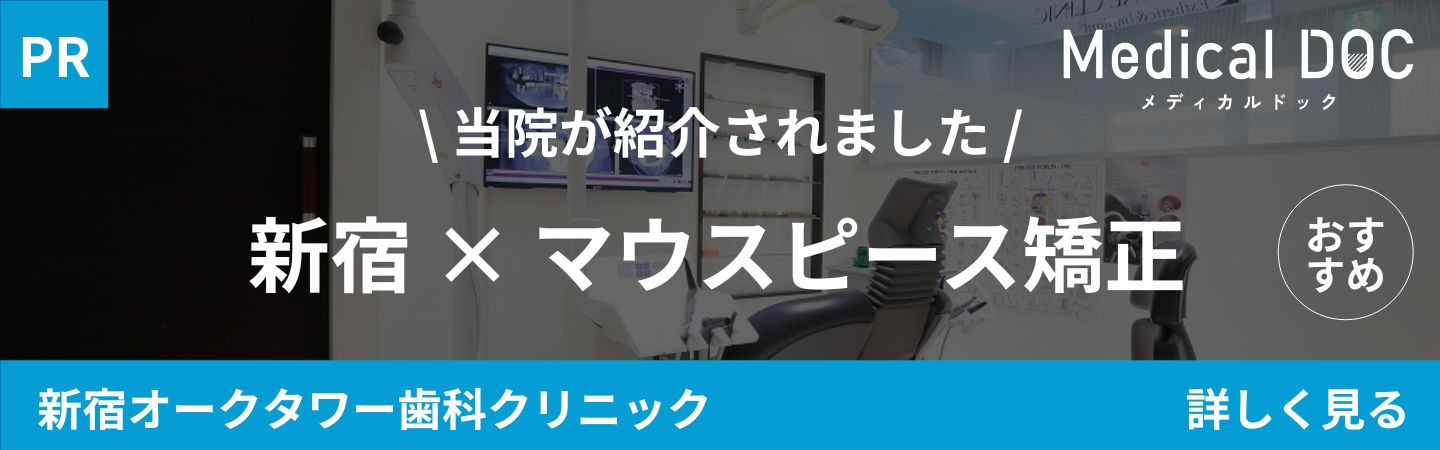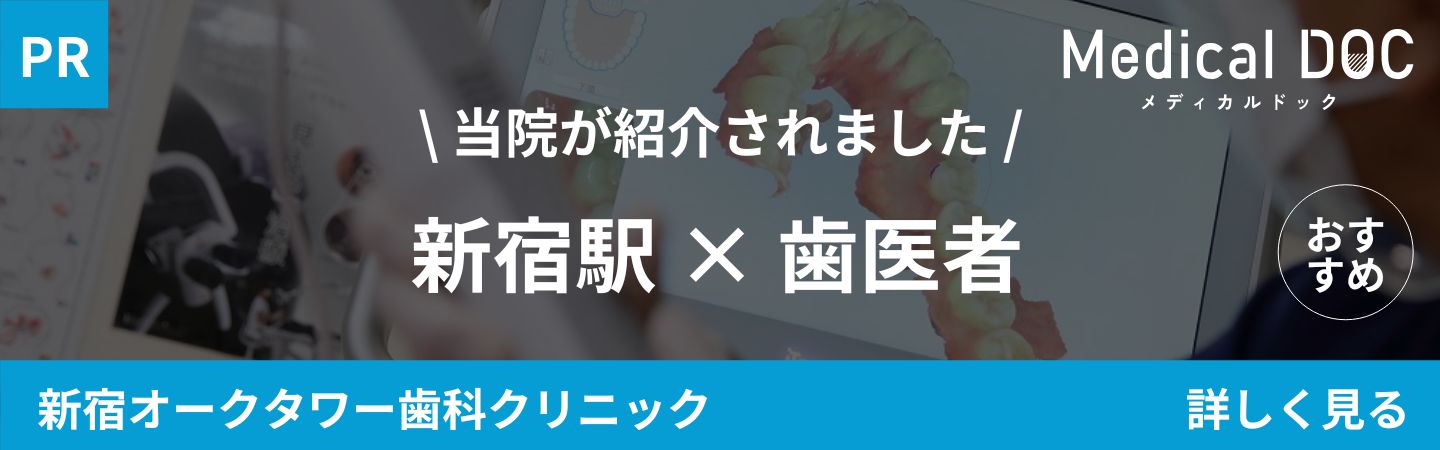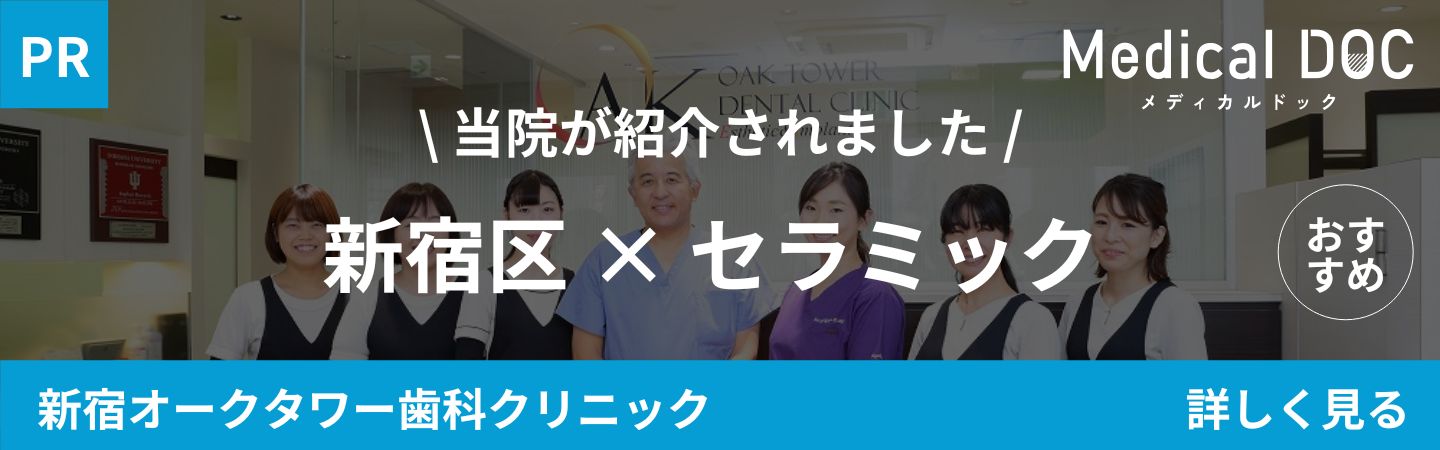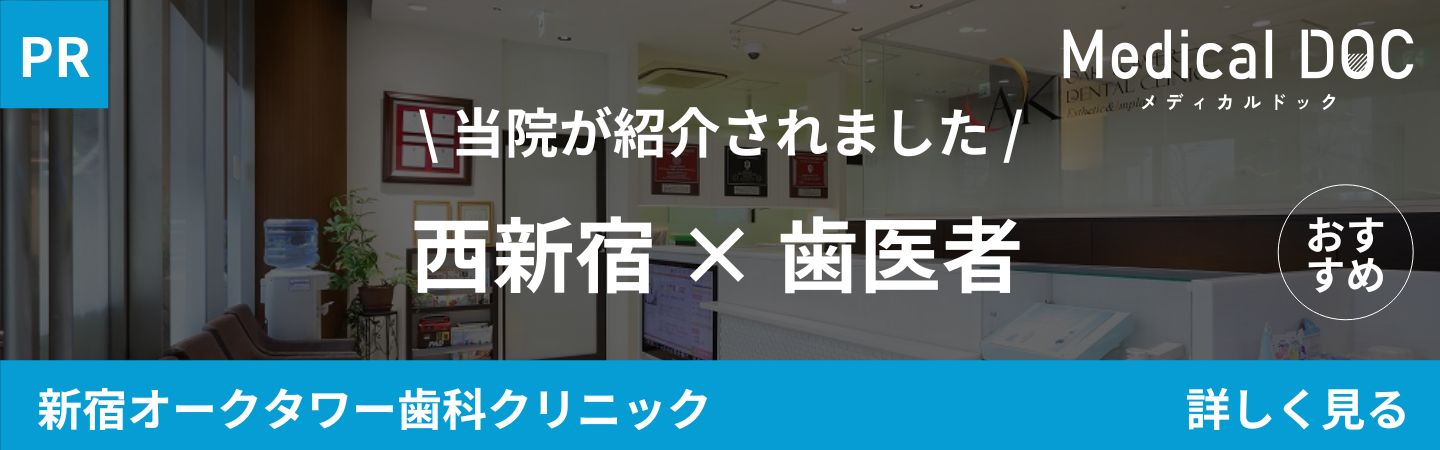新宿オークタワー歯科クリニックです。
歯をきれいに保つならセラミック、強度を求めるなら金属という常識は、ジルコニアの登場で一変しました。人工ダイヤモンド級の高強度と天然歯さながらの半透明性を併せ持つジルコニア治療は、審美性と耐久性の双方を妥協したくない人にとって最先端の選択肢です。本記事では「優れた審美性」「高い耐久性」「金属アレルギーリスクの低減」「幅広い治療への適用」「長寿命」という5つのメリットと、「費用が高い」「割れる可能性がある」「症例によってはセラミックに劣る場合がある」という3つのデメリットを整理し、具体例を交えながら深掘りしていきます。前歯でも自然に仕上がるのか、10年先も安心して使えるのか、費用に見合う価値があるのか――そんな疑問を抱える読者が、自身の口元に最適な治療法を見極められるよう順を追って解説していきます。
ジルコニア治療とは?基本情報を解説
ジルコニア治療は、人工ダイヤモンドとも呼ばれる酸化ジルコニウムを用いた補綴(ほてつ)治療の総称です。従来主流だった金属冠やガラス系セラミックと比較して、強度・耐久性・審美性のバランスに優れている点が特長で、特に奥歯のクラウン(被せ物)やブリッジ、インプラント上部構造で高い評価を得ています。
酸化ジルコニウム自体は1970年代にバイオマテリアルとして応用が始まり、2000年代以降にCAD/CAM(コンピュータ支援設計・製造)技術が進化したことで歯科補綴分野へ一気に普及しました。パウダーを高温で焼き固めた「シンタリングブロック」をミリングマシンで削り出す‐フルデジタル工程により、高精度かつ短納期での修復物製作が可能になっています。
健康保険適用外ではあるものの、10〜15年を超える長期使用が期待できるためライフサイクルコストに優れるのもポイントです。また、金属アレルギーの心配がなく、口腔内でイオン溶出が起きないため生体安全性が高い素材として位置付けられています。
現行のジルコニアクラウンには、高強度を最優先するフルジルコニアと、審美性を高めたマルチレイヤー(グラデーション)タイプが存在します。目的や設置部位によって使い分けることで、読者が求める“美しく長持ちする歯”を実現できる治療法といえます。
ジルコニアの特徴と素材の魅力
ジルコニアは結晶構造が単斜・正方・立方の三相を取り、イットリアを3〜5%添加して正方晶と立方晶を安定化させた部分安定化ジルコニア(Y-TZP)が歯科用途で主流です。応力が加わると微小な結晶が相変態して体積膨張を起こし、進行中のクラック(亀裂)を逆方向から押し戻して止める“トランスフォーマータフニング”が働きます。これにより抗曲げ強さ900〜1200MPa、破壊靱性9〜10MPa√mという驚異的な数値を達成し、人工ダイヤモンドと称されるほどの硬度と耐久性を実現しています。
審美面では、近年のマルチレイヤーブロックやステイニング技術の進歩により、透明感と色調グラデーションが天然歯にきわめて近づきました。光が散乱しやすい微細結晶構造と屈折率のバランスが良いため、従来の不透明感は大幅に解消されています。技工士は複数のシェードを階層的に配置したブロックを選択し、最後に専用着色材で微調整することで、隣在歯と自然に溶け込むクラウンを作製できます。
ジルコニアは生体親和性が高く、表面エネルギーが低いためプラーク(歯垢)が付着しにくい性質があります。歯肉縁下にマージン(境目)が入るブリッジでも炎症リスクが金属冠より低いと報告されており、長期的な歯周組織の安定に寄与します。
メタルクラウンは強度こそ十分ですが見た目や金属アレルギーの懸念があり、ガラスセラミックは審美性は高いものの破折リスクが残ります。ジルコニアはその両者の欠点を補完し、強度・審美・生体安全性という三拍子を兼ね備えた素材として、今後も主流であり続けると予想されています。
ジルコニア治療が適している歯科治療の種類
ジルコニアはクラウン、インレー、ブリッジ、インプラント上部構造、さらにはアバットメントにも応用されます。クラウンでは厚み1.0mm以上確保できる奥歯で最も効果を発揮し、インレーでは咬合面の範囲が広いケースで金属代替材として選択されます。ブリッジでは3〜4ユニットのロングスパン症例でも曲げ強さが維持でき、インプラントではスクリュー固定式のフルジルコニア上部構造が高い評価を得ています。
臨床データでは、臼歯部平均咬合力600〜800Nに対し、フルジルコニアは1500N以上の破折荷重を示すため、高荷重がかかる第一大臼歯やブラキシズム(歯ぎしり)患者に適しています。逆にガラス系セラミックでは荷重限界が低く、破折リスクが急増します。
前歯で審美性を最重視する場合は、フルジルコニアのコアにレイヤリングポーセレンを焼き付けるハイブリッド手法が推奨されます。これによりシャインスルー(光透過)や蛍光性が天然歯と同等になり、単層フルジルコニアより自然な仕上がりが得られます。
ただし、残存歯質が極端に少ない場合や咬合が著しく不安定な症例では、ジルコニアの強度を活かしきれず破折につながる恐れがあります。こうしたケースでは、メタルボンドやファイバーコア併用など別手法を検討する必要があるため、次節の治療フローで診査・診断が重要になる理由が理解できます。
ジルコニア治療の流れ
最初のステップはカウンセリングと診査・診断です。口腔内写真撮影、CTによる骨や神経の立体把握、さらに口腔内スキャナーで歯列をデジタルデータ化します。ここで得た情報をもとに治療計画や費用、治療期間を患者と共有し、同意を得たうえで次工程へ進みます。
形成ではジルコニアの強度を最大限活かすため、均一な厚み1.0〜1.5mmを確保し、マージンはラディアルショルダーまたはチャンファー形態が理想です。薄い部分があると応力集中で破折を招くため、歯科医師は肉眼拡大下で精密に削合し、適切な咬合スペースを設計します。
その後、CADソフトでクラウン形態をデザインし、ミリングマシンでジルコニアブロックを削り出します。削り出し後は約1450℃の高温シンタリング(焼結)を6〜10時間行い、収縮を計算した最終サイズへ変換します。必要に応じてステイニングやグレーズ処理を施し、光沢と色調を微調整します。
試適段階ではマージン適合と咬合接触を確認し、最終装着時にはリン酸エッチング不要のレジンセメントや自己接着性レジンを選択します。咬合調整はダイヤモンドポイントで軽く当たりを取った後、専用ポリッシャーで鏡面仕上げを行うとプラーク付着が抑えられます。装着後のナイトガード処方や定期検診案内を行い、治療フローは完結です。
ジルコニア治療のメリット5選
ジルコニア治療が注目される最大の理由は、従来の金属冠やポーセレン焼付け冠が抱えていた見た目・耐久性・安全性の課題を一挙に解決できる点にあります。本章では「優れた審美性」「高い耐久性と強度」「金属アレルギーのリスクが低い」「幅広い治療への適用」「長寿命とメンテナンスの簡便さ」という5つの核心メリットを、歯科材料学と臨床データの両面から掘り下げます。各項目を読めば、ご自身の治療選択に必要な判断材料が具体的に手に入るはずです。
優れた審美性
ジルコニアは結晶粒子がナノメートルレベルで均一に分散しているため、光が内部で多方向に散乱しながら透過します。この「多重散乱効果」によって、天然歯特有の柔らかな半透明感を再現できます。屈折率もエナメル質に近く、境界面での光の反射が少ないため、不自然な白濁やギラつきが抑えられる点が審美補綴における最大の利点です。
歯肉縁近くが黒ずむ“ブラックマージン”は、金属焼付け冠では避けがたい問題でした。ジルコニア冠は金属を一切含まないため光が歯肉を透過しても暗影が出ず、笑ったときに歯肉ラインが見える症例でも自然な色調を保てます。
近年はマルチレイヤーブロックが登場し、切端部から頸部にかけて色階層がグラデーション構造で成形されています。臨床ではスキャンデータを基にシェードマッピングを行い、技工士がステイニングで微妙な縞模様や透明帯を追加することで「隣在歯と判別できない」レベルまで色合わせが可能です。
ホワイトニングとの相性も良好で、ジルコニアは染料を吸着しにくいため術後の再着色リスクが極めて低いことが報告されています。適切なメンテナンスを行えば、初期の審美性を長期にわたって維持できます。
高い耐久性と強度
部分安定化ジルコニア(Y-TZP)は抗曲げ強さ900〜1200MPa、破壊靱性9〜10MPa√mを示し、ガラス系セラミックの約3〜4倍の強度があります。これは歯科材料の中でも突出しており、患者さんが硬い食品を噛んでも破折しにくい安心感につながります。
口腔内は0〜60℃まで温度が変動し、pHも食事により酸性から中性へ揺れ動きますが、ジルコニアは加水分解や酸腐食に強く、10年以上の臨床追跡で生存率95%以上という報告が複数存在します。
強度だけでなく「デンティンライク・エラスティシティ」に近づける設計思想も重要です。歯科医師はクラウンの厚みを1.0mm以上確保し、マージンを均一なラウンド形態にすることで応力集中を防ぎます。この設計とジルコニアの靱性が相まって、咬合力を効率よく分散できます。
強度が高いことで応用範囲は広がり、ロングスパンブリッジやインプラントのスクリューリテイン式上部構造でも破折リスクを抑えられます。耐久性を最重視する方にとって、ジルコニアは現在最有力の補綴材料と言えます。
金属アレルギーのリスクが低い
ジルコニアはメタルフリー材料であり、口腔内で金属イオンが溶出することがありません。金属冠ではニッケルやクロムが唾液に溶け出し、体内でタンパク質と結合して抗原化することでアレルギー反応を誘発しますが、ジルコニアはこうした機序自体が起こりません。
実際に金属アレルギーによる皮膚湿疹を訴えていた患者さんで、金属冠をジルコニアクラウンへ置換したところ、半年以内に症状が寛解した臨床例が報告されています。皮膚科との連携症例でも同様の改善が確認され、アレルギー対策として有効性が裏付けられています。
さらに、金属イオンが歯肉を黒変させるブラックラインも発生しないため、歯肉が薄いタイプの方でも審美面での不安がありません。インプラントアバットメントにジルコニアを使用した場合、軟組織の付着性が向上しバイオフィルム形成が抑制されるといった報告もあり、口腔全体の生体安全性が高まります。
金属アレルギー既往や金属の見た目に抵抗がある方には、ジルコニアは最も安全性が高い選択肢となります。
幅広い治療への適用
ジルコニアの強度と加工性の高さは、クラウン・インレー・ラミネートベニア・ブリッジ・インプラント上部構造といった多岐にわたる補綴治療で発揮されます。特に奥歯のクラウンでは、金属冠から置き換えても咬合力に十分耐え、審美性も向上します。
CAD/CAM技術の進歩により、カンチレバー式ブリッジやインプラントと天然歯の連結など複雑な設計でも強度計算を行いながら製作可能です。臨床評価ではジルコニア3ユニットブリッジの5年生存率が97%と高く、メタルセラミックに匹敵する結果が得られています。
矯正治療後にプロビジョナルレストレーションから最終補綴へ移行する際、色調データをデジタルで保存しておき、最終クラウンにジルコニアを用いることで治療期間を短縮しつつ高精度な一致が得られます。
5DスキャナやAI搭載デザインソフトの導入により、噛み合わせ再現や色調シミュレーションの精度が大幅に向上しました。これら最新ワークフローに対応した歯科医院を選べば、ジルコニアのポテンシャルを最大限に引き出すことができます。
長寿命とメンテナンスの簡便さ
ジルコニアは表面に圧縮応力がかかる「表面硬化層」を持ち、低温環境下でのマルテンサイト変態(低温老化)に対して高い耐性があります。そのため10〜15年という長期使用が期待でき、実際に12年経過クラウンの生存率が94%と報告された長期研究もあります。
素材の表面エネルギーが低くプラークが付着しにくいことから、二次カリエスの発生率は金属冠に比べ約40%減少したというデータがあります。虫歯の再発を気にして頻繁に再治療する必要がないため、通院回数が少なくて済む点は大きな利点です。
メンテナンス時の注意点は、超音波スケーラーを使用する際にチップを歯肉側から当てないこと、鏡面研磨を維持するためにアルミナ系ではなくダイヤモンドペーストでの最終研磨を行うことなどが挙げられます。これさえ守ればクリーニングは通常のセラミックと同等の手技で完了します。
定期検診の目安は6ヶ月ごとで十分です。日常のケアも通常の歯ブラシとフロスで対応でき、特別な洗浄剤やコーティング処置は不要です。こうした手間の少なさが、ジルコニア補綴が「長く楽に付き合える治療法」と評価されるゆえんです。
ジルコニア治療のデメリット3選
ジルコニアは「人工ダイヤモンド」と称されるほど優れた素材ですが、完璧ではありません。長所ばかりに目を向けていると、治療後に「こんなはずではなかった」と感じる場面もあり得ます。ここでは、多くの患者さんが実際に悩む三つのデメリット―費用の高さ、割れる可能性、そして審美性がセラミックに劣る場合がある点―に焦点を当て、それぞれの背景と対処法を詳しく解説します。
これらの弱点を理解しておけば、カウンセリング時に的確な質問ができ、追加費用や再治療のリスクを最小限に抑えられます。メリットとデメリットを冷静に比較し、後悔のない治療選択を行うための土台としてご活用ください。
費用が高い
ジルコニアクラウンは1本あたりおおよそ10万円前後が相場で、保険適用外となる自費診療です。材料そのものの価格に加え、CAD/CAMシステムや高温焼結炉などの高価な設備投資、さらに高度な技工作業料が上乗せされるため、どうしてもコストが高くなります。
初期費用だけに注目すると割高に感じますが、ライフサイクルコストで比較すると評価は変わります。例えば金属冠が7年程度で再治療になるケースと、ジルコニアが12年以上機能するケースを比べると、長期的な通院回数や再製作費用を含めた総額ではジルコニアの方が安くなる可能性があります。痛みや再通院のストレスを減らせる点も、金銭以外の価値として見逃せません。
とはいえ大きな出費に変わりはないため、医療費控除を活用して税金負担を軽減したり、デンタルローンで月々の支払いを均等化したりする方法が有効です。また、自費診療でも定額制パッケージや分割払いを用意する医院も増えているため、相談してみる価値があります。
見積もりを受け取る際は「技工所名」「保証期間」「調整・再診料など付帯処置の有無」を必ず確認しましょう。ここを不透明なまま契約すると、万が一トラブルが起きたとき追加費用が発生し、本来の総額が膨らむ恐れがあります。費用面の納得感を得ることが、満足度の高い治療への第一歩です。
割れる可能性がある
ジルコニアは抗曲げ強さ900MPa以上と非常に硬い一方、陶材特有の脆性を持つため、強い衝撃が一点に集中すると破折するリスクがあります。特にクラウンを薄く設計した場合や、尖った咬頭形態を残したまま装着した場合に応力が集中しやすくなります。
ブラキシズム(歯ぎしり)やスポーツで強い咬合力がかかる患者さんでは、実際に破折事例が報告されています。これらのハイリスク症例では、装着後のナイトガード使用やマウスガード装着を徹底することで破折率を大幅に下げることが可能です。
万一割れてしまった場合、通常は補綴物を撤去し、再印象採得から新しいクラウンを再製作します。撤去・再製作には追加費用と再来院の手間がかかるため、事前に保証期間や再製作費用の取り決めを確認しておくと安心です。
破折リスクは設計段階でも抑制できます。均一な厚みを確保し、尖角を丸め、咬合面にストレス集中を起こしにくい形態を選択することが重要です。さらに、装着後に定期的な咬合チェックを行い、噛み合わせを微調整することで、トラブル発生率を最小限に抑えられます。
審美性がセラミックに劣る場合がある
最新の多層ジルコニアは以前より透過性が向上しましたが、依然としてセラミック(ガラスセラミックやE.max)に比べてわずかに白濁しやすく、前歯で光が透ける部位ではオペーク感(不自然な白さ)が出ることがあります。特に薄い唇側歯肉や明るい照明下では、屈折率の差が強調されるため注意が必要です.
この弱点を補う方法として、ジルコニアフレームにレイヤリングポーセレンを築盛する二層構造や、グラデーションを持つマルチレイヤーブロックの使用があります。ただし、追加の技工工程が増える分、費用と製作期間が延びる点は理解しておきましょう。
また、光沢感や蛍光性が天然歯と完全に一致しないケースでは、口角や照明条件によって人工物が強調されることがあります。実際の症例写真を確認し、どの程度の色調差を許容できるかを自分の目で判断することが大切です。
審美面を最優先する場合、前歯はフルセラミック、奥歯はジルコニアといった部位別素材選択が有効です。担当医に希望を伝え、色調試適やモックアップを活用しながら意思決定フローを組み立てると、完成物のイメージギャップを防げます。
ジルコニア治療を選ぶ際のポイント
ジルコニアは審美性と耐久性を兼ね備えた魅力的な材料ですが、あくまで“選択肢の一つ”に過ぎません。費用、口腔内環境、ライフスタイルなど複数の要因を総合評価し、自分に最適な治療計画を立てることが成功の鍵になります。本章では「どの歯科医院で誰に治療を任せるか」「費用をどう捉え、計画するか」「素材をどう選択するか」という三つの視点から、読者が迷わず行動に移せる判断基準を整理します。
歯科医院と歯科医師の選び方
まず確認したいのはデジタルワークフローの導入度です。口腔内スキャナ、CAD/CAMシステム、そして自院または提携技工所でのジルコニア加工実績が豊富かどうかを尋ねましょう。次に累計ジルコニア症例数、破折再製率、保証期間など“数字で示せる実績”を開示してもらうことが信頼性の裏付けになります。
カウンセリングでは具体的な質問を用意すると比較しやすくなります。例として「使用しているジルコニアブロックメーカーはどこか」「破折時の再製作費用は保証に含まれるのか」「色合わせは追加料金か」を挙げておくと、見積もり後の想定外出費を防げます。
症例写真や治療レビューを積極的に公開している医院は、技術だけでなく説明責任にも自信を持っていると考えられます。治療前後の写真を複数提示できるか、補綴後の経過をSNSやブログで発信しているかをチェックし、情報公開度の高さを品質指標に加えましょう。
最後に専門性の裏付けとして、学会認定医・専門医資格、あるいはデジタル補綴関連のセミナー受講歴を確認します。日本補綴歯科学会や日本審美歯科学会の認定医は年間研修や症例報告が義務づけられているため、最新技術へのアップデートが期待できます。
治療費用の比較と計画
クラウン1本あたりの目安はジルコニア10〜14万円、セラミック8〜12万円、メタルクラウン3〜5万円程度です。初期費用だけを見るとメタルクラウンが最安ですが、審美修復を希望する場合はジルコニアとセラミックの二択になり、最終的には色調再現力と耐久性の差が価格差に反映されています。
次にライフサイクルコストを俯瞰しましょう。ジルコニアは10年後の再治療率が約5%、セラミックは15%、メタルクラウンは30%前後と言われます。再治療費と通院回数を加味すると、5年時点での総費用差は縮まり、10年時点ではジルコニアの方が総額で安くなるケースが少なくありません。
具体的な予算組みとしては、①複数医院からの見積もり取得、②医療費控除シミュレーション、③デンタルローンも含めた月額返済額の算出、の順で進めると全体像が掴みやすくなります。医療費控除は10万円超の支出に対して所得税・住民税が軽減されるため、還付額を見込んだ上で資金計画を立てましょう。
最後に投資対効果を“見た目の改善度”“快適な咀嚼機能”“再治療リスク低減”などの指標で数値化します。例えば「審美評価10点中9点」「10年間の再治療回数ゼロ」といった具体的な目標を設定すると、費用を単なる出費ではなく自己投資として捉えやすくなります。
自分に合った治療法の選択
最初に自己チェックリストで現状を整理しましょう。1) 強い咬合力や歯ぎしりがあるか 2) 残存歯質は十分か 3) 金属アレルギー歴はあるか 4) 接客業など審美性を最重視する職業か 5) 長期間の海外滞在予定があるか――これらの項目に○×を付けるだけでも治療方針が見えてきます。
次に素材別適合度をマトリクスで考えます。例えば「耐久性」「審美性」「費用」の三軸をそれぞれ10点満点で採点し、ジルコニアは耐久性9・審美性8・費用6、セラミックは耐久性7・審美性9・費用7、ハイブリッドレジンは耐久性5・審美性6・費用9といった具合に数値化すると優先順位が整理しやすくなります。
評価軸のウエイト付けも重要です。審美性を最重視するなら「審美性50%、耐久性30%、費用20%」のように比重を設定し、各素材のスコアに掛け合わせると視覚的に最適解が浮かび上がります。エクセルや無料のスプレッドシートを使えば数分で算出できます。
最後に歯科医師との相談を円滑にするための要望シートを準備しましょう。希望する色調サンプル、咀嚼時の違和感の有無、予算上限、仕上がり希望日などを記入して持参すると、説明不足によるミスマッチを防げます。これらの準備を整えたうえで専門家の意見を聞けば、納得度の高い治療法を選択できます。
ジルコニア治療後のケアとメンテナンス
ジルコニア補綴は装着した瞬間から長い付き合いが始まります。高い強度と審美性を存分に活かすには、治療直後の対処から日常的なセルフケア、そして定期検診までをワンセットで考えることが重要です。本章では痛みへの即時対応、毎日のケアのコツ、長期的に美しさと機能を保つための注意点を順に解説します。
治療後の痛みとその対策
治療直後に感じる痛みの主原因は大きく三つに分けられます。第一に神経過敏です。歯を削る際に象牙質が露出すると一過性の刺激痛が発生しやすく、装着当日から数日でピークを迎えます。第二に咬合高径のわずかなズレです。ジルコニアは硬いため、噛み合わせが高いままだと力が一点に集中し、翌朝強い痛みとして現れることがあります。第三に歯肉の炎症で、形成時に触れた歯肉が赤く腫れるケースは装着後24〜72時間で自覚症状が出やすい傾向にあります。
痛みを緩和する即効策としては、まず市販のNSAIDs系鎮痛薬(ロキソプロフェンやイブプロフェン)が有効です。噛み合わせ由来の痛みが疑われる場合は歯科医院に連絡し、咬合紙で高い部位を迅速に調整してもらいましょう。歯肉炎症が主因なら、低出力レーザーでの消炎処置や抗炎症薬入りうがい液が効果的です。
三日以上痛みが続く、あるいは夜間にズキズキする場合は、レントゲン撮影やパルプテストで歯髄の状態を確認する必要があります。早期に補綴物を外して神経処置を行えば、破折や二次感染といった深刻なトラブルを回避できますので、我慢せず受診することが肝心です。
セルフケアとしては、装着後1週間は硬い食材を避け、冷たい飲み物や熱いスープなど極端な温度刺激を控えると神経過敏が和らぎます。また、歯磨きは柔らかめのブラシで軽いタッチを心掛け、痛みが治まるまでは患部を強くこすらないようにしましょう。
日常的なケアのポイント
ジルコニア表面はガラスのように滑らかですが、粗いブラッシングで微細な傷が入るとプラークが停滞しやすくなります。歯ブラシは毛先がラウンドカットされたソフトタイプを選び、150g程度の軽い力で小刻みに動かすと表面を傷つけにくいです。電動ブラシを使用する場合も圧力センサー付きのモデルで過度な押し付けを防ぐと安心です。
歯磨剤はフッ素濃度1450ppm以下、かつ低研磨性(RDA70未満)のものが推奨されます。研磨剤が多いホワイトニング用ペーストはジルコニア表面のグレーズ層を早期に摩耗させるおそれがあるため、日常使いには不向きです。フッ素には二次カリエス抑制効果があり、周囲歯質の虫歯リスクを同時に低減できます。
補綴周囲炎を防ぐには、歯と歯の隙間の清掃が不可欠です。コンタクトがタイトな部位はデンタルフロスを縦方向にスライドしながら通し、隙間が0.8mm以上なら歯間ブラシを45度で挿入して内壁を数回こすります。このとき、ジルコニアと天然歯の境界部分を意識的に磨くことでプラーク停滞を最小化できます。
ナイトガードやスポーツマウスピースを併用している方は、毎晩の洗浄が必須です。ぬるま湯と中性洗剤でブラッシングした後、殺菌効果のある専用タブレット溶液に10分浸漬すると細菌・カビの付着を防げます。高温のお湯やアルコール消毒は変形の原因になるため避けましょう。
長持ちさせるための注意点
半年に一度の定期検診では、マージン部の適合状態、接着材の溶解や変色、そして咬合バランスをチェックしてもらうことが不可欠です。特にジルコニアは硬度が高いため、対合歯が摩耗して咬合が変化するケースがあり、早めの微調整でトラブルを未然に防げます。
咬合力が強い人や歯ぎしりの癖がある人は、就寝時のナイトガード装着を習慣化してください。加えて、氷を噛む、パッケージを歯で開けるなど過度な荷重がかかる行為は破折リスクを高めるため控えるのが賢明です。食習慣も左右均等に咀嚼することで、一部の補綴物に負担が集中するのを避けられます。
加齢に伴い歯肉が下がると、ジルコニアと歯質の境界が露出して見た目が損なわれるだけでなく、知覚過敏を起こすことがあります。歯肉マッサージやプラークコントロールで歯周組織を健康に保ち、必要に応じて歯科医院で歯肉移植や再生療法を検討すると審美性を維持しやすくなります。
全身状態も補綴物の寿命に影響します。糖尿病で血糖コントロールが不良だと歯周炎が悪化しやすく、喫煙は血流を阻害して組織の治癒を遅らせます。HbA1cを7%未満に保つ、禁煙外来を利用して本数を減らすなど、生活習慣を見直すことでジルコニアの長期安定性が飛躍的に高まります。
少しでも参考になれば幸いです。
自身の歯についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
監修者
東京歯科大学卒業後、千代田区の帝国ホテルインペリアルタワー内名執歯科・新有楽町ビル歯科に入職。
その後、小野瀬歯科医院を引き継ぎ、新宿オークタワー歯科クリニック開院し現在に至ります。
また、毎月医療情報を提供する歯科新聞を発行しています。
【所属】
・日本放射線学会 歯科エックス線優良医
・JAID 常務理事
・P.G.Iクラブ会員
・日本歯科放射線学会 歯科エックス線優良医
・日本口腔インプラント学会 会員
・日本歯周病学会 会員
・ICOI(国際インプラント学会)アジアエリア役員 認定医、指導医(ディプロマ)
・インディアナ大学 客員教授
・IMS社VividWhiteホワイトニング 認定医
・日本大学大学院歯学研究科口腔生理学 在籍
【略歴】
・東京歯科大学 卒業
・帝国ホテルインペリアルタワー内名執歯科
・新有楽町ビル歯科
・小野瀬歯科医院 継承
・新宿オークタワー歯科クリニック 開院
新宿区西新宿駅徒歩4分の歯医者・歯科
『新宿オークタワー歯科クリニック』
住所:東京都新宿区西新宿6丁目8−1 新宿オークタワーA 203
TEL:03-6279-0018