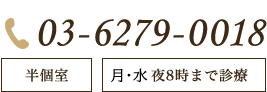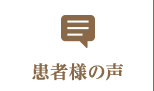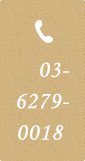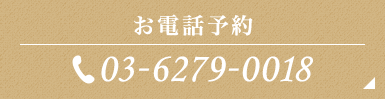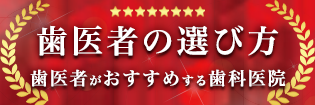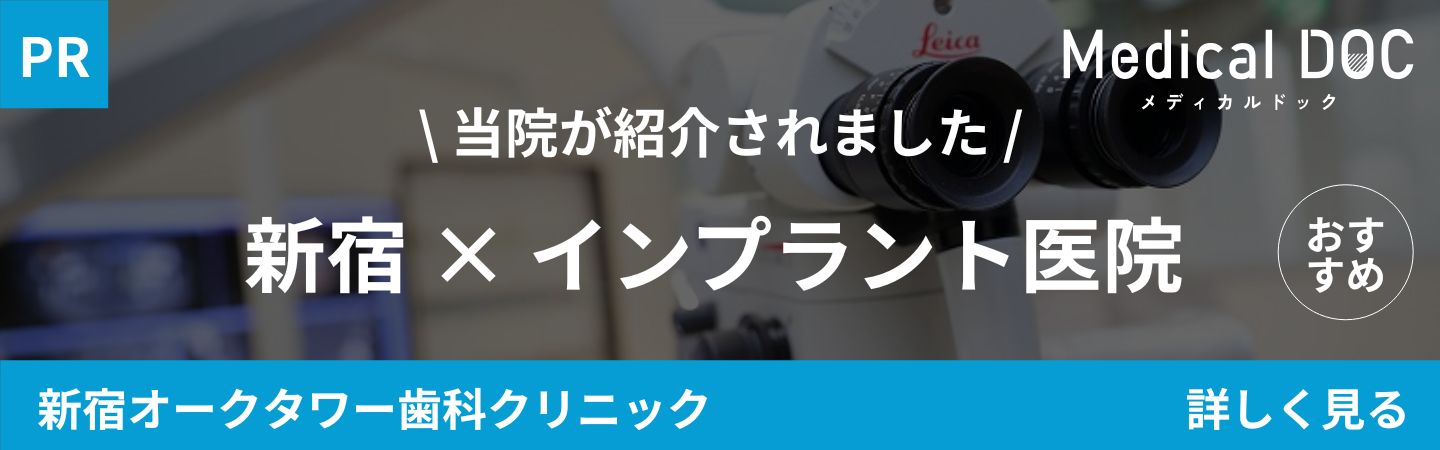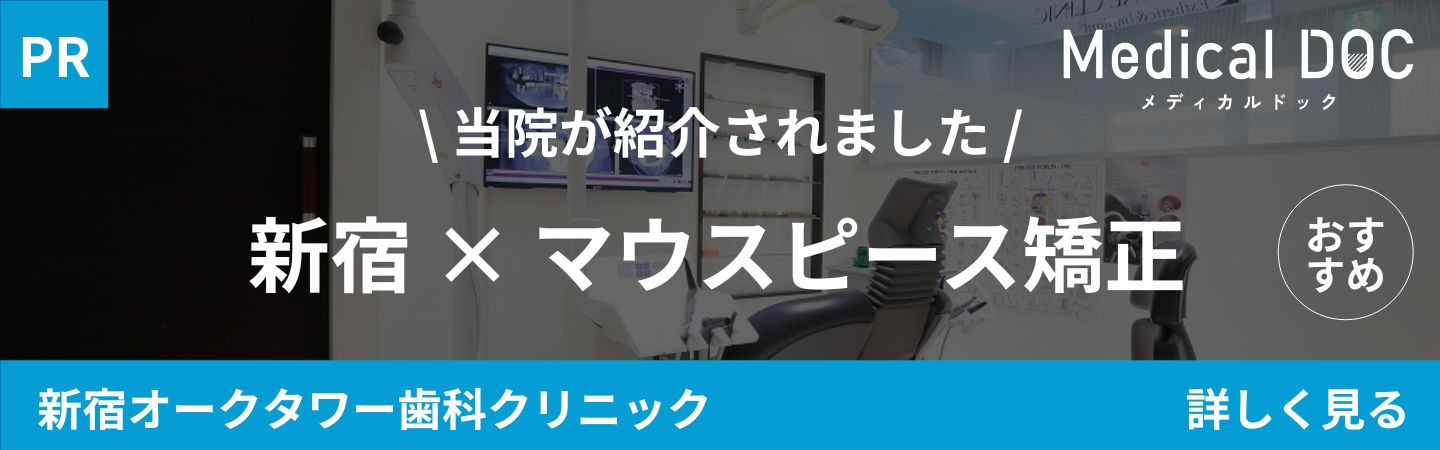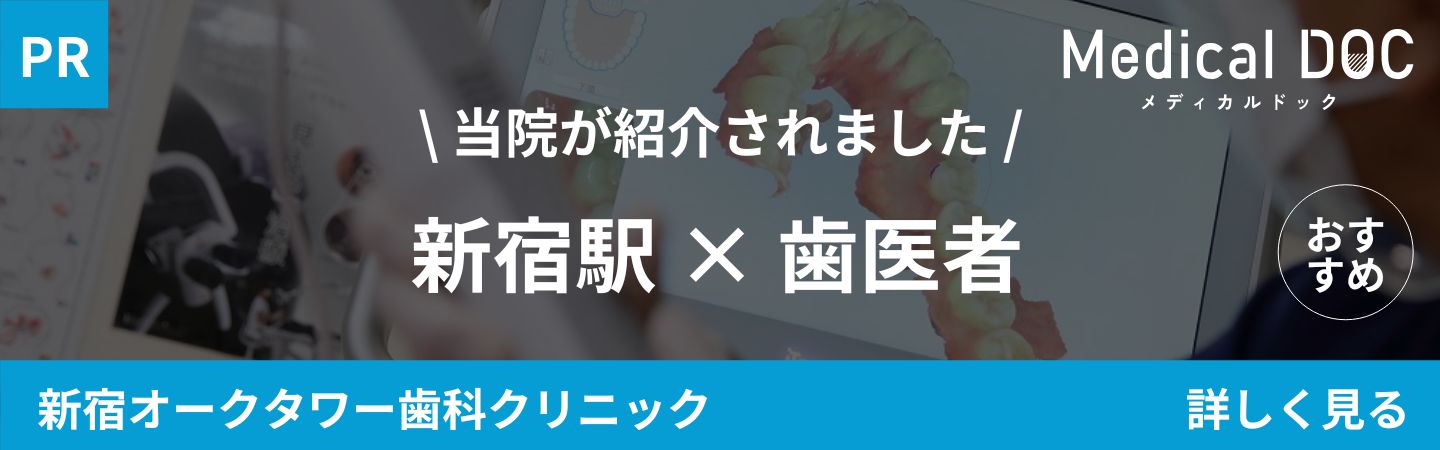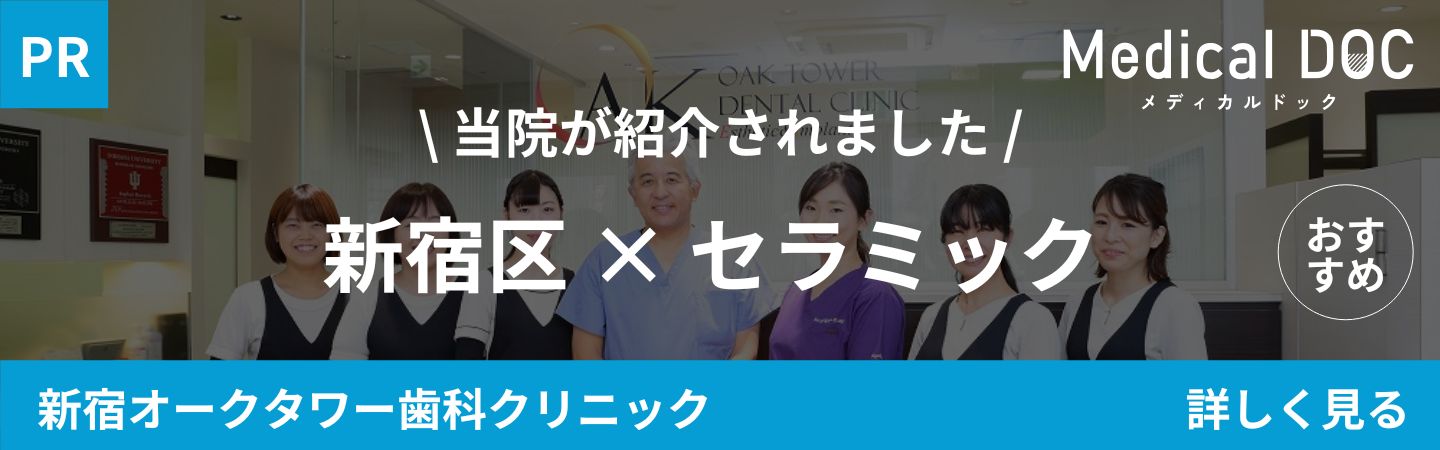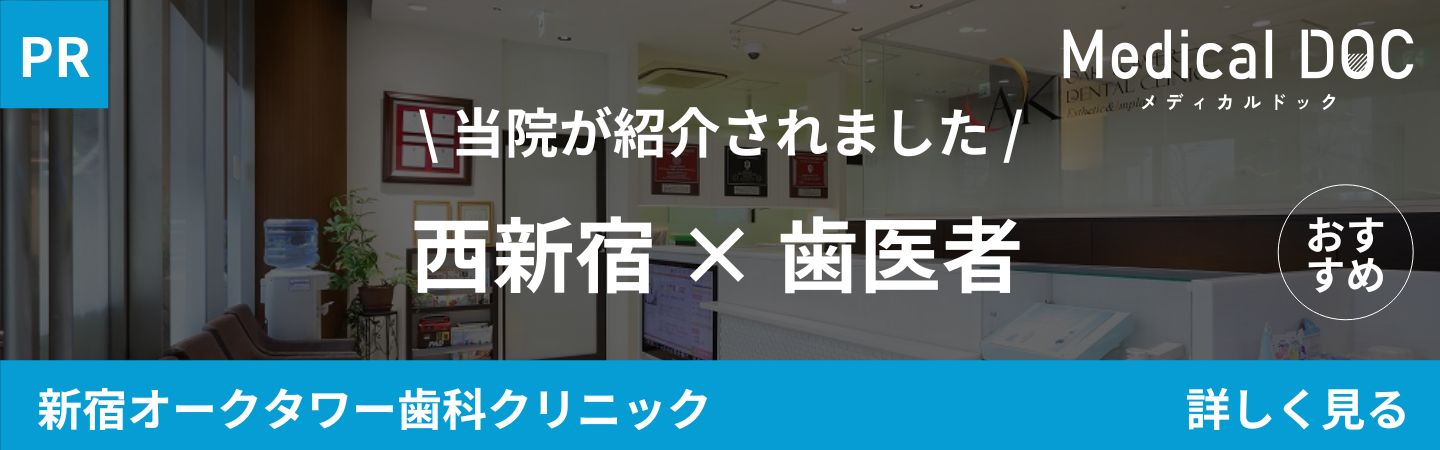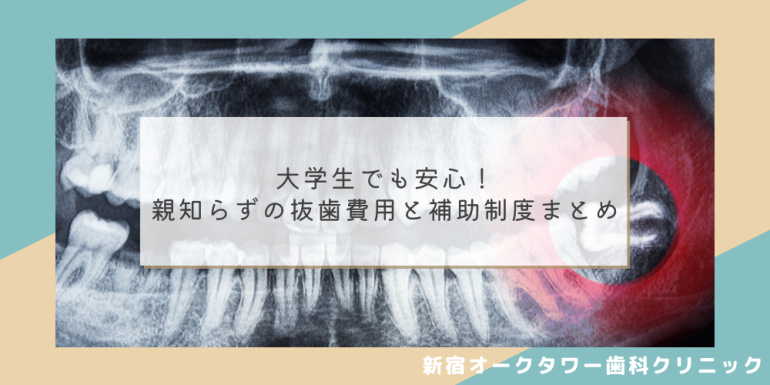
目次
- 親知らずとは?その特徴とトラブルの原因
- 親知らずの抜歯について知っておきたいこと
- 親知らずの抜歯費用と保険適用の仕組み
- 親知らず抜歯後のケアと注意点
- 親知らず抜歯に関するよくある質問
- まとめ:大学生でも安心して親知らずを抜歯するために
親知らずの抜歯は「高額で敷居が高い」と感じがちですが、実際には健康保険が適用されるため大学生の財布でも十分に手が届く治療です。3割負担で済むので、サークル費や家賃をやりくりしながらでも現実的に受けられる価格帯に収まります。授業やアルバイトを抱えつつ痛みや腫れを我慢するより、計画的に抜いてしまったほうがテスト期間の集中力も保てる――これが多くの先輩たちが体験談として語る“抜歯して正解だった”という核心です。
とはいえ、抜歯には「術中・術後の痛み」「腫れや知覚麻痺などの合併症」「予想外の費用負担」といった不安材料がつきまといます。本記事ではそれぞれのリスクを具体的な数字と実例で示しつつ、痛みを最小限に抑える麻酔法や合併症回避のための最新機器、さらには費用面を支えてくれる保険・補助制度の活用術まで網羅的に解説します。読み終わるころには、何を準備すれば安心して手術当日を迎えられるかが明確になるはずです。
厚生労働省の医療統計によると、親知らず抜歯にかかる総医療費の全国平均は約18,600円ですが、健康保険3割負担後の自己負担額はおおむね5,500〜6,000円に収まります。水平埋伏でCT撮影が必要な難症例でも自己負担は平均9,800円程度というデータが大学生協の2023年度調査で報告されており、「バイト1〜2回分で済んだ」という声が多数を占めています。この具体的な金額を知るだけでも、不安はかなり軽くなるのではないでしょうか。
さらに頼もしいのが、大学生ならではの補助制度の存在です。大学生協共済による医療費補填、自治体の歯科健診クーポン、家族が加入する企業健保の付加給付、奨学金機構の緊急小口貸付など、組み合わせ次第で自己負担をゼロ近くまで圧縮できるケースもあります。本文ではこれらの制度を取得条件や申請フローまで掘り下げて紹介しますので、学割感覚で賢く使いこなし、安心とお得を同時に手に入れてください。
親知らずとは?その特徴とトラブルの原因
親知らずの基本情報
親知らずの正式名称は第三大臼歯です。一般的には18〜20歳頃に生えてくるため、高校を卒業して親元を離れる時期とかぶり「親が知らないうちに生えてくる歯」という意味で親知らずと呼ばれるようになったと言われます。4本そろう人もいれば1本も存在しない人もいるなど本数に大きな個人差があります。最近の国内調査では、4本すべてが確認できる割合はおよそ35%、逆に1本もない割合は10%弱とされ、遺伝や顎の大きさが影響していると考えられています。
解剖学的な特徴として、親知らずの歯根(歯の根っこ)は他の大臼歯よりも湾曲や分岐が複雑で、先端が細かく分かれていたり、ねじれた形をしていたりします。そのすぐ近くには下歯槽神経という下唇の感覚を司る太い神経や血管が走行しているため、抜歯時に損傷を避ける技術が必要です。上顎では歯根の先端が上顎洞という空洞と薄い骨一枚で隔てられているケースもあり、上顎洞に穴が開くリスクもあります。こうした“神経・血管との距離が数ミリしかない”という特殊な位置関係が、他の大臼歯と比べて処置を難しくしている最大の理由です。
現代人に親知らずトラブルが増えた背景には、骨格・顎の発達と進化が関わっています。縄文時代の人骨は硬い木の実や干し肉をよく噛んでいたため顎が発達し、親知らずがまっすぐ生えるスペースが十分ありました。ところが加工食品や柔らかいパンが主食になった現代では、噛む回数が減少し顎骨の成長が追いつかないため、歯列の一番奥がスペース不足に陥りやすくなっています。たとえば、柔らかい給食中心で育った平成生まれの世代は、昭和40年代生まれと比べて下顎幅が平均2〜3mm狭いという大学病院の計測データも報告されています。
もっとも、親知らずがあっても必ず抜歯が必要というわけではありません。まっすぐに萌出し上下でしっかり咬合している場合や、完全に骨の中に埋まっていて周囲に炎症が起きない場合は経過観察だけで問題ないことが多いです。レントゲンやCTで神経との距離が十分あり、歯周ポケットが浅いなどリスクが低いと判断されたケースでは、定期的なクリーニングとフッ素塗布で長期的に温存できる可能性があります。抜歯の判断材料としては「痛みや腫れの既往」「歯ブラシが届くか」「隣接歯への悪影響の有無」がポイントになるため、専門医と相談しながら自分の親知らずの状態を把握しておくことが大切です。
親知らずが引き起こすトラブル
親知らず周辺は歯ブラシが届きにくくプラーク(歯垢)が長時間停滞しやすいため、虫歯と歯周病の集中発生地帯になりがちです。実際、国立大学附属病院の臨床統計では、親知らず部位の虫歯発生率は前歯の約6.8倍、歯周ポケット深度4mm以上の割合は7.2倍に達しました。こうした数字が示すとおり、同じ口腔内でも親知らずのエリアだけが突出してハイリスクゾーンになっているのが現実です。
親知らずが半分だけ顔を出す「部分萌出」の状態では、歯冠を覆う歯肉のポケット内に細菌が繁殖しやすく、智歯周囲炎(ちししゅういえん)という強い腫れと痛みを伴う炎症が起こります。炎症が慢性化すると、含歯性嚢胞(がんしせいのうほう)と呼ばれる液体で満たされた袋が顎骨内に形成され、レントゲンでは黒い影として確認されます。嚢胞は徐々に骨を溶かし、最終的には下顎骨を大きく欠損させる恐れがあり、放置期間が長いほど外科的処置が広範囲になる点が要注意です。
横向きに埋伏した下顎の親知らずが手前の第二大臼歯を圧迫するケースも少なくありません。たとえば21歳男性の症例では、初診時パノラマX線で第二大臼歯の遠心面に透過像が認められ、半年後のCTでは象牙質が1mm以上吸収されていました。抜歯と同時に吸収面をコンポジットレジンで修復したものの、処置が半年遅れていれば神経まで達していた可能性が高いと担当医は報告しています。このように、親知らずが直接関与しないはずの健康な歯まで巻き込んでダメージを与える点が見逃せません。
さらに炎症が深部に進行すると蜂窩織炎(ほうかしきえん)を起こし、発熱や開口障害、嚥下障害が現れる場合があります。細菌が血流に乗れば歯性菌血症となり、心内膜炎など全身合併症へ発展することも報告されています。学業やアルバイトに影響が出るレベルまで生活の質を落とす前に、親知らずのトラブルは早期診断・早期対処が必須です。
親知らずの状態による抜歯の必要性
親知らずは生え方と顎骨内での位置関係から①正常萌出型 ②水平埋伏型 ③斜位萌出型 ④部分萌出型の4タイプに大別できます。正常萌出型は上下がしっかり噛み合い清掃も届くためリスクは極小です。水平埋伏型は歯冠が横倒しで第二大臼歯を圧迫しやすく、虫歯・歯周炎の発生率が約5倍に跳ね上がります。斜位萌出型は歯冠が頬側または舌側へ傾き汚れが滞留しやすく、智歯周囲炎の再発頻度が高いことが特徴です。部分萌出型は歯冠の一部だけが露出しており、粘膜のフラップ下に細菌が入り込みやすい状態で、含歯性嚢胞(がんしせいのうほう)形成リスクが3〜4%存在します。このようにタイプ別にリスクプロファイルは大きく異なり、水平埋伏と部分萌出は“早期抜歯候補”に位置付けられます。
画像診断ではパノラマX線よりもCT(コンピュータ断層撮影)が位置関係を立体的に把握できるため有用です。下顎の親知らずであれば下歯槽神経管との距離が2mm以下に迫る場合、術後の知覚麻痺リスクが急増するためピエゾサージェリーや静脈内鎮静の併用を検討します。上顎では歯根と上顎洞底の骨壁が消失している像が確認されたら、抜歯後に口腔と上顎洞が交通する可能性が高まり耳鼻科との協力体制が不可欠です。また歯根湾曲角度が30度を超えるか、歯根先端が舌側皮質骨を突破している場合も手技が複雑化するため、術者経験の豊富な口腔外科専門医を選ぶことで安全性を高められます。
日本口腔外科学会ガイドラインでは「症候性埋伏智歯」「隣接歯に病変を及ぼす恐れのある埋伏智歯」「予防的抜歯が合理的と判断されるケース」を抜歯適応としています。水平埋伏で第二大臼歯にう蝕や吸収が認められる、あるいは部分萌出で反復性智歯周囲炎を起こしている場合は“抜歯を急ぐべき状態”です。一方、完全に骨内に包埋され病変を伴わない埋伏智歯や、正常萌出でブラッシングが良好に行えるケースは“経過観察で済む状態”とされ、年1回のX線フォローで予後を確認すれば十分とされています。
大学生ならではの学業やアルバイトの予定を考慮すると、テスト直前や長期インターン中の抜歯は避けるのが賢明です。試験期間やゼミ発表が終わった直後、あるいは春休み・夏休みの前半に手術日を設定すれば、腫れや痛みがピークとなる術後2〜3日を自宅療養に充てられます。また留学やサークル合宿が控えている場合は少なくとも4週間前に抜歯を完了させておくと、万一のドライソケットや神経症状にも対応しやすいです。カレンダーとシラバスを照らし合わせ、余裕を持った計画的抜歯を立てることで学生生活への支障を最小限に抑えられます。
親知らずの抜歯について知っておきたいこと
抜歯の難易度とリスク
抜歯の難易度は国際的にPell & Gregory分類(レベル1〜4)で評価されます。レベル1は歯冠が歯肉の上に十分露出し、鉗子だけで比較的容易に抜ける状態、レベル2は歯冠が半分以上骨に覆われ、切開と最小限の骨削除が必要、レベル3は歯冠が完全に骨に包まれ、歯根が神経管に近接する難症例、レベル4は水平埋伏下顎智歯のように歯根全体が下顎管と重なり、歯冠も骨内で真横を向いている最難関ケースです。水平埋伏下顎智歯が特に厄介なのは、①歯根が長く下歯槽神経と重なりやすい、②骨を多量に削るため術後の腫脹が強い、③歯冠分割が複数回にわたり手術時間が延びる、といった複合要因が重なるからです。
具体的なリスクを数値で見ると、下歯槽神経麻痺は全抜歯の0.5〜4%、水平埋伏症例に限ると最大で7%まで上昇します。上顎智歯では上顎洞穿孔が0.6〜2%、大量出血(持続20分以上)は0.1%未満と稀ながら重症度が高い合併症です。これらのイベントが発生すると回復に数週間から数ヶ月を要することもあり、術前にリスクと対応策を明確に共有するインフォームドコンセントが不可欠です。「どのリスクが自分に当てはまるのか」「後遺症が出た場合の治療フロー」は手術の安心感を大きく左右します。
リスク軽減策として代表的なのがCT撮影・ピエゾサージェリー・静脈内鎮静法の三本柱です。CT撮影は神経管との距離を0.1mm単位で把握でき、術後麻痺の発生率を概算60%低減させる報告があります。ピエゾサージェリー(超音波骨切削器)は硬組織だけを選択的に削るため軟組織損傷がほぼゼロに抑えられ、術後痛が従来法より平均1.2日短縮したデータが示されています。静脈内鎮静法は全身麻酔ほど大掛かりでなく、意識を保ちながら不安と疼痛を軽減できる点が特長で、処置時間が20%短縮したケーススタディも存在します。
難易度が高いほど懐とスケジュールに響く点も無視できません。レベル1の単純抜歯なら保険3割負担で約3,000円、ダウンタイムは腫れのピークが1〜2日程度です。一方レベル4ではCT(約3,500円)、ピエゾ使用料(施設差ありますが自費5,000円前後)、静脈内鎮静(自費1〜2万円)と積み上がり、総額は1.5万円〜2万円、腫れや開口障害が落ち着くまで5〜7日かかることも珍しくありません。試験直前やアルバイト繁忙期を避け、長期休暇に合わせて手術日を設定すると、学業・生活への影響を最小限に抑えられます。
抜歯前の準備と検査
親知らずの抜歯を安全に受けるためには、まず初診カウンセリングで的確な情報提供が欠かせません。歯科医師は既往歴(喘息・心臓病・出血傾向など)、薬剤アレルギー(ペニシリン、局所麻酔薬、ラテックスなど)、そして現在服用している薬(抗凝固薬、ホルモン剤、サプリメントを含む)を詳しく尋ねます。これらは麻酔選択や止血方法に直結するため、うろ覚えではなくお薬手帳や処方箋の写真を持参すると確実です。さらに、過去の手術経験や針刺し・採血で気分が悪くなった経験なども併せて伝えると、鎮静法の選択肢が広がり、当日の不安を大きく減らせます。
続いて画像診断です。親知らずの全体像を一枚で把握できるパノラマX線は被曝量が約0.02mSv、費用は保険3割負担で600円前後と低コストです。一方、CT(コンピュータ断層撮影)は立体的に神経や血管との位置関係を解析でき、水平埋伏や歯根湾曲が疑われるケースで必須となります。被曝量は0.1〜0.3mSv、費用は撮影・読影込みで3,000〜5,000円程度ですが、大学生協共済の「医療費補填特約」を利用すると自己負担が実質ゼロになることもあります。撮影前に保険証券番号を提示して、対象項目かどうか確認しておくと安心です。
画像でリスクを把握したら、次は全身状態のチェックです。血液検査では白血球数・CRP(炎症マーカー)・凝固系(PT-INR)がポイントで、感染や止血障害を術前に把握できます。海外ではPT-INRが1.5未満なら抜歯後出血リスクが有意に低下するという報告があり、日本でも同じ指標が用いられています。鎮痛薬や抗生剤の事前処方は「痛みが出てから薬局に走る」事態を防ぎ、炎症コントロールを抜歯当日から最適化します。特に智歯周囲炎の既往がある人は、術前48時間から抗生剤を内服すると術後疼痛スコアが30%以上下がると示されており、有効性は高いです。
学業とアルバイトへの影響を最小限に抑えるには、タイムライン設計が鍵です。推奨モデルは「手術1週間前までに全検査と薬の受け取り→2日前にリマインド連絡で不安点を最終確認→前日は23時までに高タンパク質の夕食、深夜の飲食は避け8時間以上の睡眠→当日は友人または家族に送迎を依頼し、帰宅後48時間はシフトを入れない」です。大学が遠方の学生は、オンライン授業がある日を選ぶと登校不要で回復に集中できます。こうしたスケジューリングを事前に立てておくことで、レポート提出や試験勉強といったタスクを遅延させずに抜歯を乗り切ることができます。
抜歯の手順と麻酔の種類
親知らず抜歯で使われる麻酔は①局所麻酔 ②伝達麻酔 ③静脈内鎮静の三方式が主流です。局所麻酔は歯肉に直接薬液を注入し、軽度~中等度の難易度に適します。保険点数は約90点(自己負担270円程度)、感覚が戻るまで60~90分と短めです。伝達麻酔は下顎の太い神経に作用させる方法で、深く埋まった水平埋伏歯に有効です。費用は局所麻酔に数十円上乗せ程度ですが、麻痺範囲が広い分、回復には2~3時間要します。静脈内鎮静は腕の静脈から鎮静薬を投与し「うたた寝状態」で手術を受けるスタイルで、不安が強い人や長時間手術に適応します。自費扱いで5,000~15,000円、覚醒まで30分、帰宅可能になるまで約1時間の観察が必要です。あなたの恐怖心や抜歯の難易度に合わせて、この三つを組み合わせるのがベストと覚えておくと選択がスムーズになります。
手術の流れを時系列で追ってみましょう。最初に麻酔が効いたら「歯肉切開」を行い、メスが入る瞬間は圧迫感だけで痛みは感じません。続いて「骨削除」。ドリルが骨を削る高周波音が耳に響きますが、痛みはゼロで振動のみを感じる程度です。視界に水しぶきが飛ぶのは冷却水が骨の温度上昇を防いでいる証拠なので心配無用です。次は「歯冠分割」。歯を数ピースに割るカリッという音が聞こえますが、実際に触れているのは歯ですから、顎への負担は最小限です。その後「抜去」でピースをピンセットで取り出し、「縫合」で傷口を閉じます。糸が引き締まる感覚はありますが、5分もかからず終了します。全体として15~40分程度が一般的で、患者さんの体感は「引っ張られる圧力と音」だけに集約されます。
近年はエアロター(高速回転切削器)や超音波切削器(ピエゾサージェリー)が登場し、骨削除が劇的に低侵襲化しています。例えば下顎水平埋伏歯で従来40分かかった骨削りが、超音波切削器を用いると15分に短縮され、発熱も抑えられるため腫れが3割減少したという大学病院の臨床報告もあります。エアロターは高速回転で切削面が滑らかになり、歯冠分割後の取り残しを防げる利点があります。一方、超音波切削器は骨は切れるのに軟組織を傷つけにくい周波数帯で振動するため、下歯槽神経を視認しながら安全域ギリギリまで骨を削れる点が特徴です。こうした最新機器の有無はクリニック選びの判断材料にもなるので、事前の見学やカウンセリングで遠慮なく確認しましょう。
抜歯が終わったら術後観察室へ移動し、看護師が血圧・脈拍・酸素飽和度を10分間隔でチェックします。傷口にはガーゼを噛んで圧迫止血を行い、30~45分で交換または除去されるのが一般的です。この間、軽いめまいがあればベッド上で安静を保ち、水分摂取のテストが合格すれば帰宅OKとなります。静脈内鎮静を併用した場合は、完全覚醒まで追加で30分ほど観察し、家族の付き添いが推奨されます。処方薬(鎮痛薬・抗生剤)の説明、次回抜糸予約、緊急時連絡先の案内を受けてクリニックを後にする流れです。当日のスケジュール感を把握しておくことで、授業やアルバイトの調整も容易になり、心の余裕が生まれます。
親知らずの抜歯費用と保険適用の仕組み
抜歯費用の目安
保険証を提示して一般的な3割負担で受診した場合、親知らずの抜歯費用は症例によって大きく変わります。最もシンプルなケースである単純抜歯(まっすぐ生えていて根が分岐していない上顎の親知らずなど)は、診察料・局所麻酔・抜歯処置・投薬を合わせて自己負担額がおおむね3,000円前後に収まることが多いです。一方、骨を削りながら横向きに埋まっている下顎智歯を抜く水平埋伏抜歯では、切開・骨削除・歯冠分割と処置が増えるため点数が高くなり、術前にCT(コンピューター断層撮影)を撮影するとさらに加算が発生します。その結果、自己負担額は概ね8,000〜12,000円の範囲に収まり、大学生協のアンケートでも下顎水平埋伏の平均自己負担は約9,400円という結果が報告されています。
費用の内訳は「診療報酬点数」という国のルールで細かく定められており、これが最終的な請求額を決める仕組みです。まず検査点数としてパノラマX線は1枚で約1,200点(3割負担で約360円)、CTは部位やスライス数により2,000〜4,000点(約600〜1,200円)が加算されます。処置点数は単純抜歯がおよそ300点(約90円)ですが、骨削除を伴う難抜歯は1,000点超(約300円)まで跳ね上がります。そこへ局所麻酔薬や縫合糸などの薬剤・材料点数、術後に処方される鎮痛薬・抗生剤(1日3回5日分で約150点=約45円)が積み重なり、最後に初診料または再診料が合算されるというロジックです。この体系を知っておくと、領収書の「医学管理料」「手術料」などの欄が何を意味するのか一目で理解できます。
保険診療の範囲を超える自由診療が選択されると、費用は一気に桁が変わります。たとえば痛みや恐怖心を軽減するために静脈内鎮静法を併用すると、麻酔科医の立ち会い費用・薬剤費・術後回復室使用料がすべて自費となり、1回につき平均20,000〜30,000円が加算されます。骨を微細に削る超音波メス(ピエゾサージェリー)を使用すると、器材使用料を含めて10,000円前後が上乗せされることもあります。さらに完全個室オペ室や無影灯など特別設備料が設定されているクリニックでは、総額が50,000円を超えるケースも珍しくありません。自由診療は価格が医院ごとの裁量になるため、見積書で内容と価格差を必ず確認することが大切です。
支払った費用は年末調整や確定申告で取り戻せる可能性もあります。医療費控除は1年間に自己または家族が支払った医療費が10万円(または総所得金額の5%)を超えた部分について、所得税や住民税が軽減される制度で、領収書と明細書を保管しておけば抜歯費用も対象になります。例えばアルバイト収入を含めた年間所得が180万円の学生が12,000円の抜歯費用を支払い、同年に急性虫歯治療や薬代で計40,000円を追加で使った場合、合計医療費52,000円から所得の5%にあたる90,000円を差し引くと控除額はゼロですが、高額療養費制度と合わせて考えると別のメリットが生じます。高額療養費制度は月内の医療費自己負担が所得区分に応じて一定額を超えた場合に払い戻しが受けられる仕組みで、たとえば住民税非課税区分の学生なら自己負担上限が月額35,400円に設定されています。親知らず4本を同月に抜歯して自由診療を含め合計60,000円支払ったとすると、約24,600円が後日還付される計算になり、実質負担を大幅に下げることが可能です。
学生向け補助制度や支援策
大学生協共済の「医療費補填特約」は、健康保険の自己負担額をさらに補助してくれる頼もしい仕組みです。たとえば親知らずの水平埋伏抜歯で保険自己負担が9,000円かかった場合、共済は上限10万円の範囲でその50%(4,500円)を給付します。請求の流れはシンプルで、①大学生協のサイトまたは窓口で請求書をダウンロード・記入、②領収書の原本と診療明細をA4コピーし同封、③手術日から90日以内に簡易書留で郵送という3ステップです。書類に不備がなければ約2週間で指定口座に振り込まれるため、授業料や家賃の引き落としに支障をきたす心配もありません。
自治体が配布する成人歯科健診クーポンを活用すれば、抜歯前の必須検査であるパノラマX線撮影費を0円にできるケースがあります。たとえば東京都杉並区では「20歳~25歳歯科健診」クーポンを発行し、提携歯科医院での診察・X線撮影が年度内1回無料です。申込期限は毎年12月末で、区のウェブサイトから電子申請すると2週間ほどで自宅にハガキ型クーポンが届きます。大阪市の「はぐくみ健診」も同様にX線・口腔内検査が無料で、利用には学生証と保険証の提示が必要です。自治体名と期限を忘れずチェックし、検査費を上手に削減しましょう。
保護者の扶養内にある学生は、家族保険や企業健保の付加給付を見逃せません。たとえば大手IT企業の健康保険組合は「高額医療費付加金」として、1カ月あたり自己負担額が2万円を超えた分を全額払い戻します。実際にAさん(21歳)は親の健保に加入しており、抜歯関連費用が総額3万円でした。国保3割負担でAさんが窓口支払いしたのは9,000円ですが、健保から6,000円の付加給付が戻り、最終負担は3,000円となりました。負担割合が実質1割まで下がることも珍しくないため、家族の保険証の裏面にある給付窓口へ事前に問い合わせておくと安心です。
どうしても自己負担を工面できない場合は、日本学生支援機構の「緊急採用・応急採用奨学金」や大学独自の医療費助成制度が救いになります。緊急採用では無利子で最大10万円を即日貸与してもらえる制度があり、必要書類は学生証コピー、診療見積書、指導教員の署名入り申請書の3点です。書類を学生課へ午前中に提出すれば、最短3営業日で振り込まれます。さらに多くの国立大学は保健管理センターを通じて「医療費一部補助」を実施しており、領収書原本と治療報告書を提出すると1〜2割相当が給付されます。申請期限は受診日から30日以内が一般的なので、治療が終わったらすぐ学生課に足を運ぶことが行動のカギになります。
費用を抑えるためのポイント
保険証の種類が学期途中で変わると、同じ治療でも自己負担額が余計に発生するケースがあります。例えば実家の国民健康保険からアルバイト先の企業健保に切り替わったタイミングを大学の窓口に申告し忘れた場合、病院には旧保険証情報が残り続け、3割負担が適用されず10割請求になる事例が少なくありません。医療機関は後日訂正に応じてくれますが、一時的に数万円を立て替えることになり、返金までに2〜3か月を要します。受診前に現行保険証のコピーをスマートフォンに保存し、初診時に提示するだけでこの無駄な出費を確実に防げます。
CT撮影は親知らずの抜歯計画に欠かせませんが、撮影費だけで4,000〜6,000円かかるのが一般的です。大学附属病院で高性能CTを一度撮影し、そのデータをDVDやクラウドで受け取り、町のクリニックへ持参することで重複撮影を回避できます。DICOM(医療用画像データ形式)は全国共通で閲覧可能なので「データ持ち込み可」の歯科医院を予約時に確認すると安心です。筆者の学生相談例では、この方法によりCT費用を2回分抑え、約5,000円節約したケースが複数報告されています。
処方薬にかかる費用も見逃せません。ジェネリック医薬品を指定するだけで、鎮痛薬と抗生剤の合計がブランド品の半額程度になることが多いです。さらに大学周辺の調剤薬局を価格比較すると、同じジェネリックでも20〜30%の差があることが分かります。例えば都内某大学近くのA薬局ではロキソプロフェン錠10錠が210円、一駅離れたB薬局では同じ錠剤が160円でした。処方箋は発行後4日間どの薬局でも使用できるので、アプリで事前に見積もりを取り、最安の店舗で受け取ると着実にコストを下げられます。
年間医療費が1年間で自己負担合計2万円を超えると、確定申告で医療費控除を利用できる可能性が高まります。レシートを撮影して自動仕分けする家計簿アプリを導入し、e-Taxでオンライン申請すれば郵送コストも不要です。実際に親知らず抜歯と虫歯治療を同年度にまとめた学生では、医療費合計48,000円に対して所得税・住民税合わせておよそ15,000円の還付を受け、実質負担が約3割減りました。レシート管理を習慣化するだけで学費や生活費に回せる資金が増えるため、抜歯に限らずすべての医療行為で活用したいところです。
親知らず抜歯後のケアと注意点
抜歯後の痛みや腫れへの対処法
抜歯直後から12時間ほどは麻酔や出血による鈍い違和感が中心ですが、鋭い痛みが強まるピークは統計的に術後24時間前後です。腫れはやや遅れて48〜72時間のあいだに最大化し、その後ゆっくり引いていきます。72時間を過ぎると炎症性サイトカインの分泌が落ち着き、痛みも腫れも半減するのが一般的な経過です。ただし、水平埋伏歯の大規模骨削除を伴ったケースでは回復が1日程度遅れることもあります。
冷却療法はこの時間経過に合わせて行うと効果的です。アイシングの基本は「15分冷却→45分休止」を1セットとして繰り返すことにあります。連続で冷やし続けると血流が停滞し治癒が遅れるため、必ずインターバルを設けます。冷却材は保冷ジェルパックが温度安定性の点で最適ですが、なければ冷凍庫の保冷剤や氷水を入れたビニール袋でも代用可能です。いずれの場合も薄いタオルを1枚挟んで低温熱傷を防ぎ、頬の外側から創部全体を覆うように当てると均一に温度を下げられます。
薬物療法では作用機序の異なるNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)とアセトアミノフェンの併用が推奨されています。例として、ロキソプロフェン60mgを8時間ごと、アセトアミノフェン500〜750mgを6時間ごとの交互服用で痛みを抑えつつ総NSAID量を減らす方法が一般的です。胃の弱い人はNSAID開始と同時に胃粘膜保護剤(プロトンポンプ阻害薬やレバミピド)を追加すると、胃痛や吐き気のリスクを大幅に下げられます。市販薬を自己判断で重ね飲みすると過量投与になる恐れがあるため、処方箋の指示に従い、疑問点は薬剤師に即相談する姿勢が安全です。
痛みと腫れの変化を可視化するために“痛み日誌”をつけるとセルフモニタリングが容易になります。スマートフォンのメモや専用アプリで、①時刻、②痛みの強さを0〜10の数値で評価、③服用薬と冷却時間、④体温を記録しておくと、異常を早期に発見できます。たとえば術後4日目にいったん和らいだ痛みが再び強くなった場合はドライソケットの兆候が疑われるため、日誌を持参して歯科医院に連絡すると診断が迅速です。客観的なデータは医師側の判断材料にもなるため、結果的に治癒を早める助けになります。
抜歯後の合併症リスクと対応策
親知らずを抜いた後にもっとも多く見られるトラブルがドライソケットです。発症率は全抜歯症例の2〜5%ほどと報告されており、血餅(けっぺい:かさぶたのようなもの)が剥がれて骨がむき出しになることで、激しい拍動痛や口臭が数日続きます。0.12%クロルヘキシジン洗口液を術後24時間以降に朝晩30秒ゆすぐだけで、ドライソケット発生率を約40%低減できたという国内外の臨床試験が複数存在し、費用も数百円と手軽な予防策です。
次に心配されるのが下顎の親知らず抜歯で起こり得る下歯槽神経損傷です。下唇やあご先のしびれが特徴で、神経伝導速度(電気刺激が神経を伝わる速さ)が一時的に低下することで感覚が鈍くなります。多くは3〜6か月で自然回復しますが、ビタミンB12の投与により末梢神経の再髄鞘化(神経の再生速度)が約15%向上したという報告や、低出力レーザー照射で痛覚閾値が早期に回復した症例もあり、併用することで回復期間を短縮できる可能性があります。
上顎の抜歯ではまれに上顎洞(じょうがくどう:頬骨内の空洞)と穴がつながることがあります。鼻をかんだ際に血の混じった水が漏れる、鼻血が長引くといった症状がサインです。直径2mm程度までの小さな穴は血餅保護と抗生剤内服で自然閉鎖することが多いものの、3mm以上の場合は口腔外科と耳鼻科が連携し、頬側の歯肉弁を回転させるブッカルフラップ法などで早期に閉鎖します。手術自体は局所麻酔下で20分前後と短時間で終わり、術後1週間程度で日常生活に戻れます。
創部が赤く腫れて38℃以上の発熱や膿汁が出る場合は感染を疑います。第一選択薬はアモキシシリン250〜500mgを1日3回5日間、ペニシリンアレルギーがある人はクリンダマイシン300mgを同様に処方することが一般的です。症状が改善しない、あるいは膿が溜まって開口障害が出てきた場合は、速やかに再受診して切開排膿と洗浄を行う必要があります。無理に我慢すると顎骨炎や敗血症に進行するおそれがあるため、「痛み止めが効かないほど痛む」「口が指2本分しか開かない」といったサインを感じたら迷わず歯科医院へ連絡しましょう。
抜歯後の口腔ケアと歯ブラシの使い方
術後24時間は抜いた穴に血餅(けっぺい)というゼリー状の血のかたまりができ、この血餅が“天然のガーゼ”となって傷口を覆います。うがいをすると血餅が流されてしまい、ドライソケットと呼ばれる激痛状態に移行しやすくなるため、この時間帯は口をゆすぐ代わりに唾液を前に吐き出す程度にとどめてください。25時間以降になれば血餅が線維性ネットワークへと変化し始めるため、生理食塩水を軽く含んで口角を動かさずにそっと流すようにすすぐと、細菌量を抑えつつ血餅は温存できます。
歯磨き再開の目安は術後48時間です。ブラシの毛先を歯面に対して約45度で当て、1〜2mmの幅で小刻みに動かす“バス法”が傷口周辺に最もやさしい動かし方になります。奥歯の裏側など届きにくい部分には毛束が小さいタフトブラシが効果的で、たとえば「ライオン DENT.EX tuft20」や「Ciメディカル Tuft24」はヘッド径が小指の先ほどしかなく、創部を避けながら隣接歯のプラークをピンポイントで除去できます。
プラークコントロールを徹底するには、洗口液とジェルを時間帯で使い分ける方法が合理的です。朝と昼は0.05%フッ化ナトリウム洗口液(例:クリニカアドバンテージ デンタルリンス)を30秒ほど含み、歯質を再石灰化させて初期むし歯をブロックします。就寝前はクロルヘキシジン0.12%相当のジェル(例:コンクールFジェルコート)を豆粒大だけ歯ブラシに取り、創部周辺を避けてゆっくり塗り伸ばすと、夜間の細菌増殖を抑制し歯周病の二次感染を防げます。
術後1週間を過ぎて抜糸が済んだら、口腔ケアの対象を歯以外にも広げましょう。舌表面の舌苔(ぜったい)を舌ブラシで奥から手前へ1回だけやさしくかき出すと、揮発性硫黄化合物が減って口臭対策になります。デンタルフロスは創部が完全上皮化する2週間後を目安に再開し、歯間の炎症をリセットしてください。さらに、ナイトガードやマウスピースを使用している人は、傷口の圧迫を避けるため歯科医師と装着再開時期を相談し、全体の咬合バランスを整えると将来的な顎関節トラブルも予防できます。
親知らず抜歯に関するよくある質問
抜歯のタイミングについて
20歳前後の顎骨は、骨芽細胞と破骨細胞の代謝が最も活発で、海綿骨(スポンジ状の柔らかい骨)が多く含まれています。このため親知らずを抜歯した際の抜歯窩(歯を抜いた空洞)は速やかに血餅で満たされ、コラーゲン線維→未熟骨→成熟骨と段階的に置き換わりやすいという組織学的特徴があります。実際、同じ水平埋伏歯を抜いた場合でも、20歳前後の患者は30代に比べ平均2日早く腫れが引き、知覚異常の発生率も約半分にとどまるという臨床報告があります。早期抜歯は「治癒が速い」「抜歯後の骨欠損が小さい」「周囲の第二大臼歯へのダメージが少ない」といった複数のメリットを同時に得られるのが大きな魅力です。
大学生活は定期試験、実習、サークル合宿、留学などイベントが密集していますが、親知らず抜歯に必要なダウンタイムは平均で3〜7日程度です。カレンダーを俯瞰すると、「春休み前半(2月上旬〜中旬)」「夏休み前半(7月末〜8月第1週)」「後期試験直後の1月下旬」が比較的空白期間になりやすく、術後の腫れや痛みが学業・アルバイトに与える影響を最小限にできます。例えば春休み前半に抜歯した場合、1週間後には新学期の履修登録に支障なく参加できるケースがほとんどです。海外留学を控えている場合は、出発日の4週間以上前に抜歯を終えておくと、再診や万一の合併症対応の時間的余裕が確保できます。
一方、智歯周囲炎などで頬が腫れたり痛みが強い「炎症期」に無理やり抜歯を行うと、出血量が増え、ドライソケット発生率が平常時の約3倍に跳ね上がります。そのため口腔外科では、まず抗生剤を3〜5日間投与して炎症をコントロールし、腫脹が引いた時点で改めて計画的に抜歯するプロトコルが一般的です。このワンクッションを入れることで手術時間が短縮し、術後の腫れも30〜40%軽減すると報告されています。痛みが強いときほど「今すぐ抜いてほしい」と感じがちですが、長期的には沈静化を待つ方が結果的に回復が早く、安全性も高まります。
女性読者の場合、妊娠中はホルモンバランスの変化で歯肉が腫れやすく、妊娠後期は子宮収縮リスクから外科処置が制限されることを知っておくと安心です。つわりや胎児へのレントゲン被曝を避ける意味でも、妊娠計画があるなら事前に親知らずの状態を確認し、必要なら妊娠前に抜歯を済ませるのが理想的です。実際、産婦人科と連携する大学病院では「妊活前の口腔クリーニング&親知らず評価」を推奨しており、抜歯を完了しておくことで妊娠期の歯科トラブルが約60%減少したという報告もあります。将来の安全なマタニティライフのためにも、早めの計画が大きな安心につながります。
歯科医院選びのポイント
親知らずの抜歯を安全に行うためには、まず口腔外科専門医が在籍しているかどうかを確認するのが近道です。日本口腔外科学会は全国の認定医・専門医を公開しており、公式サイトの「認定医名簿検索」ページで郵便番号や都道府県を入力すれば、自宅や大学の近くにいる専門医の氏名・勤務先が一覧表示されます。学会のロゴマークが付いた検索結果には、更新年度や専門分野も併記されているため、例えば「顎関節」「埋伏智歯」など自分のニーズに合った資格を持つ医師かどうか一目で判断できます。学生証を提示して電話をかけ、「親知らずの水平埋伏抜歯を専門医の先生が担当してくれますか」と具体的に尋ねると、受付の対応レベルも同時にチェックできるので一石二鳥です。
次に見るべきは設備です。チェックリスト形式で挙げると、①歯科用CT撮影装置(パノラマだけでは神経管との距離が測れない)、②静脈内鎮静法に対応できる麻酔モニター(パルスオキシメーター・血圧計・ECG)、③ピエゾサージェリーや超音波切削器(骨へのダメージが小さく腫れを軽減)、④クラスB規格の高圧蒸気滅菌機(ヨーロッパ基準で全器材を完全滅菌)、⑤緊急時の酸素ボンベとAED。これらが院内に揃っているかどうかによって、合併症の発生率と術後ダウンタイムが大きく変わります。見学時には待合室のパンフレットや院長ブログにこれらのキーワードがあるか探し、なければ「CTは3D表示に対応していますか」など具体的に質問しましょう。
設備が同等の場合は、口コミ点数より“紹介状数”と“大学病院との連携実績”を重視すると失敗しにくいです。日本歯科医師会の2022年統計によると、年間紹介状30件以上を大学病院へ送ったクリニックは、親知らず抜歯後の再手術率が0.8%と、紹介状が5件未満のクリニック(1.7%)に比べて約半分でした。また大学病院から逆紹介(術後フォローアップを任される)を受ける件数が多い医院ほど、ガイドラインに沿った術前検査を実施している傾向が強いことが報告されています。SNSやポータルサイトの星の数はサクラや一時的な感情に左右されやすいため、客観的に測定できる連携データを優先すると合理的です。
最後に、学生に優しい運営体制かどうかを評価します。夜間(18時以降)や土曜日の外科枠があるか、有休を取りづらい実習期間でも通えるかは重要ポイントです。決済面では保険診療でもキャッシュレス決済に対応し、自由診療分は分割払いが可能か確認しましょう。総合的な比較フレームワークとして「①専門医在籍 ②CT完備 ③連携実績 ④夜間・土曜対応 ⑤キャッシュレス」の5項目を各20点満点で採点し、合計80点以上を合格ラインに設定すると、複数の医院を数字で比べられて迷いが減ります。自分のライフスタイルに合わせて点数配分をカスタマイズすれば、費用と安全性を両立したベストな歯科医院が見つかります。
親知らず抜歯後の生活への影響
抜歯直後の48時間は、硬い物や熱い物が創部を刺激し出血や疼痛を増幅させるため避ける必要があります。しかしエネルギーやタンパク質が不足すると治癒が遅れるので、栄養価を落とさずに食感と温度を調整することがポイントです。具体例としては、牛乳とプロテインパウダーをシェイクした「タンパク質シェイク」で必須アミノ酸を補給し、冷蔵庫から出して10分ほど置いた常温豆腐で植物性タンパク質とイソフラボンを摂取します。また、フライパンに油をひかずに弱火で作るスクランブルエッグは柔らかくビタミンDも豊富で、カルシウム吸収を助けます。ほかに完熟バナナをフォークで潰してギリシャヨーグルトと混ぜれば、食物繊維と乳酸菌を同時に取れるデザートにもなります。
活動再開の目安については、日本口腔外科学会の調査で「下顎水平埋伏智歯を抜歯した大学生156名の平均ダウンタイム」が示されており、軽作業への復帰は2.7日、通常講義への出席は3.2日で可能だったと報告されています。アルバイトもレジ打ちや事務など座位中心であれば3日目から復帰できるケースが大半です。スポーツやサークル活動の再開は、血圧上昇による再出血を避けるため1週間程度空けるのが安全です。特にコンタクト系競技は創部に外力が加わりやすいので、10日間の猶予を見込むと無理なく復帰できます。
術後の腫れを隠す目的でマスクを着用する学生は多いですが、大学によっては教室内での常時着用を推奨する一方、実習科目ではフェイスシールド併用が義務付けられている場合もあります。キャンパスの感染症対策ガイドラインを確認し、腫れが落ち着くまでの約3〜5日間は対応可能なマスク(立体構造で口元に空間ができるもの)を選ぶと楽に呼吸できます。また、抜歯写真をSNSにアップしてしまうと歯肉の生々しい画像が拡散し、思わぬストレスにつながることがあります。周囲からのコメントで不安が増幅するケースもあるため、公開範囲を限定するか、画像共有を控える選択がメンタルヘルスに優しい対策です。必要に応じて大学の学生相談室やカウンセラーに気軽にコンタクトを取りましょう。
抗生剤(例:アモキシシリン)服用中にアルコールを摂取すると、代謝過程でアセトアルデヒドが蓄積し顔面潮紅や動悸を引き起こす「ディスルフィラム様反応」のリスクが高まります。少量でも症状が出るため、処方期間+48時間は禁酒が原則です。また、喫煙はニコチンによる末梢血管収縮で末端組織の酸素分圧が低下し、創傷遅延やドライソケット発症率を非喫煙者の約2倍にまで押し上げます。この機会に禁煙外来を活用すれば、口腔内のみならず全身の健康改善につながります。睡眠時間の確保、砂糖入りエナジードリンクの節制なども含め、生活習慣を見直す好機として術後期間を位置付けると、将来的なむし歯・歯周病リスクも同時に下げられます。
まとめ:大学生でも安心して親知らずを抜歯するために
親知らず抜歯の重要性を理解する
この記事を通して一貫してお伝えしてきたのは、「親知らずは大学生でも保険適用内で抜歯でき、放置するとかえって高くつく」という一点に尽きます。例えば水平に埋まった下顎智歯でも3割負担で8,000〜12,000円前後ですが、放置して第二大臼歯が虫歯・歯周病を併発すると補綴や根管治療で合計50,000円以上になるケースが珍しくありません。数字で比べると“いま8千円”と“将来5万円以上”の差が見え、先延ばしが家計に与えるインパクトは明白です。
もちろん抜歯には短期的なデメリットもあります。術後24時間の痛み、48〜72時間の腫れ、そして1万円前後の自己負担。しかし長期的には隣接歯を守り、含歯性嚢胞や口腔癌リスクを下げるなど、将来の医療費・通院時間・生活の質(QOL)を大幅に節約できます。短期の不快感と長期のメリットを天秤にかければ、合理的な答えはほぼ自動的に導かれます。
実際に行動へ移すために、ここで学んだポイントをセルフチェックシートにしてみましょう。①レントゲンやCTで親知らずの位置・神経との距離を確認したか ②抜歯費用と補助制度(大学生協共済・自治体助成)の有無を把握したか ③試験・アルバイトへの影響を考慮し手術日を決めたか ④術後ケア用の冷却材・鎮痛薬・柔らかい食事を準備したか——この4項目を今日のうちにチェックすれば、明日には予約の電話を入れられます。
親知らずの抜歯は、単なる痛みの解消ではなく「健康への投資」です。20歳前後で抜歯を済ませれば、その後20〜30年にわたって隣接歯を守り続け、将来のブリッジやインプラントに要する数十万円を節約できる可能性があります。時間・お金・QOLをトータルで考えれば、今行う抜歯ほど費用対効果の高い自己投資はありません。今日の決断が、未来の笑顔とゆとりある学生生活、ひいては社会人生活まで支えてくれることを忘れないでください。
費用を抑えながら安心して治療を受ける方法
保険・補助制度・医療費控除をフルに組み合わせる“トリプル活用モデル”を具体例で見てみましょう。例えば22歳の大学生ゆきさんが下顎の水平埋伏智歯を抜歯したケースでは、総額34,000円(診察・CT・抜歯・薬剤の点数換算)が発生しました。ここで公的医療保険の自己負担3割を適用すると支払額は約10,200円に縮小します。さらに大学生協共済の「医療費補填特約」は1日あたり5,000円まで補償されるため、手術当日に5000円を受け取り、実質負担は5,200円へ減少。最後に確定申告で医療費控除を申請すると、課税所得が103万円の扶養内であっても控除額の計算上900円ほどの還付が発生し、年間トータルでは4,300円台まで圧縮できました。手続き自体はオンライン申請が中心で、合計所要時間はおよそ40分。手間に対して削減効果が大きいことがわかります。
診療前に提示される見積書では「検査費」「処置費」「薬剤費」の3項目を確認することがコスト最適化の鍵になります。検査費にはパノラマX線が約1,000円、CTが約3,000円と書かれているかチェックしましょう。CTが5,000円以上で計上されている場合は点数計算ではなく“自由診療バンドル”の可能性があるため再確認が必要です。処置費では単純抜歯(約1,500円)か難抜歯(約5,000円)かで大きく差が出るので、自分の症例分類が妥当かどうか医師に根拠を尋ねます。薬剤費は抗生剤・鎮痛剤・胃粘膜保護剤がセットで500円前後が相場ですが、ジェネリック指定が明示されているかも重要なポイントです。これらを基準とし、相場から1,000円以上高い項目がないか逐一目を通すことで過剰請求を防げます。
カウンセリング時の“費用×安全”交渉術としては、まず麻酔法の選択肢を提示してもらうことが有効です。局所麻酔のみなら追加費用ゼロ、伝達麻酔は+1,000円前後、静脈内鎮静は+10,000円以上と幅がありますが、水平埋伏でも局所+伝達で十分な症例は意外と多いものです。また、既に大学病院で撮影したCTデータをUSBで持参すれば再撮影は不要になる場合がほとんどなので「データ持ち込み割引」を交渉してみてください。さらにピエゾサージェリー(超音波骨刀)の使用料を任意にできないか相談すれば、安全性を確保しつつ5,000円前後のコストダウンが見込めます。医師側も合理的なリクエストには応じやすいため、遠慮せず根拠を示してコミュニケーションを取ることが大切です。
最後に支払い方法を工夫してキャッシュフローを守りましょう。分割払いは病院側が2~3回まで手数料無料で設定している例があり、アルバイト収入が月末に入る学生でも無理なく支払えます。医療ローンは最長60回まで組めますが、金利が年4~8%と高めなので総支払額が増える点に注意が必要です。クレジットカード一括払いにしてポイントやキャッシュバックを狙う方法もありますが、翌月に全額引き落とされるため残高管理が必須です。ポイント還元率1%のカードで1万円決済すると100円相当が戻る計算になり、実質負担のさらなる削減につながります。自分の収入サイクルと利息・ポイントを比較し、最も損の少ない方法を選択することで費用面のストレスを最小限に抑えられます。
抜歯後のケアを徹底して健康な口腔環境を維持する
親知らずを抜いたあとに最も見落とされがちなのが、計画的な再診スケジュールです。口腔外科の追跡調査によると、術後1週間で創部の約80%が上皮化し、1ヶ月で骨の初期再形成が進みますが、6ヶ月までは内部のリモデリングが続いています。このため、多くの大学病院では「1週間・1ヶ月・6ヶ月」の3ステップ診察を推奨し、途中の受診漏れがあると感染やドライソケット再発率が2倍に跳ね上がるというデータもあります。履修やアルバイトの都合で忙しくても、このタイミングだけは優先して予約を確保することが、長期的な口腔トラブル防止への最短ルートになります。
食生活の見直しは創傷治癒を加速させる即効性のあるセルフケアです。精製糖を多く含むドリンクやスナックを控えるだけで、血糖値急上昇による炎症性サイトカインの分泌が減少し、治癒期間が平均1.3日短縮したという臨床報告があります。また、ビタミンCとコラーゲンは結合組織の再構築をサポートする主役で、1日あたりビタミンC500mg・コラーゲン2.5gを2週間継続摂取したグループは、抜歯窩の肉芽形成が30%向上したとの実験結果も。大学生協のコンビニでも入手できる100%果汁ジュースやチキンブロススープを活用すれば、忙しい講義の合間でも無理なく栄養補給が可能です。
創部が落ち着いたあとは、抜歯をきっかけに口腔全体のメンテナンス習慣を底上げする絶好のチャンスです。具体的には、3〜4ヶ月ごとの定期クリーニングと年2回のフッ素塗布をセットにすると、隣接歯の虫歯発生率を45%低減できると報告されています。さらに、デンタルフロスやタフトブラシを日常的に取り入れることで、親知らず喪失後に生じやすい咬合力の偏りを早期に補正できます。抜歯というイベントを「終わり」ではなく「スタート」と位置づけ、セルフケアのPDCAを回すことで、将来の歯科治療コストを大幅に削減できるのです。
長い目で見ると、抜歯後のケア状況はインプラントや矯正治療といった将来のオプション選択にも直結します。創部が健全に治癒し、周囲骨量が維持されれば、必要になったときにインプラント埋入が容易になり、費用も抑えられます。また、親知らず抜歯で生まれたスペースを利用した歯列矯正では、歯の移動効率が最大20%向上するとの統計もあります。今の行動が10年後の自由度を決める――この視点を持つだけで、毎日の歯磨きや定期受診のモチベーションは格段に高まります。未来の自分への最高の投資として、今日から徹底ケアを始めましょう。
少しでも参考になれば幸いです。
自身の歯についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
監修者
東京歯科大学卒業後、千代田区の帝国ホテルインペリアルタワー内名執歯科・新有楽町ビル歯科に入職。
その後、小野瀬歯科医院を引き継ぎ、新宿オークタワー歯科クリニック開院し現在に至ります。
また、毎月医療情報を提供する歯科新聞を発行しています。
【所属】
・日本放射線学会 歯科エックス線優良医
・JAID 常務理事
・P.G.Iクラブ会員
・日本歯科放射線学会 歯科エックス線優良医
・日本口腔インプラント学会 会員
・日本歯周病学会 会員
・ICOI(国際インプラント学会)アジアエリア役員 認定医、指導医(ディプロマ)
・インディアナ大学 客員教授
・IMS社VividWhiteホワイトニング 認定医
・日本大学大学院歯学研究科口腔生理学 在籍
【略歴】
・東京歯科大学 卒業
・帝国ホテルインペリアルタワー内名執歯科
・新有楽町ビル歯科
・小野瀬歯科医院 継承
・新宿オークタワー歯科クリニック 開院
新宿区西新宿駅徒歩4分の歯医者・歯科
『新宿オークタワー歯科クリニック』
住所:東京都新宿区西新宿6丁目8−1 新宿オークタワーA 203
TEL:03-6279-0018